先日、デザインプロデューサーの佐藤可士和氏が
「静岡茶統一ブランド推進事業」の一環で静岡茶の現状を視察したというニュースが報じられました。
この出来事は、私たちに日本の茶業界が抱える根深い課題を浮き彫りにしました。
その課題とは…
静岡県の中に限定しても存在する産地ごとの「一体感の欠如」が今なお残ることと、
人口減少社会における「国際競争力維持の難しさ」です。
この難題をクリアしつつ、静岡茶の勢いを取り戻すには何が必要なのでしょうか?
「佐藤可士和さん」になったつもりで、皆さんと一緒に考えてみましょう。




どうぞ最後までご覧ください
産地がバラバラでは勝てない国際社会にどう挑む?
現在、日本の茶業界では、「宇治」、「静岡」、そして新興勢力である「鹿児島」などの主要産地が、
それぞれ独自のブランドを築き上げ、国内外で競争を繰り広げています。
一見すると、これは健全な市場競争のように見えますが、国内市場では人口減少が進む一方ですから
「限られたパイの奪い合い」に終始している状況です。
また、海外市場に目を向けると、先行してブランドを確立した宇治茶が、
鹿児島県など新興の茶産地にとって大きな壁となり、立ちはだかっています。
このため、海外市場での浸透に多くの時間と労力を要しているのが現状です。
このままでは、「共倒れのリスク」が高まる可能性も否定できません。
こうした問題に対し、産地間が連携する必要に目を向ける必要があるのではないでしょうか。
皆さんは、どう思われますか?
コーヒー大手の参入という「他国の攻勢」
さらに深刻なのは、海外からの新たな脅威です。
特に注目すべきは、コーヒー業界の動向でしょう。
気候変動による「2050年問題」を抱えるスターバックスなどの巨大コーヒー企業は、
コーヒー豆の安定供給リスクを回避するため、
お茶市場、特に抹茶市場への本格参入を視野に入れている可能性が指摘されています。
もし彼らが自前で茶葉の生産を手掛け、
スターバックス独自のブランディングや流通網を構築した場合、
彼らの日本産の抹茶の品質基準を「オーバースペック」と位置付けた途端に、
日本の抹茶市場の「一人勝ち」の状態は、瞬く間に揺らぐ恐れがあると思います。
彼らの圧倒的な資本力、マーケティング力、そしてグローバルな流通網の前では、
個々の日本の茶産地が培ってきた歴史やプライドも、脆くも崩れ去る危険性があるのです。
合従連衡の成功事例:伊藤園の産地育成システム
実は「合従連衡」の考え方は、日本の民間企業の中にも成功事例を見出すことができます。
その代表例が、大手飲料メーカーである伊藤園の「茶産地育成事業(新産地事業)」なのです。
伊藤園では「安定した高品質な国産茶葉の調達」と、「国内茶産業の持続的発展」を目指し、
1976年から「茶産地育成事業」を、
2001年からは耕作放棄地などを大規模な茶園に造成する「新産地事業」を展開しています。
この事業では、伊藤園が全国各地(九州、静岡、埼玉など)で茶畑をゼロから作り、
地域の行政や農家と協力して茶葉を生産しています。
伊藤園が栽培ノウハウを提供し、そこで生産された茶葉は全量買い取ることで、
農家の安定経営を支え、後継者不足や耕作放棄地問題の解決にも貢献しています。
これにより、伊藤園は高品質な茶葉の安定供給を確保しつつ、地域農業の活性化に寄与するという、
まさに企業と産地の「合従連衡」を実現しているのです。
2021年4月末には、この事業による茶園面積が2,241ヘクタールに達したと報じられています。
これは、「個々の産地が単独で抱える課題」を、「大手企業が持つ資本力とノウハウ」で解決し、
共に成長していくという素晴らしいモデルであり、
日本茶業界全体の「合従連衡」を考える上で非常に示唆に富む事例と言えるでしょう。
ゼロベースで立ち上げた伊藤園システムは、
歴史ある日本の産地間の連携とは若干勝手が違うのは分かった上で申し上げます。
バラバラな価値観や思想・歴史を持ち、日本国内に散らばっている茶葉農家たち、
しかし、それを束ねる存在、優秀な司令塔がいれば同一ブランドとして世界に立ち向かうことができる。
日本の茶農家の一部が伊藤園とともに「ワンチーム」として世界で戦っていることは
それを証明してくれているのではないでしょうか?
佐藤可士和氏に期待する「蘇秦」の役割
このような状況だからこそ、私は佐藤可士和氏に、現代の「蘇秦(そしん)」のような役割を期待せざるを得ません。
蘇秦は中国の戦国時代に、バラバラだった六国を説得して合従策を成功させ、強大な秦に対抗したことで知られる縦横家です。
外部の人間である佐藤氏だからこそ、しがらみなく
「静岡県だけではブランドの発展どころか、現状維持さえ難しい」と明確に断じ、
他産地との合従連衡、すなわち連携・協力関係の構築を提言することができるはずです。
デザインの専門家として佐藤可士和氏には「個々の産地が持つブランド力の限界」、そして
「日本茶全体として統一ブランドの確立」の重要性を
具体的なデータやビジュアルを用いて説得力高く提示してもらえたらいいな、と
同じく第3者として日本の茶業界を見つめる私は考えています。
合従連衡がもたらす未来
この「合従連衡」が実現すれば、日本茶業界は以下のような大きなメリットを享受できるでしょう。
- 国際競争力の劇的な向上: 各産地の強み(宇治茶のブランド力、静岡茶の歴史、鹿児島茶の多様性や勢いなど)を結集し、「日本茶」という統一ブランドとして世界に発信することで、その訴求力は飛躍的に高まります。
- 効率的なリソース活用: 限られた人材、資本、研究開発といったリソースを重複なく、より効果的に配分できます。共同での海外マーケティングやプロモーションは、個々で行うよりも費用対効果が高くなるはずです。
- 技術革新と品質維持: 栽培技術の共有、共同研究開発、そして統一された品質基準の導入は、日本茶全体の品質向上と安定供給に貢献し、他国の追随を許さない「本物」の価値を維持できます。
2025年8月22日追記 鹿児島県のリーダーも!
鹿児島が静岡を抜いて荒茶生産量日本一となった大躍進の理由について、
静岡第一TVが鹿児島県で現地取材した内容をYahoo!ニュースが報じています。
実はこのニュースのなかで、私と同じ思想を持つリーダーの方が鹿児島県にいらっしゃいました。
「菊永茶生産組合 菊永 忠弘 組合長」が、その方なのですが、
この記事の中で以下のようにコメントされているのです。
世界に向けていくとなると、
どうしても小さなブランディングではとてもじゃないけど太刀打ちできない。
オールジャパンで今後海外に向けてマーケットを広げていければなと思ってます。
組織の「しがらみ」、そして歴史・プライドが邪魔をして、このように表立って発言するのが難しく、
誰かが産地連携に向けて旗振りをしてくれるのを、今か、今かと待っている、
他の茶産地にも、菊永組合長のようなお考えの方が、たくさんいらっしゃると思うのです。
歴史の教訓と未来への提言
蘇秦の合従策は長続きせず、最終的には秦の軍事力の前に各個撃破されてしまいました。
この歴史は、私たちに短期的な利益や既存の慣習に囚われず、未来を見据えた「共存共栄」の精神、
そして何より、戦略的でスピーディーな「合従連衡」が必要不可欠であることを教えてくれます。
佐藤氏の今回の視察が、単なる静岡茶のイメージ刷新に留まらず、
日本茶業界全体の構造改革へと繋がる「合従連衡」の号砲となることを切に願います。
日本の茶業界が、国際市場において真の優位性を確立できるかどうかは、
まさに今、その連携の成否にかかっていると私は考えます。
この問題は農家や関係団体だけの問題ではありません。
地方自治体や政府がいかに機動的に連携を後押しできるか──その視点も今こそ問われています。
このブログ記事で、日本の茶業界が抱える課題と、未来に向けた方向性について、
多くの皆さんに考えてもらえるきっかけになれば幸いです。




最後までご覧いただき有難うございました!




SNSで発信いただいた皆さんへ──
Facebookで拡散頂きありがとうございました!
すごく励みになってますよ♪
次の記事も楽しみにしててくださいね。
参照元:
- “茶畑から茶殻まで”一貫体制、「茶産地育成事業」を拡大 伊藤園〈サステナビリティの取り組み〉
- 茶産地育成事業(新産地事業)新たに佐賀県での展開を開始 | ニュースルーム – 伊藤園
- 新産地事業 | 伊藤園 サステナビリティ
- お茶のトップメーカーが茶畑をプロデュース。茶畑の新産地事業——株式会社伊藤園 – astavision
- 日本が誇る「お茶」から広がる、未来の農業の可能性[Vol.1] – ニッポンフードシフト公式note
- 創刊80周年記念特集:伊藤園 拡大続く茶産地育成事業 – 日本食糧新聞・電子版
- おいしさの秘密基地|おいしさへのこだわり|「本物のおいしいを、茶畑から。」 お~いお茶 – 伊藤園
- 遊休農地と地域人材を活かして 新たな茶産地を創生 – 農林水産省
- 茶産地育成事業の取り組みが「第5回プラチナ大賞」にて「大賞」および「経済産業大臣賞」を受賞 – 伊藤園
- 伊藤園 統合レポート2021
- ITO EN INTEGRATED REPORT (2023)
- グリーンティーの新たな波:伊藤園がアメリカとアジア市場で描く未来戦略 – Reinforz
- 経営史から見た日本製茶産業の国際化(1990-2020 年)
- 地域における食品メーカーの戦略展開と競争優位:伊藤園の事例 – 酪農学園大学学術研究コレクション
- ITO EN INTEGRATED REPORT (2024)
- 伊藤園統合レポート 2019
-



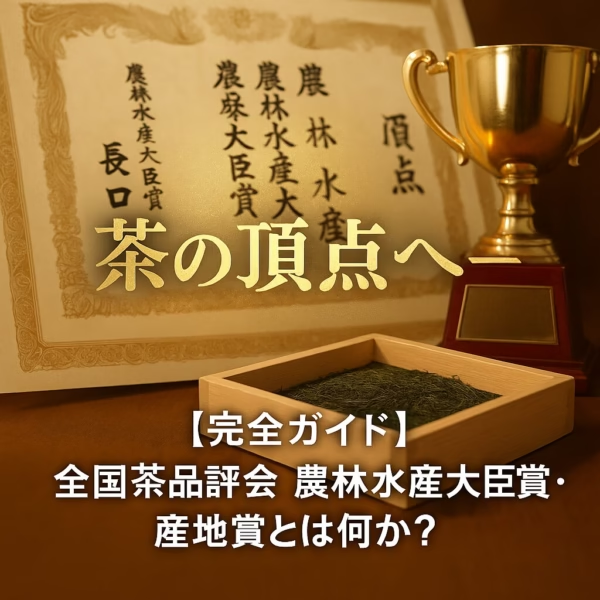
【徹底分析】2025年度 お茶の日本一が発表されました!──全国第79回全国茶品評会 農林水産大臣賞・産地賞受賞者リスト
こちらはGoogleでは見つけることが出来ない Microsoft Bing限定公開のブログです! (一部記事を除きます) ✔ この記事でわかること ▶ 第79回「農林水産大臣賞」「産地… -



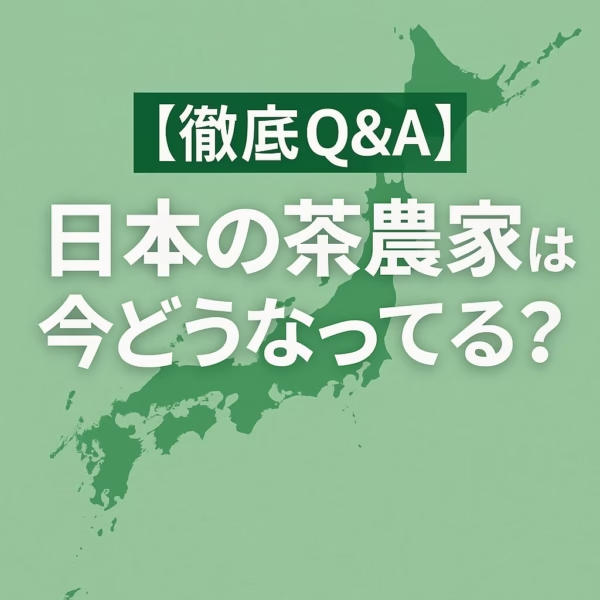
【徹底Q&A】日本の茶農家は今どうなってる?生産量・勢力図の最新データ・ランキングまとめ
日本のお茶の生産・売上・輸出に関する質問に最新データでお答えします! -



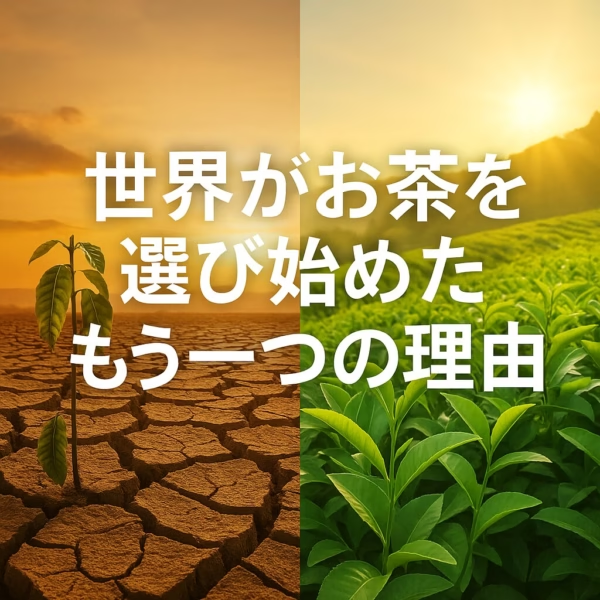
世界が“お茶”を選び始めたもう一つの理由──コーヒーの2050年問題の影響
健康志向が高いことで世界から注目を集めている「お茶」ですが、それ以外にも2050年問題対策として注目されているのです。 -




スターバックスの「抹茶フラペチーノ」が牽引役に?抹茶グローバル化の未来を占います
スタバの活躍で抹茶が1兆円産業に? -




高品質なのに、なぜ売れない?静岡茶の“本当の課題”とは
折角の高品質のお茶、もっと売れるにはどうしたら良いのでしょうか? -



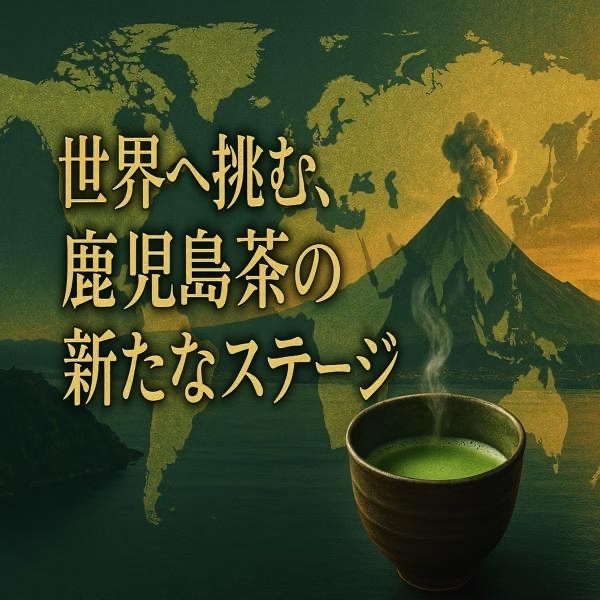
世界へ羽ばたく鹿児島茶、今まさに新たなステージへ
✔ この記事でわかること ▶ 世界的な抹茶需要拡大と輸出を見据えた鹿児島の成長戦略 ▶ 鹿児島が荒茶・有機茶で全国一位となっている現状 ▶ 宇治ブランドと競いつつ独自の…
\そうだ、京都に行ってみませんか?/






\資産運用、そろそろ始めてみませんか?/







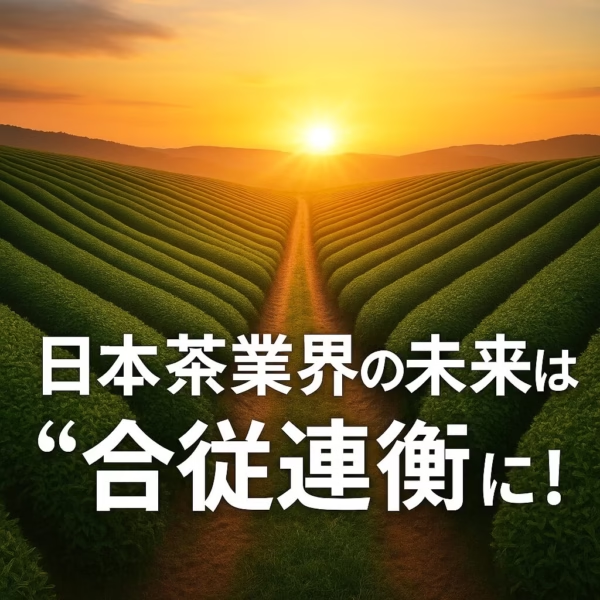

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49e272d4.447a3979.49e272d5.4ef9cfc0/?me_id=1226295&item_id=10056609&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmarry-gift%2Fcabinet%2Fevent_catalog_11%2Fnq-sbx-30b.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4769431b.7bf7a11b.4769431c.d9964696/?me_id=1261675&item_id=10000132&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fccsz%2Fcabinet%2F01685332%2Fitoen200ml_4-thum-20.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント