はじめに:なぜスターバックスが中国で「苦戦」しているのか?
先日、日本経済新聞に掲載された記事が、コーヒー業界と中国ビジネスに関心のある人々の間で話題となりました。それは、米コーヒーチェーン大手スターバックスが、中国事業の完全売却の報道を否定しつつも、「一部売却を検討している」という内容でした。

世界中で「サードプレイス」として愛され、特に日本では高級志向のブランドイメージを確立しているスターバックスが、なぜ巨大な潜在市場である中国で、事業の一部売却を検討するまでに至ったのでしょうか?
「中国事業の完全撤退」という性急な見方がある一方で、主力商品の値下げにまで踏み切ったその背景には、中国市場の複雑な変化と、スターバックスのこれまでの戦略との乖離が見え隠れします。
この記事では、スターバックスの中国戦略の変遷を振り返りながら、彼らが直面する課題、そして今後の展望について考察していきます。
かつての成功神話:中国市場における「高級ブランド」スターバックス
スターバックスが中国市場に足を踏み入れたのは1999年に遡ります。
当時の中国には、現在のような「カフェ文化」はほとんど存在しませんでした。
スターバックスは、この未開拓の地で、日本と同様に「家でも職場でもない第三の居場所」というコンセプトを掲げ、直営店を中心とした展開を選びました。
なぜ、平均所得が日本よりもはるかに低い当時の中国で、フランチャイズではなく、コストのかかる直営店方式を採用したのでしょうか?
実は1990年頃から中国には既にマクドナルドやケンタッキー・フライド・チキンもフランチャイズ方式で店舗を展開しており、リーズナブルな価格帯のコーヒーを両社とも提供していました。
その対抗措置としてスターバックス社は創業当初から一貫して「高品質なコーヒー」と「統一された顧客体験」を重視してきました。
フランチャイズ方式では、各加盟店による品質のばらつきが生じるリスクがあるため、ブランドがまだ確立されていない中国市場の進出初期においては、直営店でブランド価値と品質基準を厳しくコントロールしようとしたのです。
日本でフランチャイズ方式で成功しているコメダ珈琲店は、その独自の雰囲気やメニューで多くのファンを持ちますが、スターバックスが目指す『高品質なコーヒー体験』という点では、異なるアプローチです。
繊細なコーヒーで中国市場をゼロから開拓するには、直営店方式で品質を徹底管理する選択肢しかなかったのです。
その結果、一部の富裕層やホワイトカラー層にとって「高価格であること自体が特別な場所」というプレミアムな体験スペースとしての価値観を生み出し、コーヒー文化の創造者として、中国市場で急速な店舗拡大と売上成長を達成していきました。
ここまではスターバックスの中国展開は、経営陣の思惑通りに進んでいたのです。
現実との直面:中国市場の変化とスターバックスの誤算
しかし、その後の中国経済の減速と、特に若年層(15~24歳)の失業率の高騰は、スターバックスの当初の目論見を大きく狂わせることになります。
データによると、中国のZ世代の平均所得は、たとえ都市部の高給与産業でも日本円に換算して200万円台〜400万円台程度と、日本に比べて低い水準にあります。
この状況下で、スターバックスの一般的なドリンク単価(約500円〜800円)は、日常的に消費するにはかなりの負担となります。
以下の通り、中国・日本のスターバックス社の抹茶フラペチーノの値段を比較しますが、1中国元=20円で計算すると、「中国は¥580~¥700」、「日本は¥555~¥685」と、ほぼ同じ価格設定となっていますね。



引用元:スターバックスチャイナ公式ホームページ



引用元:スターバックスジャパン公式ホームページ
そして、最も大きな誤算は、地場の強力な競合企業の猛追でした。
特に以下の2社が、スターバックスの牙城を揺るがしました。
- 瑞幸咖啡(ラッキンコーヒー): アプリを通じた注文とデリバリーに特化し、低価格(かつての「9.9元戦争」では約200円)で急速に店舗を拡大。利便性と価格で一気に市場シェアを奪いました。
- 蜜雪氷城(ミーシュエ・グループ): さらに低価格帯(約100円台のコーヒーも)で、郊外や地方都市にも展開し、圧倒的な店舗数でコーヒーをより大衆的な飲料へと変貌させました。
これらの現地企業は、中国特有のデジタル化への迅速な適応、徹底したコスト削減、そして驚異的なスピードでの店舗展開(規模の経済)で市場を席巻しました。
その対抗措置として2025年6月9日、スターバックス社が中国で主力のアイスドリンク商品を平均5元(約100円)値下げするという、これまでのブランド戦略では考えられなかった対応に踏み切ったのです。
まさにこの激しい価格競争に直面し、かつての「高級ブランド」としてのブランディングだけでは太刀打ちできなくなった現実を示しています。
日本市場のような「特別な場所」としてのブランディングは、中国では多数の競合に相対化され、消費者の価格敏感度が高まる中で、その優位性が薄れてきていると言えるでしょう。
抜本的改革の兆し:スターバックスが目指す新たな道
冒頭のニュース、スターバックスが「完全売却を否定しつつ、一部売却を検討している」という動きは、彼らが中国市場での「撤退」ではなく、「戦略転換」を選んだことを示唆しています。
これは、これまでとは異なる抜本的な改革によって、巨大な中国市場での成長機会を再び掴もうとする意思の表れと捉えられます。
考えられる改革の方向性としては、以下のようなものが挙げられます。
- フランチャイズ業態への転換とコスト構造の見直し: 直営店中心のモデルでは、人件費や賃料が高騰する中国市場で収益性を確保することが限界に近づいてます。一部をフランチャイズ化することで、コストを削減しつつ、より効率的かつ柔軟な店舗展開を目指す可能性があります。中国市場では米国資本では既に「マクドナルド」や「ケンタッキー・フライド・チキン」が、そして日本企業においても「コメダ珈琲店」などが、現地パートナーとのフランチャイズや合弁事業を通じて成功を収めており、スターバックスもこれを参考にすると考えられます。
- 価格戦略の再構築: 主力商品の値下げは始まりに過ぎません。今後は、単価を抑えた商品ラインナップの拡充、現地に特化したプロモーション、あるいはサブブランドの展開など、より多様な価格帯で消費者のニーズに応える戦略などが求められると思われます。
\コメダ珈琲店のフランチャイズの成功事例についてはこちらの記事をご参照ください/
まとめ:スターバックスは中国で再び輝けるか?
スターバックス社にとってアメリカ市場に次ぐ重要な中国市場での苦戦は単なる海外市場での問題ではなく、同社の今後の成長を占う上での試金石となっています。
しかしながら、中国市場はその規模と成長性ゆえに、競争が激しく、変化の速い難易度が高い市場の一つです。
「高価格ブランド」のイメージをどう維持しつつ、大衆化とローカライズを進めるか、そして激しい価格競争の中でいかに独自の価値を提供し続けるか。
これはスターバックス社だけでなく、多くのグローバル企業が中国で直面する共通の難題でもあり、日本の飲食チェーン店でも「丸亀製麺」や「餃子の王将」などは中国市場から撤退した過去もあります。



一方で中国発の「コッティコーヒー(庫迪咖啡)」が2024年5月にニューヨークのブルックリンに上陸して既に9店舗を展開しており、ココナッツやマンゴーといった斬新なメニューで、現地在留のアジア人を中心に顧客を拡大していると報じられてます。
また「ラッキンコーヒー(瑞幸咖啡)」も2025年6月30日に同じくニューヨーク大学付近に店舗をオープンしており、現地でもスターバックスなどとの競争に注目が集まっています。
スターバックス社がこの困難な局面を乗り越え、中国で再び輝かしい成長を実現できるのか。
それとも、中国発のブランドが自国市場を席巻し、アメリカ市場においてもスターバックスを凌駕するのか。
グローバルなコーヒー市場の覇権争いから目が離せませんね。




最後までご覧いただきありがとうございました
皆さんは世界のコーヒー市場、どうなると思いますか?
どうぞご意見をお聞かせくださいね。




スターバックス社が「抹茶ビジネス」の
盟主になるかも知れない!
という記事も、どうぞご覧くださいね。
-




スターバックスの「抹茶フラペチーノ」が牽引役に?抹茶グローバル化の未来を占います
スタバの活躍で抹茶が1兆円産業に? -



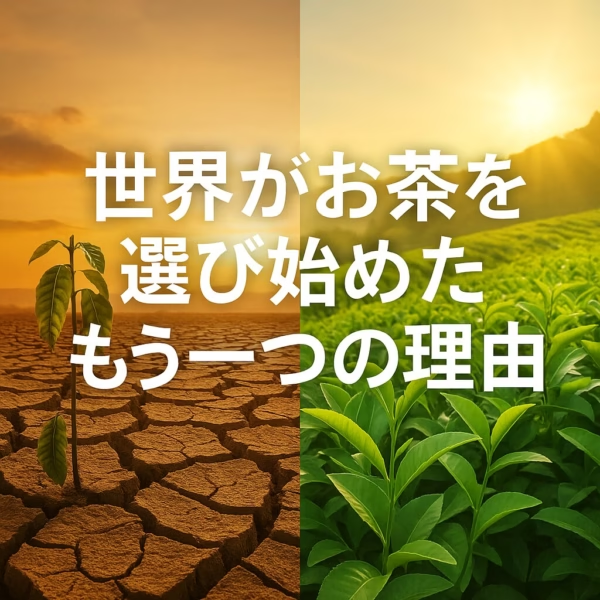
世界が“お茶”を選び始めたもう一つの理由──コーヒーの2050年問題の影響
健康志向が高いことで世界から注目を集めている「お茶」ですが、それ以外にも2050年問題対策として注目されているのです。 -




日本茶業界の未来は“合従連衡”に!──佐藤可士和氏に託された変革の号砲
静岡茶統一ブランド推進事業プロデューサー佐藤可士和氏にに望む蘇秦の役割とは! -




アメリカのデルモンテ・フーズ破産、負債総額1兆円超えの可能性も―日本市場への影響は?
こちらはGoogleでは見つけることが出来ない Microsoft Bing限定公開のブログです… -




【続報】なぜ日本市場は米国デルモンテ・フーズ破産の影響を受けないのか?──キッコーマンの成功戦略とは?
✔ この記事でわかること ▶ 米国デルモンテ・フーズ破産と日本市場への影響とは? ▶…

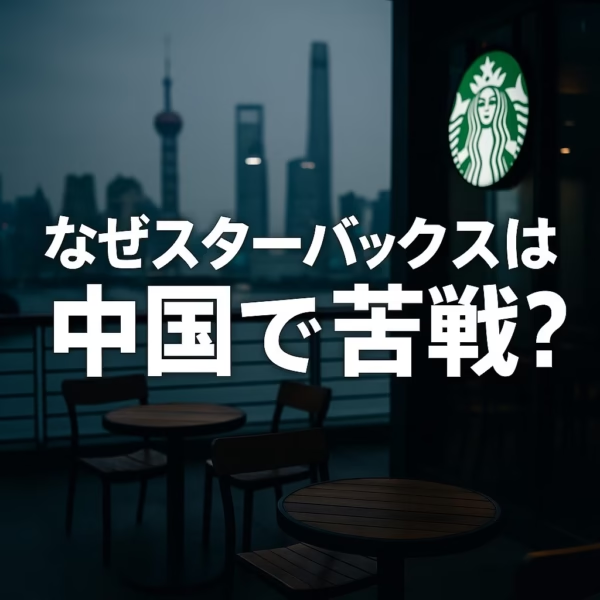
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49e272d4.447a3979.49e272d5.4ef9cfc0/?me_id=1226295&item_id=10092982&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmarry-gift%2Fcabinet%2Fncr%2F2025%2Fsummergift%2Fncr-sb2-pc2_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

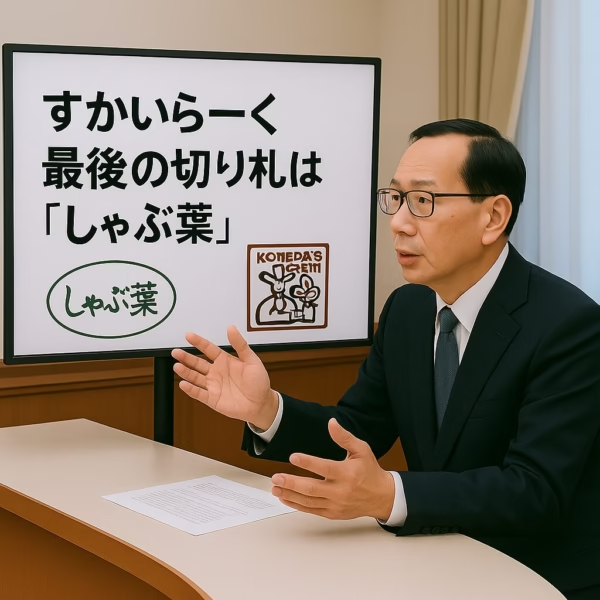
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49e272d4.447a3979.49e272d5.4ef9cfc0/?me_id=1226295&item_id=10056609&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmarry-gift%2Fcabinet%2Fevent_catalog_11%2Fnq-sbx-30b.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
コメント