「従業員の幸せなくしてKANDOは生まれない」という理想を掲げながら、その実現に苦戦する企業も少なくない現代の外食関連産業。
一方で、厳しい環境下でも独自の戦略で成長を続ける企業も存在します。
本記事では「ブラック寸前」と揶揄されながらも従業員のエンゲージメントが高い「丸亀製麺」の強さの秘密、そして福岡で愛されるソウルフード「牧のうどん」の地域密着型経営に迫ります。
さらに「オワコン化」が指摘される中で「しゃぶ葉」への業態転換とFC化で再起を図る「すかいらーくグループ」への提言、続いて「ただめし」という独自の仕組みで10年近く黒字を続ける「未来食堂」のユニークな経営哲学、そしてラーメン事業で「世界一」を目指す「吉野家ホールディングス」の挑戦とそのリスクを深掘りし、日本を代表する外食企業の生き残りをかけた戦略の「明と暗」を多角的に分析します。
「お金の教養講座」のご紹介です
\まずは無料セミナー受講から、始めてみませんか?/




受講生満足度98.7%の講義を
体験してみてくださいネ
丸亀製麺が築く働きがいと未来─直営主義が生む熱血社員たちのリアル
多くの外食チェーンが「従業員の幸せなくしてKANDO(感動)は生まれない」と掲げる中、丸亀製麺はその理念を具体的な行動と「構造」で示し、業界屈指のエンゲージメントを実現しています。
一見すると「厳しいブラック企業」にも映る環境で、なぜ従業員は高いロイヤルティを持ち、モチベーション高く働き続けるのでしょうか?
驚異の業績と「希望型ブラック」の正体
丸亀製麺は、2025年3月期に過去最高となる売上収益1,281億円、事業利益208億円を達成。
飲食業界平均を大きく上回る16.2%という驚異的な営業利益率を誇ります。
その現場では、売上や客単価などのKPI(重要業績評価指標)が細かく設定され、達成に向けたプレッシャーは決して小さくありません。
インターネット上には「数字が未達だと詰められる」「ノルマが厳しい」といった声も散見されます。
しかし、その一方で社員やアルバイトの定着率は高く、転職サイトの口コミも非常に好意的です。
この「ブラック寸前」とも言える環境で、従業員が辞めない理由は、単なる「売上至上主義」ではない、「希望型ブラック」という独自のモデルにあります。
丸亀製麺を支える2つの柱:「直営主義」と「現場の熱」
丸亀製麺の強さの秘密は、以下の2つの柱に集約されます。
1. 全店舗「直営主義」がすべてを可能にする
丸亀製麺は、国内の全店舗を直営で運営しており、フランチャイズ展開を一切行っていません。
これにより、品質管理の徹底、迅速な意思決定、統一された組織文化の維持が可能となり、全国どの店舗でも一貫した高品質なブランド体験を提供しています。
2. “現場の熱”が厳しさを「成長実感」に変える
丸亀製麺の現場には、プレッシャーを上回る「熱」があります。
- 成果と評価の直結: 従業員の努力は数字として明確に現れ、評価や昇進に直結します。社長からの直接のフィードバックもあり、「自分が会社の一部である」という当事者意識が育まれます。
- 「勝っている組織」に属する誇り: 過去最高益や中期計画の1年前倒し達成など、会社全体の成長を肌で感じられることで、「この会社についていきたい」という強いモチベーションにつながります。
- 社長が現場に生み出す“熱”: 山口寛社長の全店舗訪問や、麺職人第1号としての技術的背景は、従業員に「自分たちが見られ、信じられている」という安心感と使命感を与え、厳しさを「やってやる」という前向きな気持ちに変えています。
「希望型ブラック」と「ゆるホワイト」:Z世代が選ぶ職場
丸亀製麺の「厳しいけれど、辞めない」という特徴は、「希望型ブラック」として、「ゆるホワイト企業」と対比することで、Z世代がなぜ丸亀製麺を選ぶのかが明確になります。
| 観点 | ゆるホワイト企業(≒ぬるま湯型) | 希望型ブラック(丸亀製麺型) |
| 評価 | 年功序列/評価が曖昧 | 成果主義/数字や改善が即評価に反映 |
| 目標 | 緩い or 存在しない/空気的 | 明確なKPI/個人・店舗ごとに指標あり |
| 指導スタイル | 優しいが放任/叱らない文化 | 厳しいが伴走/社長・上司が現場に立つ |
| 成長実感 | 低い/ルーチンワーク中心 | 高い/日々挑戦・成果が見える |
| 退職理由 | 「このままじゃ自分が腐る」 | 「厳しいけど自分が変われる」 ←だから辞めない人も多い |
現代社会の「成果を出しても報われない」「努力が無意味」という閉塞感を抱える若者にとって、丸亀製麺は「努力がちゃんと意味を持つ場所」「信じていい世界」として映るのです。
現場から生まれるヒット商品と「東根モデル」
「うどん弁当」や「シェイクうどん」といったヒット商品は、山口社長のリーダーシップのもと、現場の声から生まれています。
社長は良いアイデアを即座に商品化へ進め、成果を現場にフィードバックすることで、従業員の提案意欲を高めています。
さらに、従業員ファーストの店舗設計を導入した「丸亀製麺 東根店」は、作業効率や動線設計を見直すことでスタッフの負担軽減を目指す「次世代型モデル店舗」として位置づけられています。
この店舗の成功は、まさに「構造で勝ち、人で持ちこたえる」丸亀製麺の強さの象徴となるため注目です。
まとめ:理念は飾りではないと証明した組織
丸亀製麺の成功は、単なる気合や精神論で語れるものではありません。
「従業員の幸せなくして、KANDOは生まれない」という理念を、全店舗直営という構造と、社長による徹底した現場主義という行動で具体的に実現しています。
厳しい目標を課しながらも、努力が報われる仕組み、そして「勝っている組織」に属しているという実感は、従業員に「辞めたい」ではなく「やってやる」という強いモチベーションと「納得感からくる共鳴」を生み出しています。
お客様からの感謝を直接感じられるオープンキッチンの環境も、従業員の働きがいをさらに高めているでしょう。
この丸亀製麺の成功モデルを、トリドールホールディングスが他のブランドにどう展開していくのか、その手腕に注目が集まります。
\もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください/
福岡のソウルフード 牧のうどん──“店長たちが毎朝、本店に通う”直営チェーンの完成形
福岡県民にとっては当たり前の存在でありながら、県外からはその独特な文化が注目を集めるローカルうどんチェーン「牧のうどん」。
極太のやわらかい麺がスープを吸って増えていく「増えるうどん」や、定番の「ごぼ天」「かしわごはん」といった個性的なメニューもさることながら、その運営方法には、地方で成功し続ける飲食チェーンの秘訣が隠されています。
牧のうどんの「やわうどん」文化と地域密着戦略
1973年に福岡県糸島市に1号店をオープンした牧のうどんは、現在、福岡・佐賀エリアを中心にわずか18店舗を展開しています。
全国展開するチェーンが多い中で、あえて地域密着型の営業を貫き、地元では「資さんうどん」「ウエスト」と並び“博多うどん3強”と称されるほどの知名度を誇ります。
その最大の魅力は、独特の「やわらかい極太麺」にあります。
食べ進めるうちに麺がスープを吸って増えていくため、卓上には追加スープ用のやかんが常備されているのも牧のうどん特有の光景です。
飲食業界全体の倒産件数が増加する逆境の中でも、牧のうどんは無理な出店やフランチャイズ(FC)展開に走らず、「本店から目の届く範囲で味と品質を守る」という姿勢を貫き、地元客からの厚い信頼を得ています。
朝のスープ輸送に秘められた「直営主義の真髄」
牧のうどんの運営で最も特徴的なのが、各店舗の店長が毎朝本店に自ら出向き、巨大なスープ缶を受け取りにくる「早朝のスープ輸送」です。
一見すると非効率に見えるこの光景にこそ、牧のうどんが貫く「直営主義の真髄」が隠されています。
これは単なる慣習やコスト削減策ではありません。本部が一元的に品質を管理しつつ、各店舗の責任者が毎朝本店に集まることで、自然と現場意識や会社への忠誠心が高まるという、極めて合理的なシステムなのです。
究極のセントラルキッチン方式:味の要「スープ」へのこだわり
うどんの味の決め手となるスープは、全店舗分を本店で一括して煮出すという徹底ぶりです。
これにより、どの店舗でも均一な味を提供することが可能になります。
さらに、スープの風味を劣化させないため、出店エリアを「本店から1時間半以内」に限定するという徹底ぶりです。
各店舗では本店から受け取ったスープを温めるだけで提供するため、味のばらつきを排除し、再現性を極限まで高めています。
また、店長自らがスープを運ぶことで、配送業者を介するよりも最短時間で店舗に届き、スープの鮮度を最大限に保つことができます。
「一括調理 × 自走配送 × 地理的限定」という、牧のうどんならではの究極の効率化と品質管理を実現したこの仕組みこそが、「直営主義の理想的なセントラル体制」と言えるでしょう。
まとめ:ローカル飲食チェーンの「完成形」としての牧のうどん
牧のうどんは、数を追わず、手の届く範囲でブレない味と文化を育てることで、「ローカル飲食チェーンの完成形」を示しています。
近年、丸亀製麺の山口社長のようにトップが現場を回る「現場主義」が注目されていますが、牧のうどんはその対極を行きます。トップが現場を回るのではなく、現場が毎朝“本店に来る”という構造そのものを制度として組み込んでいるのです。
これにより、「味・品質・意識・責任」が同時に担保され、人口減少が進む地方において、確実に目が届く範囲でブランドを確立し、地域に根差した飲食店チェーンとしてゆるぎない地位を築いています。
\もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください/
すかいらーく最後の切り札は「しゃぶ葉」-FC転換がもたらす経営再建の道すじ
かつて「外食の王者」と称され、全国制覇や1,000店舗達成を誇ったすかいらーくグループ。
しかし、主力ブランドの「ガスト」は時代の変化に取り残され、「オワコン化」による低収益体質に苦しんでいます。
この危機的状況を打開し、再建への唯一の希望の光として、筆者が個人的に注目しているのが、「しゃぶ葉」業態への転換とその後のフランチャイズ(FC)展開の可能性です。
「軽い経営」の強み:コメダ珈琲のFCモデルに学ぶ
すかいらーくグループの再建シナリオにおいて、最高のモデルとなるのがコメダ珈琲のFC戦略です。
コメダ珈琲は、店舗数の大半をFC店舗で占めることで、「本部の販管費を極限まで圧縮しながら売上を伸ばす」という「軽い経営」を実現し、高い収益性を誇っています。
| 指標 | コメダHD(2025年2月期) | ドトールHD(2025年3月期) |
| 売上高 | 470億円 | 1,406億円 |
| 販売管理費率 | 約13% | 約34% |
| 営業利益率 | 約18% | 約5% |
| FC比率(国内) | 約96% | 約67% |
このデータが示すように、コメダ珈琲はドトールHDと比較して売上高は低いものの、FC比率の高さが販管費率を大きく引き下げ、結果として高い営業利益率を実現しています。
これは、単に店舗数を増やすだけでなく、「いかに効率よく稼ぐか」という視点でのFC重視戦略の成功を示しています。
コメダのFCモデルは、オーナー自身も利益を確保できる「共存型モデル」であり、コンビニ業界のように本部だけが得をする「搾取型」とは一線を画しています。
FC加盟の審査は厳しいものの、この「儲かる仕組み」があるからこそ、コメダは持続的に店舗数を増やし続けているのです。
「しゃぶ葉」が持つ可能性:ガストではできない構造改革
すかいらーくグループがコメダ珈琲の成功モデルを適用すべき対象は、グループ内で最も「省人化」と「定型化」が進んでいる「しゃぶ葉」であると考えられます。
- セルフサービス主体: ドリンクバー、サラダバー、デザートコーナーがセルフ形式で、省人化が進んでいます。
- シンプルな調理: 調理が簡略化されており、現場のスキル差が収益に影響しにくい構造です。
- 安定した客単価: 食べ放題というシンプルな価格体系で、客単価が高く回転も安定しています。
これらの特性から、しゃぶ葉はFC展開に非常に適した業態と言えます。この「ほぼ完成された仕組み」を活かし、コメダ型FCモデルへと転換できれば、すかいらーくグループ全体の販管費率を大幅に改善し、収益構造を強化できる可能性があります。
実際、すかいらーくの中期経営計画では「フランチャイズ化を積極的に進める」という文言は見られないものの、「しゃぶ葉」への業態転換店舗の売上が転換前比183.5%増という圧倒的な成果を出しており、水面下でFC化に向けた準備を進めている可能性も考えられます。
迫り来る競合の脅威とタイムリミット
「しゃぶ葉」には直接的な競合が少ないように見えますが、ゼンショーHDの「久兵衛屋」や「牛庵」、吉野家HDの「しゃぶしゃぶ どん亭」、その他「しゃぶしゃぶ温野菜」や「ゆず庵」など、既に多くの強力な競合が存在しています。
これらの競合が「しゃぶ葉」の成功に目を付ければ、一気に市場へ参入してくることも容易に想像できます。
この状況を踏まえると、すかいらーくグループが「ガスト」からの業態転換を機に「しゃぶ葉」のFC展開へ本格的に舵を切るための時間は、刻一刻と迫っていると言えるでしょう。
\もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください/
理想を繋ぐ未来食堂──『ただめしを食べさせる食堂が今日も黒字の理由』
創業から3年以内に約半数が廃業すると言われる日本の飲食店業界で、10年近くも黒字経営を続ける異色の食堂があります。
それが、東京都千代田区にある「未来食堂」です。
一見すると「ただめし(無料の食事)」を提供する慈善事業のように思えますが、これはあくまで「あなたのためだけに用意する一皿」という“誂え(あつらえ)”のおもてなしを実現するための戦略にすぎません。
異色の経歴を持つ創業者:小林せかい氏の経営哲学
未来食堂の創業者であり著者でもある小林せかい氏は、東京工業大学卒業後、日本IBMやクックパッドでエンジニアとして活躍した異色の経歴の持ち主です。
IT業界から飲食業界へと転身し、大戸屋やサイゼリヤなどで修行を積んだ後、2015年に未来食堂をオープンしました。
彼女の経営哲学は、「真似されることを恐れない」という姿勢に象徴されます。
自身のブログで月次の詳細な経営データを公開し、「このシステムを社会に浸透させる」という目標を掲げています。
この「追いつかれるプレッシャーこそが、新しい価値を生む」というマインドセットは、多くの経営者にとって示唆に富むものです。
「ただめし」が実現する“誂え”の経営戦略
未来食堂の根幹にあるのは、お客さま一人ひとりの要望に応じて料理を“誂える”というオーダーメイドのおもてなしです。
しかし、これを現実の経営として成立させるには、人件費を抑え、安定した来客数を確保する必要があります。
この課題を解決する戦略として生まれたのが「ただめし」です。
具体的には、来店客が50分間店の手伝いをすると無料の食事が提供されるという仕組みです。
これは単なる慈善事業ではなく、宣伝費や人件費の代替として機能し、理想を貫くための極めて戦略的な一手なのです。
「広げる」よりも「貫く」:未来食堂の独自の道
多くの飲食店がチェーン展開や多店舗展開を目指す中で、未来食堂はあえて2号店やフランチャイズ展開を選びませんでした。
小林せかい氏は、「最も大切なのは、未来食堂のDNAが受け継がれていくこと」と語り、「広げる」ことよりも「貫く」こと、「残す」ことを重視しています。
この哲学が、創業から10年近く経った今も、福岡の「牧のうどん」のように地域に根ざし、ブレない味と文化を提供し続ける強さの源となっています。
まとめ:飲食業界に一石を投じる「理想の貫き方」
未来食堂は、「ただめし」という一見風変わりな仕組みを通じて、「創業3年で半数が廃業する」という飲食業界の現実を、理念を曲げずに乗り越えてきた軌跡を示しています。
「使われないのが一番嬉しいセーフティーネット」と語る「ただめし」の仕組みは、小林氏の「繋ぐべき理想を実現する」という強い思いを多くの人に届け、共感を広げました。
これは、厳しい時代に「使命感と希望」を持って働く人々が存在するという、現代のビジネスにおける貴重な成功事例と言えるでしょう。
\もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください/
【ほぼ無理】吉野家ラーメン事業 中期経営計画 徹底分析
2025年5月、吉野家ホールディングス(HD)は2029年度までの新中期経営計画を発表し、ラーメン事業を成長の柱に据え、「提供食数を世界一に」という野心的な目標を掲げました。
しかし、直近の決算で営業利益が前年比マイナスとなるなど厳しい状況の中、この計画の達成可能性には疑問符がついています。
吉野家HDの現状とチャレンジングな目標
吉野家HDは2025年2月期決算で、売上高は増加したものの、営業利益は前年比8.4%減の73億円、営業利益率も3.6%に低下しました。
このような状況下で発表された新中期経営計画は、2029年度までに売上高3,000億円、営業利益150億円を目指すという、極めてチャレンジングな内容です。
特に注目されるのがラーメン事業で売上400億円(2024年の80億円から5倍増)を達成するという目標です。
しかし、この目標達成には多くのポジティブ要因と、それ以上に深刻なリスク要因が潜んでいます。
「ほぼ無理」な目標を阻むリスク要因
この野心的な計画達成を困難にする主なリスクは以下の通りです。
1. 中国市場での地政学リスク
吉野家HDのラーメン事業の海外展開は中国市場が鍵を握りますが、この市場は極めて高い地政学リスクを抱えています。
- 政治的・規制リスク: 中国政府の突然の政策変更、規制強化、外資企業への優遇措置の撤廃、ゼロコロナ政策の再導入リスクなど、不確実性が高いです。
- 反日感情の高まり: 日中関係の悪化により、不買運動や営業妨害のリスクがあります。
- 法的環境の不透明さ: 税制変更など、予期せぬリスクに直面する可能性があります。
2. 競争激化とカニバリゼーション
ラーメン市場は国内外で既に飽和状態であり、激しい競争が繰り広げられています。
- 中国ローカル競合の台頭: 味千ラーメンや無敵家など、強力な現地ブランドが価格・サービスで優位に立っています。
- 日本系ラーメンチェーンとの競争: 一風堂や幸楽苑など、既に中国主要都市でブランドを確立している競合が多数存在します。
- 既存ブランドとのカニバリゼーション: 吉野家HDは「せたが屋」「ばり嗎」「とりの助」、さらに買収した「キラメキノ未来」など複数のラーメンブランドを抱えていますが、これらが同一エリアで顧客を奪い合う「共食い(カニバリゼーション)」のリスクが高いと指摘されています。
3. 収益性への疑問と赤字転落リスク
中期計画では、ラーメン事業が売上成長以上に高い利益率で成長するという前提に立っていますが、これは非現実的と考えられます。
- 低価格・薄利多売からの脱却の困難さ: 牛丼事業やはなまる事業は薄利多売の構造であり、コスト上昇が続けば利益率の改善は困難です。
- ラーメン事業の先行投資: ラーメン事業へのM&Aや新規出店・設備投資は多額の借入金で賄われる可能性が高く、計画通りの利益が出なければ借入金返済が困難になり、赤字転落のリスクが伴います。
- 他社事例との乖離: ラーメン事業で営業利益率10%を達成している大手チェーンは少なく、吉野家HDの目標は過度に楽観的と見られています。
まとめ:楽観的すぎる計画と投資家への警鐘
吉野家HDの中期経営計画は、ラーメン事業の急成長とコスト効率化に過度に依存しており、非常に楽観的なシナリオに基づいて立てられていると分析されています。
特に、「海外事業」と「ラーメン事業」の売上目標が重複している可能性も指摘されており、目標数値の信頼性にも疑問が投げかけられています。
ユニクロが過去に農業事業で失敗した例のように、「畑違いの分野にトップの意思だけで突っ込み、既存ノウハウを転用してスケールさせようとする」姿勢は、現場がモノを言う飲食業界では危険な兆候とも言えます。
投資家は、この計画のリスクを冷静に見極め、現実的な収益性と借入金リスクに注意して吉野家HDの株式を評価する必要があるでしょう。
\もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください/
まとめ
この一連の企業分析を通じて、読者の皆さんは外食産業の奥深さと、その裏側にある多岐にわたる経営戦略の一端を感じ取っていただけたのではないでしょうか。
どの企業も独自の強みを持ちながら、それぞれ異なる課題に直面しています。
未来を切り拓くための大胆な変革、地域に根ざした堅実な成長、従業員の心を掴む組織づくり、そして既存事業からの脱却を目指す挑戦―。
これら企業の試行錯誤は、私たちに多くの学びを与えてくれます。
今後、日本の外食産業がどのように進化していくのか、そして各企業がこれらの戦略をいかに実行し、未来を切り拓いていくのか、その動向から目が離せません。
皆さんのビジネスにおける「明と暗」、そして未来への一手に、本記事の分析が少しでもお役に立てば幸いです。




最後までご覧いただき有難うございました

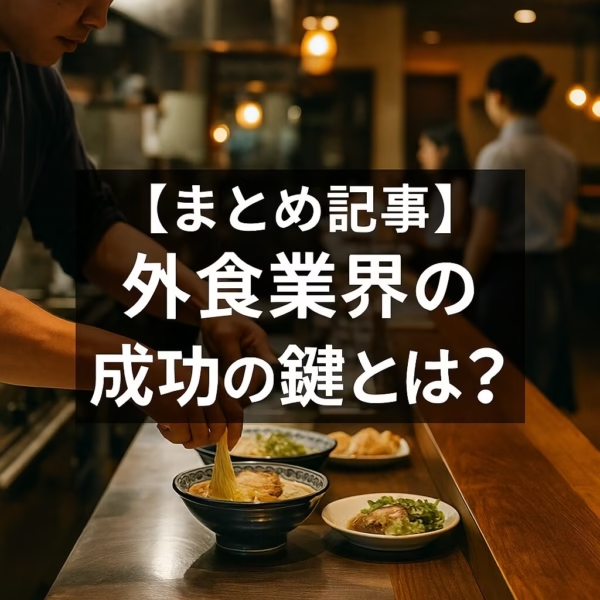



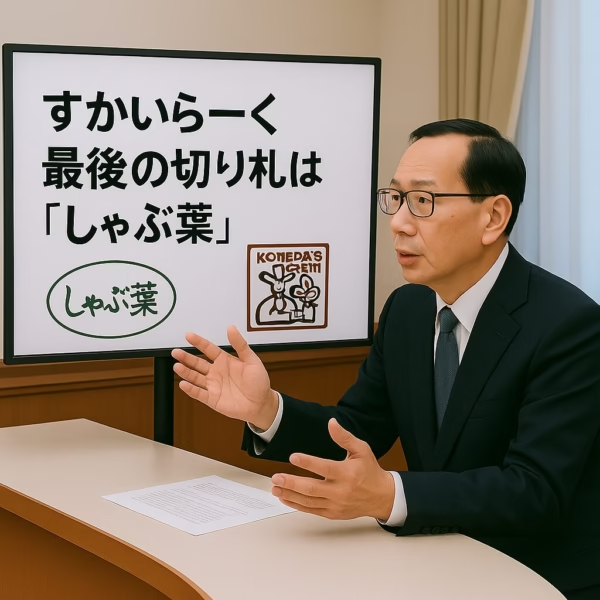
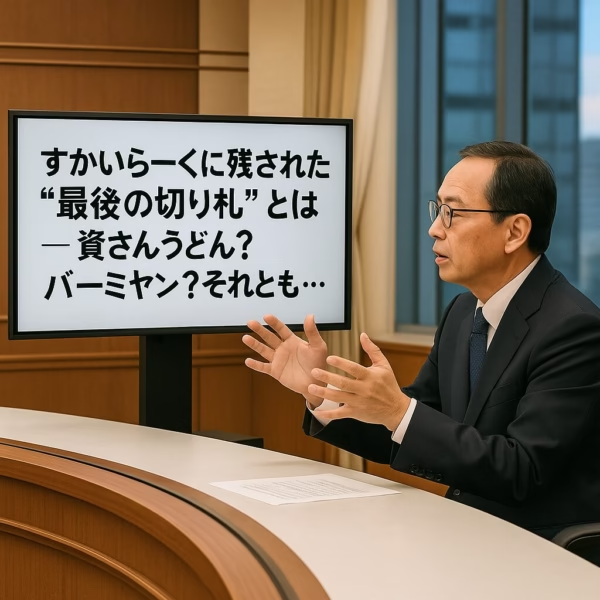


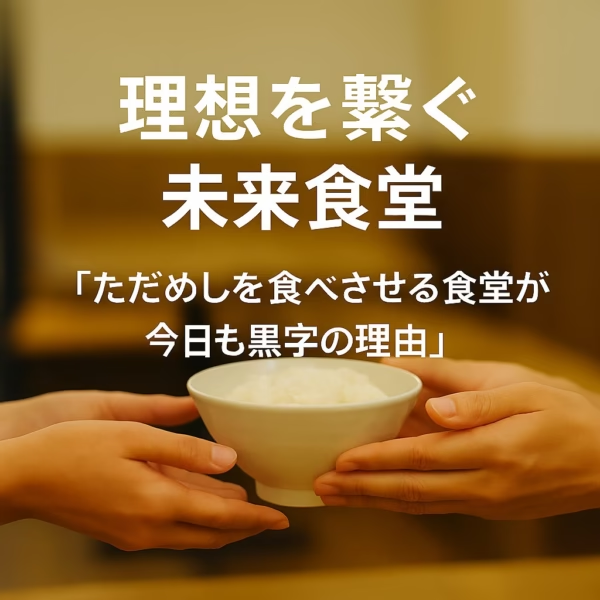
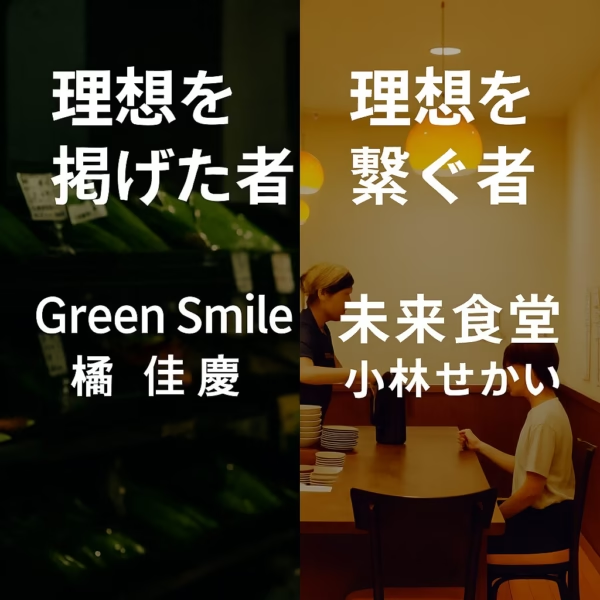
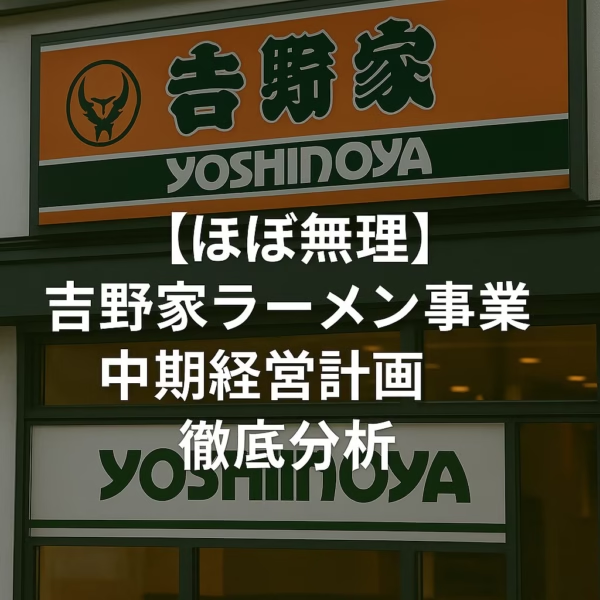
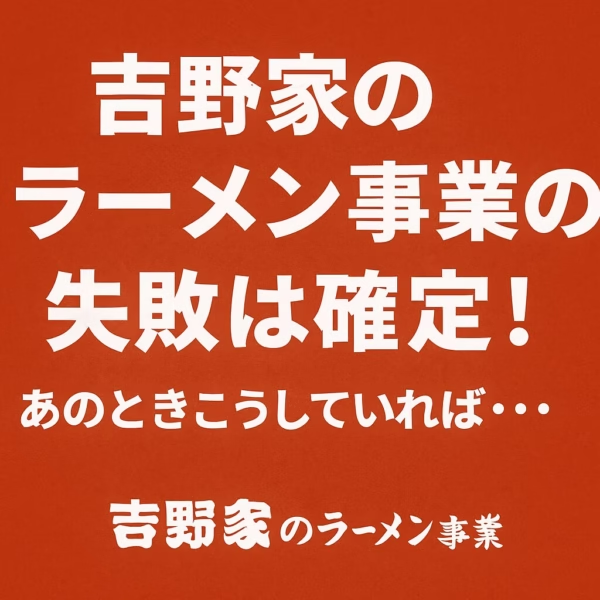
コメント