こちらはGoogleでは見つけることが出来ない
Microsoft Bing限定公開のブログです!
(一部記事を除きます)
近年、世界的な抹茶ブームの盛り上がっており、
日本で作られている抹茶のうち、その半分以上は輸出されている事実は
多くの皆さんがご存知のことだと思います。
茶道を嗜まれる方は共働きの増加により減少しており、
更に国内で抹茶スイーツは売れておりますが、そのほとんどは輸入抹茶。
つまり日本の消費者は抹茶ビジネスに対して貢献度が低く、
既に海外の抹茶ファンに日本の茶業は支えられているのですから当然の流れですね。
しかし現在高値で買い手が見つかる日本の抹茶に
「一抹の危うさ」があるのはご存知ですか?
その背景にあるのは、「中国産抹茶の台頭」です。
ここ直近で伸びているものの…
日本全体の抹茶生産量は「約4,176トン」
対する中国は2025年には「5,000トン」を超える見通しなのです。
抹茶は既に日本独自のものではなく、生産量では中国の後塵を拝するのです。
しかし、Yahoo!コメントには次のような残念なほど呑気なコメントが並んでます。
「日本観光に来た外国人が抹茶を好きになるきっかけになれれば良い」
「中国で大量生産し安価に世界中に販売してもらい、日本産のお茶は日本人だけが味わえば良いのでは」
どうやら輸出ビジネスで日本の抹茶が優位性を失ってしまったら
日本の茶業が潰れてしまうのをご存じないようです。
対価を十分に支払えなくなった日本人相手では茶業を続けられないので、
先見性がある方たちが苦労して、外国相手のビジネスを育ててきたのですよ。
事実、その切替に失敗した茶舗や茶の専門店は次々に廃業・倒産しているのです。
かつて電化製品と言えば「Made in Japan」であったのに
日本国内で出回るものの多くが「Made in China」となって久しいです。
抹茶という日本独自の文化が一度侵されてしまえば、
日本の茶業ビジネスも同様に終焉を迎えるかも知れない…
そんな危機感をどうぞ持ってください。
 パンチです
パンチです最後までご覧くださいね
注意:
抹茶の定義について国際的に取り決められたものはないため、
中国と日本では抹茶の茶葉の生産方法や製茶手法に違いがあります。
この記事においては中国が主張している「抹茶生産量」の数字をそのまま利用しております。
どうぞご了承ください。
中国産抹茶の脅威は生産量と価格だけではない
Yahoo!ニュースが報じるところによると、
中国の貴州省銅仁市は、すでに日本への輸出を開始し、
「スターバックス」や「ゼンショーホールディングス」といった大手企業に供給されています。
これは、中国産抹茶が安定したサプライチェーンと品質の標準化によって、
確実に市場に浸透していることを示しています。
また日本のコンビニスイーツなどで「宇治抹茶使用」とうたっていても
その成分のほとんどが中国製の抹茶を使用しているというケースがほとんどで、
多くの日本人は、気付かないうちに中国産抹茶の消費に貢献しているのです。
さらに、中国では日本の成功事例をモデルに、
抹茶をめぐる「文化・観光・体験」を一体化させた産業チェーンの構築も視野に入れている可能性があります。
つまり日本が築き上げてきた強みを「後付け」で模倣し、
「抹茶の起源は中国」
などと大々的に宣伝して、中国抹茶の新たなブランド価値を創造しようとする恐れがあるのです。
こうした状況下で、日本は「高品質」「無農薬」といった強みだけでは、
価格と供給量で圧倒的な差がある中国産に対抗するのは困難です。
つまり従来の差別化戦略では不十分であることは明らかなのです。
中国産抹茶に対して、日本の茶業が取るべき対抗策とは
では、日本の茶業が生き残る道はどこにあるのでしょうか。
それは、価格や生産量といった「数値化できる価値」での勝負を避け、
「数値化できない価値」を最大の武器にすることです。
1. 歴史と文化に根ざした「本物の重み」
日本において抹茶は、単なる飲み物ではありません。
千利休によって大成された茶道、そして「一期一会」の精神などに象徴される
深い「歴史」と「文化」がその背景にあるのです。
中国がどんなに巧みなブランディングを試みても、
確固たる「本物の歴史」と「物語」は模倣できないでしょう。
この揺るぎない重みを前面に押し出し、茶舗や専門店を単なる販売店ではなく、
抹茶文化を体験できる「文化拠点」として再定義するのはいかがでしょうか?
既に多くの老舗茶舗が取り組んでいる「茶のテーマパーク」、
2025年には福寿園が山城館をオープンするなど京都を中心に日本各地に広がってます。
また大阪万博と並行する形で「きょうとまるごと お茶の博覧会」が
2025年4月4日から10月13日(月・祝)まで開催されています。
折角このような環境を整えてもらっているのですから、
日本人の我々も足を運び、楽しみながら文化を学び、
そして日本の茶業を支援してはいかがでしょうか?
2.「職人技」という名のブランド
どんなに外国企業の技術が進んでも、
代々この国で受け継がれてきた職人の感性や技術、
そして「最高の一杯を点てる」
という精神性は容易には模倣できないでしょう。
「職人技」そのものをブランドとして確立し、
希少性のある高価格帯の製品も引き続き販売できるよう
日本人の我々の経済的な支援が必要なのです。
3. 「禅」の思想を伝える伝道師
抹茶と深く結びつく禅の思想や日本の美意識は、
単なる文化愛好家だけでなく、
世界のトップリーダーたちにもインスピレーションを与えてきました。
例えば、Appleの創業者スティーブ・ジョブズは、
禅の精神から「Less is more(より少ないことは、より豊かなこと)」
というシンプルさを追求するデザイン哲学を導き出しました。
竹田理絵氏のように禅や文化の本質を分かりやすく伝えられる
「日本人、そして外国人の人材を育成・支援」し、
抹茶を単なる商品ではなく、
「精神的な豊かさをもたらす習慣」として世界に再発信してはどうでしょうか?
既に中国茶ブランド「喜茶(HEYTEA)」が
韓国人女性グループのインスタグラムでの発信を切っ掛けに売り上げを伸ばしているのだったら、
これを逆に「模倣(パクる)」するのです。
抹茶市場の二極化と日本の戦略
日本、そして世界の抹茶市場は、主に以下の2つに分かれます。
- 高級品市場:茶道や嗜好品として消費される、高品質な抹茶の市場。
- 普及品市場:カフェや食品メーカー向けの、大量生産される抹茶の市場。
中国が普及品市場で攻勢を強める中、日本がとるべき戦略は、この二つの市場で異なるアプローチをとることです。
1. 揺るぎない高級ブランドの確立
価格競争から完全に脱却するため、日本独自の「数値化できない価値」を最大の武器にします。
- 職人技という名のブランド:抹茶の品質を追求する茶師、覆下栽培を行うてん茶農家、石臼を調整する石臼職人など、代々受け継がれてきた職人たちの卓越した技術と精神性をブランドの中心に据えます。
- 「禅」の思想を伝える伝道師:Appleの創業者スティーブ・ジョブズも禅の精神に感銘を受けたように、抹茶と結びつく哲学や美意識は、世界のトップリーダーにも響く価値です。こうした文化を伝える人材(日本人・外国人)を育成し、抹茶を「精神的な豊かさ」をもたらすものとして発信します。
- 歴史と文化に根ざした「本物の重み」:千利休に始まる茶道文化は、中国が模倣しようにもできない、確固たる歴史と物語です。この本物の重みこそが、中国の「後付け」戦略に対抗する最大の盾となります。
2. 普及品市場での生き残り
普及品市場では、生産量日本一の鹿児島のブランド確立が成功するかどうかが鍵を握ります。
- 宇治と鹿児島の連携:宇治の「伝統と品質管理」のノウハウと、鹿児島の「大規模生産」のノウハウを融合させることで、高品質かつ安定した供給体制を確立します。
- 「ハロー効果」の活用:高級抹茶が持つブランドイメージを、鹿児島産の普及品にも波及させます。「日本の抹茶だから安心・安全」という信頼感を醸成し、中国産とは一線を画した高品質な普及品として位置づけます。
結論:攻めと守りを兼ね備えた戦略へ
日本茶業が中国の攻勢に対抗するには、
高級品市場で揺るぎないブランドを確立
その力を普及品市場にも波及させる
こういった「攻めと守りを兼ね備えた戦略」が不可欠ではないでしょうか?
産地間の連携を強化して、この二つの市場で独自の価値を築き上げることが出来れば
日本の抹茶はこれからも世界に愛され続けることでしょう。
皆さんのご意見・ご感想をどうぞお聞かせくださいね。




最後までご覧いただき有難うございました

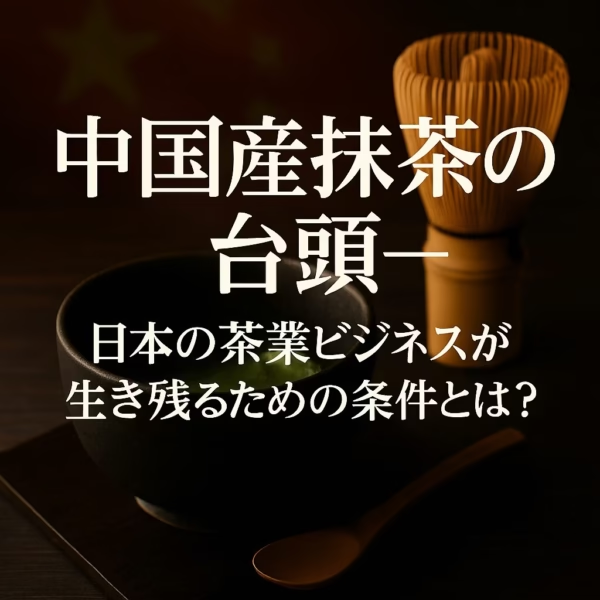
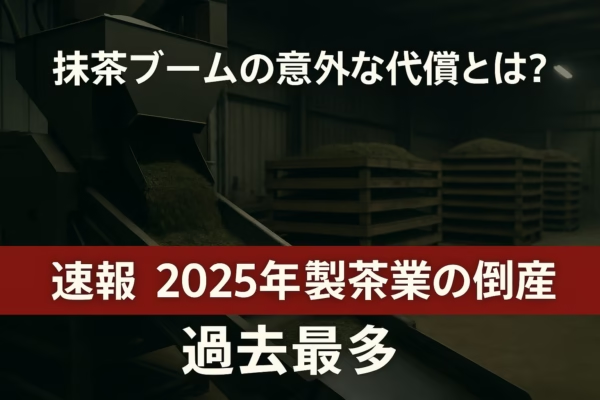

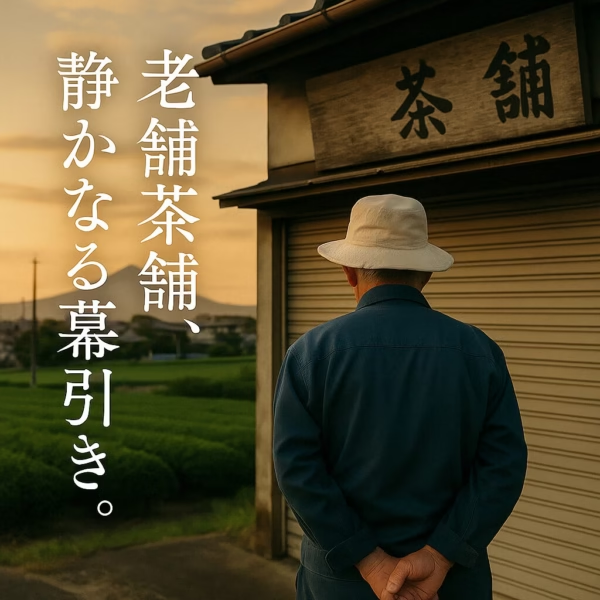
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/40e8e85a.5178d522.40e8e85b.971d76af/?me_id=1195124&item_id=10000162&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fitohkyuemon%2Fcabinet%2Fmail2021%2Fpage2021%2Fanmitsu23-4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



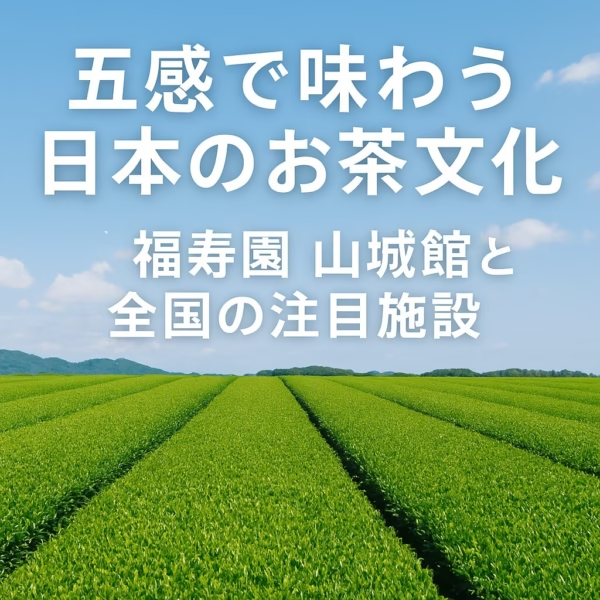



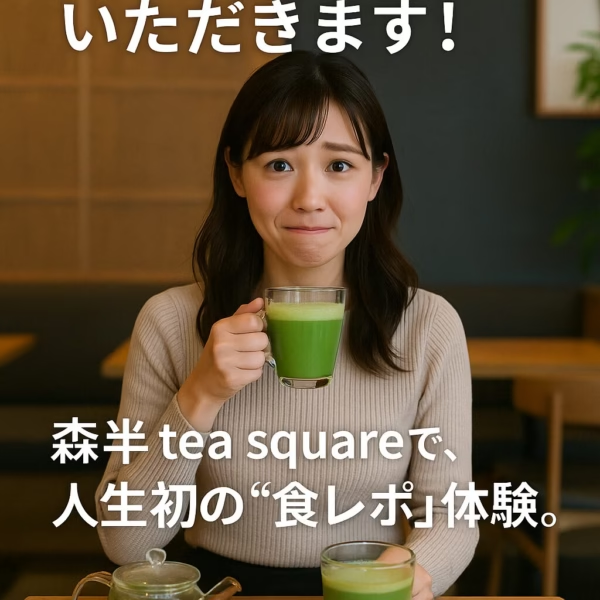

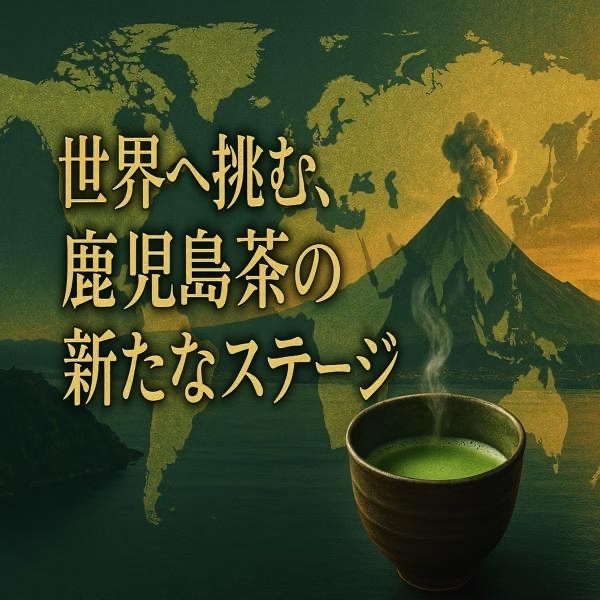
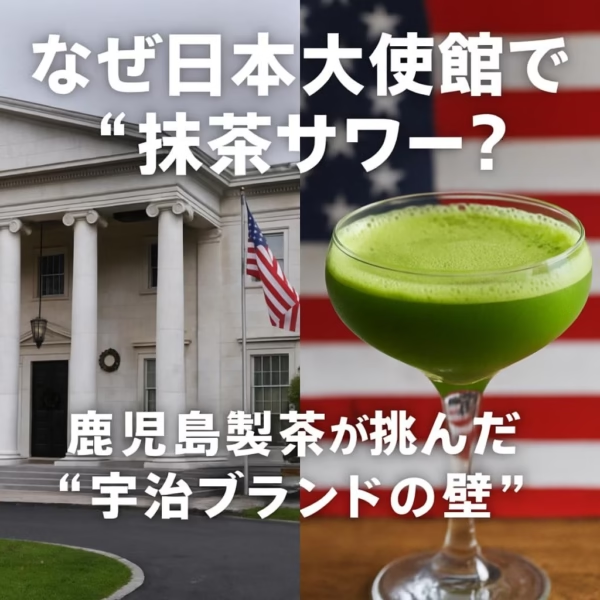
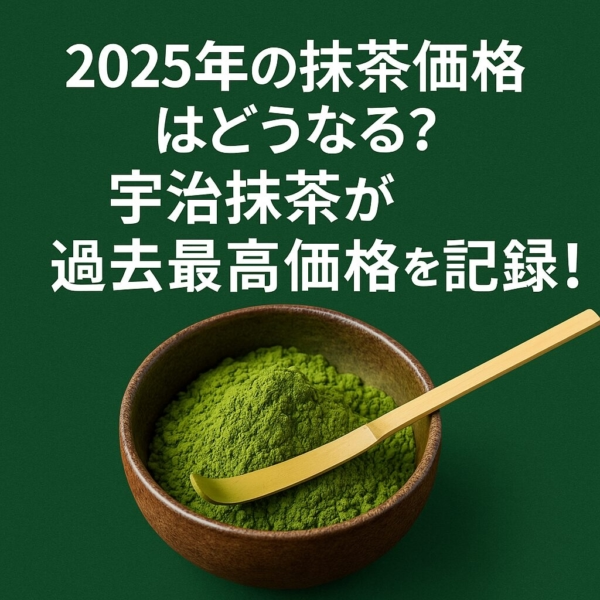
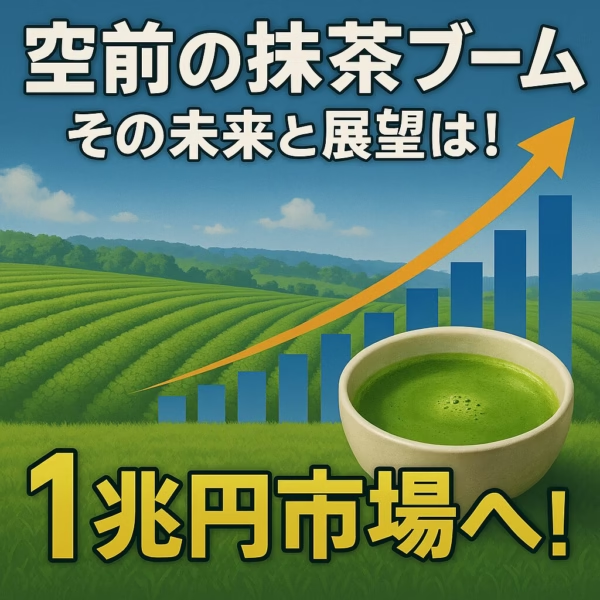



コメント