こちらはGoogleでは見つけることが出来ない
Microsoft Bing限定公開のブログです!
(一部記事を除きます)
近年、スーパーマーケットで色とりどりのパプリカを見かける機会が一段と増えました。
実は、日本におけるパプリカの消費量は年々増加しており、
その背景にはいくつかの要因があります。
- 健康志向の高まり: パプリカはビタミンCやβ-カロテンを豊富に含み、美容や健康に関心が高い人々に支持されています。
- 料理の彩り: ピーマンよりも甘みがあり、加熱しても色鮮やかさを保つパプリカは、料理の見栄えを良くするためにSNSの人気の高まりに合わせて、幅広く使われるようになりました。
- 巣ごもり需要: コロナ禍で自宅で料理をする機会が増え、手軽に使えて食卓を華やかにするパプリカの需要が特に高まりました。
現在、日本で消費されるパプリカのほとんどは海外からの輸入品です。

世界的にはオランダや、パエリアで有名なスペインが圧倒的な市場シェアを誇るのですが、
日本では韓国産が大半を占めているのをご存知でしょうか?
韓国では、1990年代半ばから日本市場をターゲットにパプリカ栽培を本格的に開始し、
生産量のほぼ100%を日本へ輸出しているため
私たちが普段スーパーで手に取るパプリカの多くが韓国産なのです。
そんなパプリカ市場に名乗りを上げたのが大和証券グループです。
証券業界とは全く異なる分野である農業、
「パプリカ生産」で覇権を目指しており注目を集めています。
農業と金融の融合を目指す新たなビジネスモデルについてお伝えします。




どうぞ最後までご覧くださいね
- ▶ 日本のパプリカ市場の現状と課題
- ▶ 大和証券グループをはじめとする大手資本の参入動向
- ▶ 農業×金融の新ビジネスモデルの可能性
「国産パプリカ」の現状について
国産パプリカの収穫時期
露地モノの国産パプリカの収穫時期は、一般的に5月から9月までです。
夏野菜であるピーマンと同様に、暑いこの時期に新鮮なパプリカを手に入れることができます。
国産パプリカの自給率
パプリカ生産には厳格な温度管理が求められるため露地栽培は非常に難しいとされており、
国産パプリカの自給率は、全体の流通量の約5〜10%程度となっています。
残りの大部分は輸入に頼っており、そのうちの約8割が韓国の野菜工場で育てられたものです。
日本国内では宮城県や茨城県、大分県などが主要な生産地として知られており、
なかでも大分県は地熱を利用した「温泉パプリカの発祥地」ということです。
皆さんはご存知でしたか?



大和証券グループの取り組み 生産拠点の整備
大和証券グループの「大和フード&アグリ」は、主に2つの拠点でパプリカを生産しています。
- 静岡県磐田市:「スマートアグリカルチャー磐田(SAC磐田)」という農園を2021年10月に買収、運営しています。
- 北海道釧路市:「北海道サラダパプリカ(HSP)」という会社に2024年4月に出資し、経営に参画しています。



生産規模と特徴
- SAC磐田では、3ヘクタールの敷地に2棟の巨大なビニールハウス(高さ6メートル)を設置して、8万本のパプリカをスマート農業技術を用いて栽培しており、年間400トン超を出荷しています。
- 通年での安定供給を目指しており、磐田と北海道の気候の異なる2拠点を活用しています。
- 両拠点を合わせた「年間生産量は1,100トン」を上回り、国産パプリカの生産量としてはトップクラスとなります。
- 農林水産省の「地域特産野菜生産状況調査」によると2022年度の国内パプリカ収穫量は7,340トンであり、同社は15.0%のシェアを誇ります。
課題と展望
- SAC磐田は当初、販売戦略と生産のミスマッチなどの課題がありましたが、現在は継続的な黒字経営を確保しています。
- 大和証券グループは、農業の「負のスパイラル」を断ち切り、新たなビジネスモデルを構築しようとしています。



パプリカ生産への挑戦の背景
大和証券グループがパプリカ生産に乗り出した主な理由は以下の通りです。
- 農業の将来性への着目:低収益が続いてきた第一次産業の農業に将来性を見出し、金融業界の知見を活かして新たな価値を創造する可能性を感じたためです。
- 投資とコンサルティング事業の新たな対象:農業を投資とコンサルティング事業の積極的な対象として位置付け、金融と農業を融合させた新しいビジネスモデルの構築を目指しています。
- 現実性の高い農業の実現:「農業×金融」の視点から、効率的で収益性の高い農業経営を目指しています。
- 農業の「負けのスパイラル」打破:農業の「負けのスパイラル」を断ち切り、新たなビジネスモデルを構築しようとしています。
- 大規模投資の可能性:野菜工場や水産工場の建設には大規模投資が必要となるため、大企業や投資家を募る可能性があります。
なお、2024年12月に大和フード&アグリ社が公表した情報によると、
静岡と北海道のパプリカ事業と、大分でのトマト事業合算で「売上 10億円」という、
上場企業の農業事業としては特筆すべき実績をあげています。



生産設備とファンドの活用
大和証券グループは、自社のパプリカ生産の成功体験を「農業ファンド」に応用することを検討しています。
ファンドは個人を含めた投資家から集めた「資金の受け皿」となり、「出資に応じたリターンを得られる仕組み」です。
このようなファンドの仕組みを農業法人に採用すれば、
野菜生産に伴う収益の一部を投資家に配分できるようになります。
コンサルティング業務の展開
大和フード&アグリの久枝和昇社長は、このパプリカ生産のプロジェクトについて
「日本で成長する市場である」と力を込めていますが、
もう一つの大きな狙いは、農作物生産や食の分野のコンサルティング業務です。
大和フード&アグリは自らがパプリカを作ることで培ったノウハウを基に、
農業への新規参入を目指す企業に助言する「コンサルティング業務」を2023年6月に開始しました。
これまでに手がけたコンサルティング業務は大企業向けが中心であり、
資金を自社で用意できる大企業に助言し、参入企業は自己資金で挑戦しています。
未来への展望
大和証券グループが農作物生産の当事者として思い描く未来は、
大規模な事業者による効率的な農業です。
収益が上がり、就農者が増えれば、
日本の大きな課題である「食料安全保障の強化」につながると期待されます。
個人投資家にとっては株式や債券などの有価証券に加え、
農業ファンドも投資対象としてより一般的に検討されるようになる日もそう遠くないかもしれません。
このように、大和証券グループはパプリカ生産という新たな分野に挑戦し、
農業と金融の融合を目指しているのです。
豊田通商、宮城県栗原市でのパプリカ生産プロジェクト
豊田通商の取り組みとは?
パプリカ生産をきっかけに農業へ参入した大手資本は大和証券が初めてではありません。
豊田通商は、トヨタグループの総合商社であり1948年に設立されました。
多岐にわたる事業展開をする中で、食品事業も展開しており、
宮城県栗原市の地元農家と共同で2008年7月に設立した
農業生産法人「ベジ・ドリーム栗原」がパプリカの生産を行っています。
この結果、宮城県は全国No.1の生産量となり、ふるさと納税の返礼品にもパプリカが採用されてます。
今後の展望
豊田通商は栗原農場(約4.2ヘクタール)と大衡農場(約1.8ヘクタール)で栽培を行っております。
年間の生産量は、約1,000トン規模とされてますから、
前述の大和フード&アグリに匹敵する規模ですね。
トレーサビリティ管理を徹底し、安心・安全・高品質なパプリカを生産しています。
この取り組みは、地元農家との協力を得ながら進められており、
パプリカの主要産地が宮城県となるためのブランド力向上に貢献しています。
豊田通商のパプリカ生産も、国内農業の未来を占う試金石とも言える取り組みであり、
地元農家との協力を深め、持続可能な農業の実現を目指しています。
\詳しくはこちらをどうぞ‼/
まとめ
大和証券グループは最新技術を駆使したスマート農業を推進し、
豊田通商は地域との協力を重視した生産体制を築いています。
それぞれのアプローチには独自の強みがあり、異なる視点からパプリカ生産に取り組んでいます。
従来、日本の農業については零細な家族経営農家が中心となった構造的な問題があり、
そこに気象変動リスクや少子高齢化が相まって、儲からない事業の代表格となっています。
もはや個人経営の小規模な農業では持続的な事業運営は困難です。
日本の農業復活には今回紹介したような
大資本の企業グループの参入と
スケールメリットによるコスト削減が不可欠であると考えられます。




最後までご覧いただきありがとうございました。




この記事がお役に立ったら、
ぜひSNSで拡散してくださいね!
-




JA産直1位になっても、私は農家を辞めました― 脱サラ就農の現実と、これから夢を追う人へ。
農業で大切なご家族の生活を支えるのは、大変な時代なのです。 -



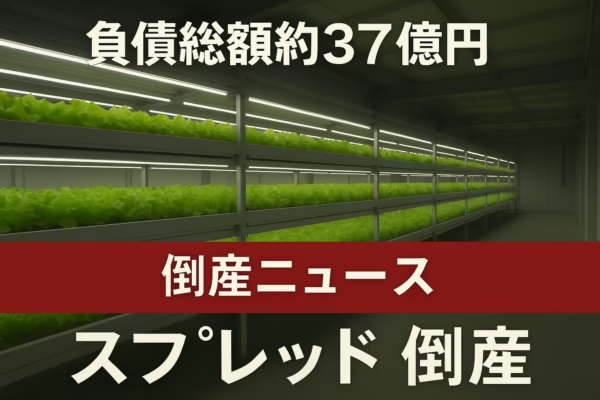
負債総額 約37億円 – 京都市 野菜工場 スプレッド倒産の裏側
✔ この記事でわかること ▶ なぜ「野菜工場のトップランナー」スプレッドが倒産したのか ▶ 農業法人の倒産が続く“業界全体の危機”と、その共通点 ▶ 「農業を仕事にしたい… -




有限会社ワールドファームの20年余りの挑戦、そして破産から得られた教訓
✔ この記事でわかること ▶ 異業種から農業参入したワールドファームの挑戦と成功の軌跡 ▶ コロナ禍と固定費増大がもたらした経営破綻の背景 ▶ 農業ビジネスにおける教訓…




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b7be727.2527d8d5.4b7be728.db1ca744/?me_id=1369271&item_id=10000726&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Ff444618-kokonoe%2Fcabinet%2F07945139%2F030-653_04.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b7be4a2.41007fd4.4b7be4a3.49f4a8ed/?me_id=1409633&item_id=10000383&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff040002-miyagi%2Fcabinet%2F1150_1401727_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
コメント