組織の中で働くということは、ときに、自分でも気づかないうちに、小さな妥協を重ねることなのかもしれません。
池井戸潤の『空飛ぶタイヤ』は、脱輪事故をきっかけに浮かび上がる企業の闇を描いた作品ですが、本当に問いかけてくるのは、「人として、どう生きるか」ということでした。
2018年に映画化された際には、ディーン・フジオカさんが、ホープ自動車の社員・沢田悠太を演じています。
彼は、まさに「組織人の葛藤」を体現する存在です。
50代になった今、若い頃には見えていなかった“心の中の葛藤”が、ひしひしと伝わってきました。
今回は、熱血主人公の零細企業社長の赤松徳郎ではなく、あえて一癖ある大企業のエリート社員 沢田悠太に焦点をあてて、組織人として「最後に何を選ぶか」について、私自身の思いも交えながらご紹介していきたいと思います。
※あくまでこれは私個人の視点によるレビューです。
小説や映画には、この行間にこそ伝わることが詰まっています。
ぜひ、ご自身の目で確かめてみてください。
本書「空飛ぶタイヤ」の紹介(あらすじ・背景)
神奈川県内で、走行中の大型トラックからタイヤが外れ、歩道を歩いていた母子を直撃するという痛ましい事故が起こります。
母親は命を落とし、小学生の息子は軽傷。
事故を起こしたのは、零細企業である「赤松運送」のトラックでした。
警察やマスコミは、整備不良による事故として赤松運送を糾弾。
世間からのバッシングが集中し、会社は存亡の危機に追い込まれます。
しかし事故の背景には、トラックメーカーである大手企業「ホープ自動車」の重大な欠陥隠し(リコール隠し)という、企業体質の問題が潜んでいました。
運送会社の経営者である赤松徳郎(映画では元TOKIOの長瀬智也さんが演じてます)が、会社と社員、そして家族を守るために熱く真実を追いかける一方で、大企業であるホープ自動車のエリート社員・沢田悠太は、組織の中でこの問題に向き合いながら、「会社人」としての立場と「人間としての正義」の間で深く揺れ動いていきます。
『空飛ぶタイヤ』は、単なる企業犯罪小説ではありません。
それぞれの立場で生きる人々の内面に踏み込み、組織に属するすべての人間に共通する問いを投げかける物語です。
「守るべきは、組織か、それとも自分の良心か?」
沢田悠太という存在に見る、組織人の葛藤
ホープ自動車の社員・沢田悠太(ディーン・フジオカさん)は“平均的なエリート会社員”です。
上を見て下に合わせ、組織の空気を読みながら、そのなかで「それなりに仕事をしてきた」と思っている男です。
そんな沢田が、脱輪事故をきっかけに社内のリコール隠しに触れ、ある決断を下します──社長への内部告発です。
ただし、その動機は決して純粋ではありませんでした。被害者への同情や社会正義ではなく、対立部署である品質保証部への私怨、長年くすぶってきた不満、そして、どこかで「自分が正しい」と思いたいという浅くて都合の良い正義感が、その行動の原動力だったように見えます。
会社は沢田に、長年の夢だった開発部門への異動を提示しました。
沢田は、事実の黙殺と引き換えに、その「取引」に応じます。
こうして、彼は希望していた部署へと移ることになります。
だが、新しい職場で待っていたのは、
自由も創造性も許されない、閉ざされた空気です。
やがて沢田は悟ります──
これは口を封じるための“飼い殺し”だったのだと。
失望の中で、沢田は再び動きます。
今度は社外──警察への正式な告発です…
確かに、最終的に彼の行動は、企業の不正を明るみに出し、社会にとっては意味のあるものだったかもしれません。
しかし私は、その行動を誇るべき“勇気”とは、どうしても思えません。
彼は、自ら選んだ妥協と打算の道が閉ざされたからこそ、結果として“正しい行動”をとっただけではないでしょうか。
「自分のための正義」
「逃げ場を失った末の決断」
それを“立派だった”とは、とても言い難い。
沢田に自分を重ねることはありません。
むしろ、「ああはなりたくない」という反面教師として、主人公の赤松徳郎(長瀬智也さん)とは一味違う、極めて人間臭い沢田の姿は、今でも私の中に強く焼きついています。
50代の今、なぜこの物語が響いたのか
若い頃であれば、この小説は「企業の不正を暴くサスペンス」として楽しんで終わっていたかもしれません。
善と悪がはっきりしていて、正義が勝つ──そんな物語は世の中にいくらでもあります。
でも、50代になった今、私の目に映ったのは「正義の物語」ではなく、もっと複雑で、もっと現実的な「会社人の物語」でした。
とくに、大企業ホープ自動車のエリート社員・沢田悠太。
社内での立場を守りたい、相手部署を陥れたい、自分が正しかったことにしたい──
そんな打算や私情を背負いながら動き始めた彼の行動は、正義というには遠すぎるものでした。
けれど、最後に彼が取った行動には、確かに意味があった。
途中までは軽蔑していた彼のことを、「まあ、あいつでもこういうことはやるんだな」と見直したのも事実です。
この作品は、清濁あわせ持った人間が、それでも「最後に何を選ぶか」を描いています。
そしてその選択が、しっかりと物語にケリをつけてくれたことで、
読み終えたあとに、どこか爽やかな風が吹いたような読後感がありました。
面白かった。
誇張ではなく、心からそう思える一冊でした。
結び|読者への問いかけ
沢田悠太は、全く立派な人物ではありません。
むしろその逆で、彼はとてもズル賢く、打算的で、「何かのついでに正しいことをした人間」だったと言えるかもしれません。
けれど、現実の組織人、エリート社員とは、案外そんなものではないでしょうか。
最初から清廉で、まっすぐで、迷いがない人間など、現場にはそうそういません。
大事なのは、「葛藤の末、最後にどちらを選ぶか」ということだと思います。
途中で間違えても、それでも、自分にだけは嘘をつかない選択をすること──
それが、信頼というものの根っこにあるのではないかと、この物語を読んで思いました。
是非、沢田悠太の心の動き、「葛藤」に着目して小説版、映画版をお楽しみください。




最後までご覧頂き有難うございました
池井戸潤さんの本の中でも、リアリティ度 No.1の本作。
最高に面白かったですよ!




私たちの読書レビュー、
次回もお楽しみに!
👉https://www.makoto-lifecare.com/
“In the end, what defines us is not how we start, but what we choose when it matters most.”
最後に人を定義するのは、どんなふうに始めたかではなく、一番大事なときに何を選んだかに尽きる。
📱この記事をスマホでも読みたい方へ
お使いのスマートフォンで以下のQRコードを読み取って、通勤中や週末にも気軽にアクセスできます。
PCで読んで「これは保存しておきたい!」と思った方は、ぜひご活用ください。


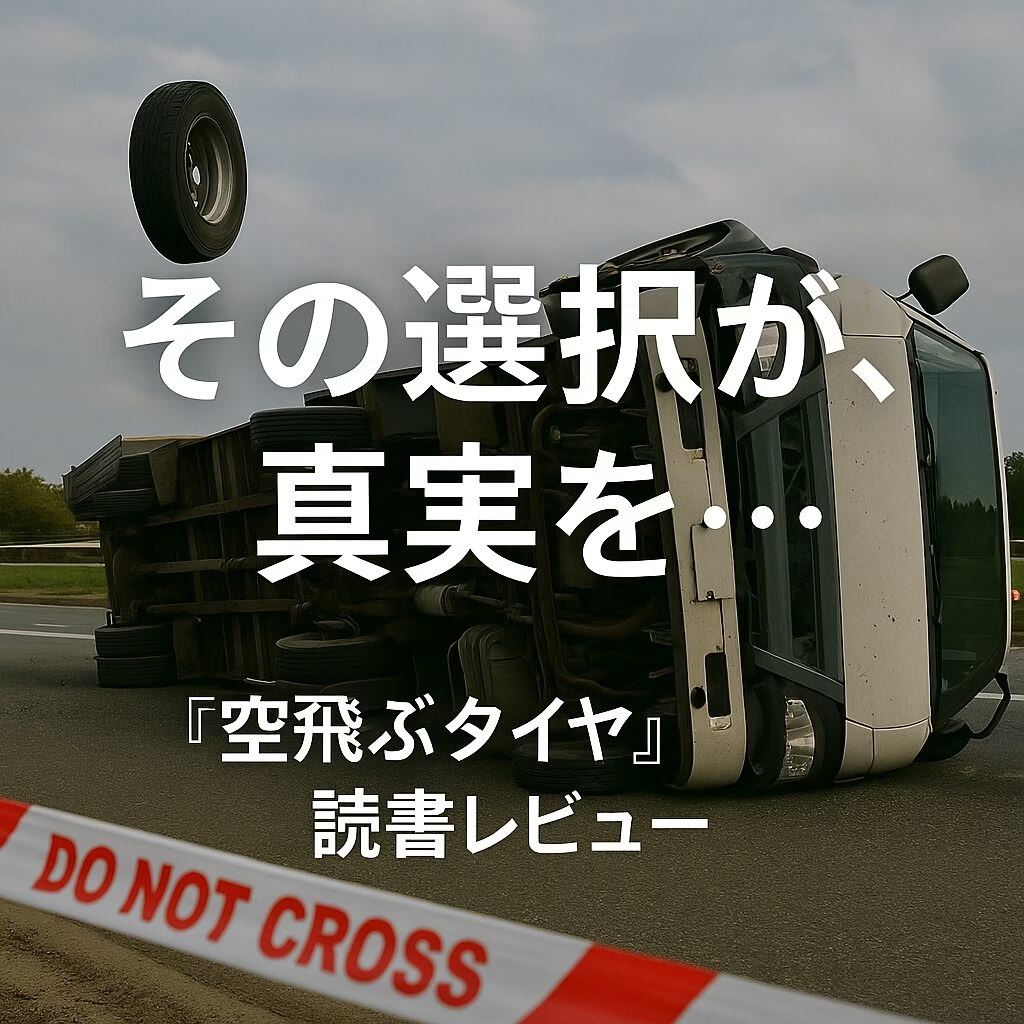
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3d8f481b.684b1bea.3d8f481c.2b2282bf/?me_id=1213310&item_id=13273838&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4520%2F9784062764520_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3d8f481b.684b1bea.3d8f481c.2b2282bf/?me_id=1213310&item_id=13273839&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4537%2F9784062764537_1_11.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
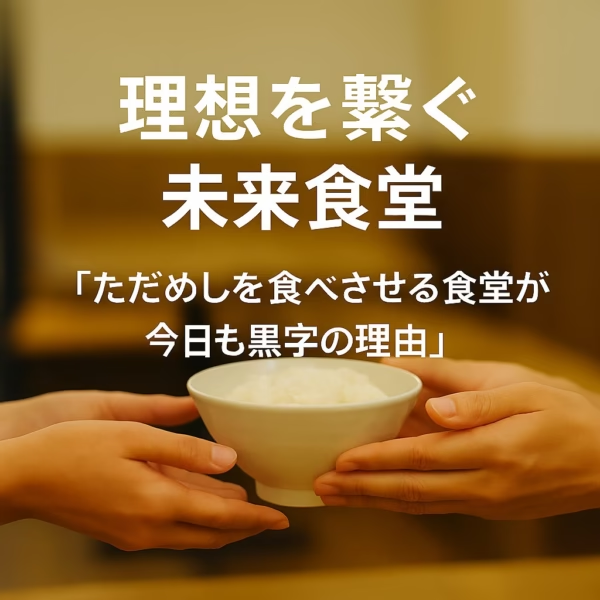

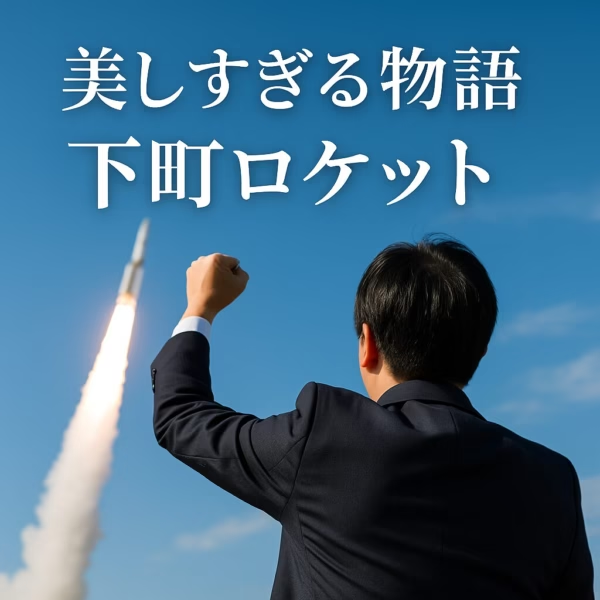
コメント