中小企業が逆境を乗り越え、大企業に挑み、仲間とともに夢を掴み取る──
そんな池井戸潤が綴る「熱血ストーリー」に心を打たれた読者も多いことでしょう。
けれど私には、どうしても乗り切れない違和感が残りました。
50代を迎え、組織の内側も外側も知る立場になった今、この物語に描かれた世界は、私にはあまりにも“美しすぎる”ように思えたのです。
現実の経営、現実の組織、現実の人間関係──
それらを知っているからこそ感じた「ズレ」と、それでも最後まで読み通したことで見えた「この作品なりの意義」。
今回は、熱狂的な賛辞があふれる中、あえて一歩引いた視点から『下町ロケット』を見つめ直してみたいと思います。
※あくまでこれは私個人の視点によるレビューです。
小説や映画には、この行間にこそ伝わることが詰まっていると思います。
ぜひ、ご自身の目で確かめてみてください。
社員は、夢だけでは動かない―最初に覚えた違和感
『下町ロケット』を読み進める中で、私が最初に強く感じたのは、組織に漂う現実感の薄さでした。
もちろん、技術者たちが誇りを持って働く姿は眩しく映りました。
夢に向かって一丸となる姿に、心を動かされる読者が多いこともよく分かります。
けれども、現実の会社経営はそれほど単純ではありません。
佃製作所も、かつて研究開発への先行投資が裏目に出たことで、資金繰りが悪化し、社員にボーナスカットを強いた過去がありました。
さらに、物語の冒頭では、最大手顧客である京浜マシナリーとの年間10億円規模の契約も失っています。
現場では今期赤字が確定し、経費削減や売上捻出に追われる状況にあります。
この物語の舞台であるリーマンショック後の2010年代中頃は、当時の中小企業における若手社員の月給は、平均25万円前後でした。
しかも、就職氷河期をくぐり抜けて入社してきた若手社員も少なくなく、「東京でも一流の大学を出たのに、拾ってくれたのはここだけだった」という佃製作所の社員の言葉に象徴されるように、自信を失い厳しい現実に打ちのめされている若者が生々しく生きていた時代なのです。
今のように若い世代の転職も楽ではなく、一度入社してしまったら所属してしまった組織の中で生きていかなければならない中で、夢を語る社長についていける社員ばかりだったとは考えにくいものです。
実際、作中では、営業部の若手エースである江原春樹が社長の理想主義に危機感を抱き、直訴する場面が描かれます。
また、経理部係長の迫田滋は、飲み会の席で佃社長に詰め寄り、「特許使用料を結んでボーナスを弾んでください」と直言します。
一時的に社内の空気は冷え込み、士気は低下しますが、それでも物語は、大きな転機を経ることなく、社員が一丸となって夢に向かって邁進する美しい姿へと収束していきます。
現実の中小企業では、社長に異を唱えることは容易ではありません。
社員用の軽自動車が並ぶ駐車場に、ただ一台だけ社長の高級外車が止まっている──
そんな構図がむしろ当たり前であり、生活不安を抱えた社員が夢だけを信じて進めるほど甘い世界ではないのです。
現実の経営、現実の組織、現実の人間関係。
それらを見てきた私には、この物語に描かれた世界があまりにも美しすぎるように思えました。
「56億円の和解金」が意味するもの──リアリティなき訴訟劇
物語の中盤、佃製作所は大企業ナカシマ工業に対し、一転して特許侵害を理由に70億円の損害賠償請求を行います。結果として、ナカシマ工業は56億円という巨額の和解金を佃製作所に支払うことになります。中小企業が大企業に打ち勝つ、痛快な逆転劇です。
しかし、私はこの展開に“現実”の視点からどうしても違和感を拭えませんでした。
そもそも訴訟を起こしたのはナカシマ工業です。財務的に脆弱な佃製作所に対し、裁判が長期化すれば音を上げて和解を申し出てくるだろうという読みのもと、大手法律事務所を従えた、いわば“企業の論理”に基づく法廷戦略を取ったのです。
ところが、そのナカシマ工業が逆に特許侵害で訴え返され、自らの訴訟よりも先に和解に追い込まれ、結果的に巨額の和解金を支払う側へと回る──この展開は、あまりに都合が良すぎるのではないでしょうか。まるで大手法律事務所を軽んじているようにすら思います。更にこの物語では佃の元妻の紹介で、「神谷修一」というナカシマ工業や大手法律事務所に作者と同様に反を唱える「独立系スーパーマン弁護士」が登場しますが、通常20億円もの損害賠償請求を受けて相手側が大手法律事務所に依頼しているのであれば佃製作所も同規模の法律事務所に頼るのが筋だろうになぁと思います。
企業訴訟は感情論ではありません。特許の立証、侵害の有無、被告と原告の立場の明確化──こうしたステップを飛ばし、“勧められたから和解に応じた”という描写だけで56億円のやり取りが決まるのであれば、それはもはや法廷ではなく、ご都合主義の茶番劇です。
加えて、和解金56億円は決して「自由に使える資金」ではありません。仮に法人税率を30%とすれば、約17億円は納税に充てられます。弁護士費用(着手金・報酬金)も数億円は発生するでしょう。
実際に会社に残るキャッシュは、多く見積もっても30億円台前半です。しかも、佃製作所はこの時点でまだ営業赤字の状態です。開発費・固定費・損失補填といった出費を考慮すれば、決して“余裕のある状態”とは言えません。
ところが、物語はこのあと、さらなる“美談”へと進みます。
和解金が入金されると分かった途端、ナカシマ工業からの提訴を理由に佃製作所を冷遇していたメインバンク・白水銀行が、手のひらを返してすり寄ってくる──そして、佃と経理部長の殿村は「取引終了」を宣告し、借入金20億円の全額返済を即断します。
読者にとっては爽快な展開かもしれません。けれど、現実の中小企業経営者ならこう考えるはずです。
「まずやるべきは、次の融資先の確保では?」
もちろん、“物語に描かれていないだけで、裏ではちゃんとやっているはず!”という擁護もあるでしょう。しかし、それを描かずに「銀行に言い放って、スパッと返済」するだけでは、あまりにも現実離れしています。
むしろ、和解金受け取りが決定したことで、佃製作所の元を訪ねてくるであろう他行の営業担当たち──その“現実的な光景”の描写が一切ないことに、私は逆に違和感を覚えました。
白水銀行との決別シーンに、読者の多くはカタルシスを感じたかもしれません。けれど、現実を知る目で見た私は、爽快感ではなく、疑問と不安を抱いていたのです。
本来の殿村の役割とは何だったのか──銀行から来た経理責任者の“機能不全”
経理部長・殿村直弘は、佃製作所の財務を預かる責任者であり、元銀行員という経歴を持つ人物です。
中小企業において、こうした「銀行出身の経理責任者」が果たすべき役割は、ただの帳簿管理ではありません。
会社の夢や勢いに引っ張られすぎず、リスクを見極めて社長にブレーキをかける“最後の防波堤”になることこそが、最も重要な職務です。
しかし、殿村は物語の中で、そのブレーキとしての役割を果たすことなく、“佃社長の忠臣”として描かれていきます。
それが最も明らかになるのが、ナカシマ工業との訴訟の渦中で、帝国重工が20億円でバルブの特許買取を提案してくる場面です。
社長の佃は断固拒否する方針であるのに対して、営業の唐木田は、「資金繰りが崩れる」「和解金の行方も分からない」と佃の考えに反対し、また技術畑の山崎は、開発の誇りと会社の現実の間で揺れ動きます。
そして肝心の殿村はと言えば、「資金繰りの件なら心配無用です」と繰り返すばかりで、明確な財務見通しを何一つ示すことなく、社長の佃を盲目的に支持します。
本来であれば、銀行出身者として「裁判が長引けばこうなる」「訴訟敗北時の資金計画はこうだ」といった、具体的な数字・条件・代替プランを社内に提示するべき場面です。
ところが彼は、感情論と忠誠心だけで「大丈夫ですから」と押し通してしまいます。
夢に賭けたい佃社長の思いを支えたい──その気持ちは分かりますし、銀行からの出向者である「外様」の殿村が佃製作所の一員となる名シーンとして描きたかったのでしょうか。
しかし、経理責任者がその役割まで手放してしまえば、存在する価値がなくなるだけなのです。
私は殿村という人物を、「佃を支える温かい存在」としてだけでなく、「企業の理性」としても期待していました。
だからこそ、この場面での曖昧な説得力のなさに、強い違和感を抱かざるを得ませんでした。
あのM&Aコンサルタントはあり得ない──マトリックスの須田が壊した“現実感”
物語の終盤、投資コンサルティング会社「マトリックス・パートナーズ」の須田という人物が登場します。
自らの名刺を差し出し、「貴社に関心のある企業がある」と切り出すその姿に、観る者は一瞬、悪徳M&Aブローカーの登場かと思わされます。
けれども実際の須田は、礼儀正しく、腰の低い振る舞いを崩しません。
むしろ、新入社員のように従順で物腰柔らかな対応で佃に接し、強引さも不躾さも一切感じられません。
その意味で、物語中盤までに描かれた「大企業や銀行に対する不信感」を須田に重ねるのは、筋が通らないように思えます。
私が須田に対して、違和感を抱いたのは、面会の場所です。
社長の自宅に電話をかけてアポを取り、面会に選んだのが会社の応接室であるという点です。普通はホテルの会議室とか、料亭の個室とか、人目につかず決して従業員にはバレないような場所を選びませんか?
しかも須田の佃製作所、訪問当日の服装はハイブランドの高級スーツに、派手なネクタイ、そして応対してくれた事務スタッフに、わざわざ本名と社名まで名乗っていたので、経理責任者の殿村に即バレしていることが描写されています。
会社の将来に関わるかも知れない重大な話を、社内に不穏な空気が漂う中で、社長がこっそり単独で外部の投資会社と面会する──この構図が、従業員に与える心理的影響を考慮すれば、投資コンサル側も佃側も「情報管理としても、経営判断としても、リスクが大きすぎる」としか言いようがありません。
なぜならこの時、佃製作所の社内ではすでに──
- 京浜マシナリーという最大の得意先を失い、
- 帝国重工向けのバルブ生産を巡って経営判断が割れ、
- 若手社員からの不満が噴き出し、
- 今期の業績見通しは営業赤字転落が確実で、
- 社員の多くが「ボーナスすら危ういのでは」と不安を抱えている状況
にありました。
そんな中で、「社長が投資会社の人間と会っていたらしい」という噂が立つだけで余計なうわさ話や疑念が広がってもおかしくはありません。社内の信頼関係が崩れる火種になる場面を、あまりにも無警戒に描きすぎているのですが、殿村は「マトリックスと何の話を?」と疑問を持ちつつも、佃の「つまらない話さ」という回答に、ここでも忠臣だからなのか、「そうなんですか、ならいいんですが」軽くスルーしてますから驚きです。
もっともがっかりさせられたのは、この一件をきっかけに佃が「会社を売ること」に心を揺らがせる展開です。
これまで頑なに「バルブの特許だけは絶対に譲らない」と言い切っていた佃が、若手社員の不満を目の当たりにした直後のこの買収話に、「いっそ会社ごと売却してもいいのでは」と逡巡する姿には、経営者の孤独や悲哀などを感じることは一切なく、一貫性のなさ、そして43歳の中小企業経営者としての未熟さを感じざるを得ませんでした。
なぜ私は『下町ロケット』に熱くなれなかったのか── “リアル”から遠ざかる物語
多くの読者が『下町ロケット』に心を打たれたと語ります。
「胸が熱くなった」「涙が出た」「ラストにガッツポーズした」。
その声に、私はどこか置いてけぼりにされたような気分になりました。
読み終えて強く感じたのは、物語の中で描かれる人物たちの言動が、次第に“現実”から乖離していったということです。
私は、予定調和が嫌いなわけではありません。
むしろ、現実には得がたい報われ方が物語の中で叶えられることに、希望を見出す読者がいるのも理解できます。
けれど、そこに至るまでのプロセス──登場人物たちの判断、葛藤、行動──それらにリアリティの欠如が積み重なっていくことで、理解が難しいと感じる私がいました。
経営判断における軽さ、感情優先のブレた意思決定、そして周囲の人物たちの従順すぎる動き。
それらが続くうちに、私はこの物語を、現実と地続きの世界として信じられなくなったのです。
もしかすると、限られたページ数の中で、リアルを追求しすぎれば物語が重くなりすぎる。
そうした制約もあったのかもしれません。
結果として、物語がクライマックスに向かって熱を帯びていく中でも、私は少しずつ、テンションが下がっていくのを止められませんでした。
 パンチです
パンチです最後までご覧頂き有難うございました
共感して頂ける方がいらっしゃったら
すごくすごく嬉しいです!




また私たちの読書レビューを見に来てくださいね
👉https://www.makoto-lifecare.com/
📱この記事をスマホでも読みたい方へ
お使いのスマートフォンで以下のQRコードを読み取って、通勤中や週末にも気軽にアクセスできます。
PCで読んで「これは保存しておきたい!」と思った方は、ぜひご活用ください。


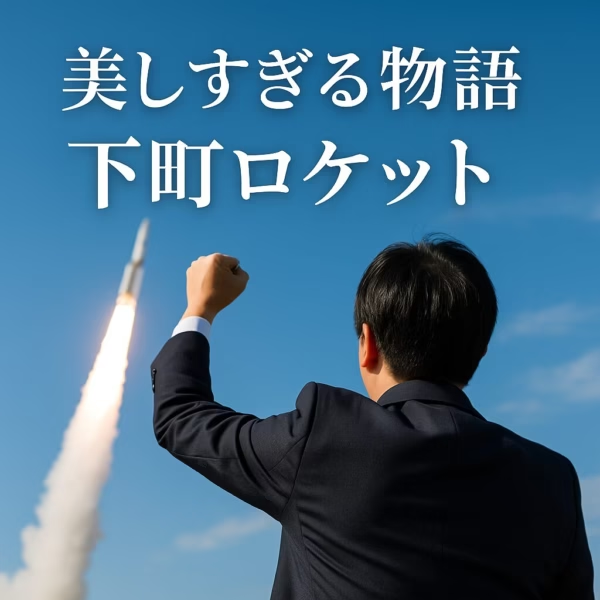
コメント