「世界最大規模、1日10トンのレタスを生産できる工場」
世界中の空腹に苦しむ人々を食糧危機から救うかも知れない
そんな期待を背負っていた野菜工場のトップランナー『スプレッド』は
2024年8月26日に民事再生法の適用を申請、
1年近くを経て2025年4月にその手続きが完了しました。
実は私、この会社から「営業責任者」としてのポジションを提案されたのですが、
最終面接を前に辞退する決断を下しました。
その理由は、企業側から理念や事業計画を聞く中で
「野菜工場のビジネスモデルに未来はない」という確信を得たからです。
- ▶ 「スプレッド」の破綻に至るまでのビジネスモデルの限界と経営課題
- ▶ 野菜工場ビジネスにおける、農業経験者から見た“現実的な問題点”
- ▶ 事業承継後の植物工場ビジネスの行方と、今後の課題
 パンチです
パンチですどうぞ最後までご覧くださいね
スプレッドの企業紹介
スプレッドという会社については、転職エージェントから、
「世界最大規模」というキーワードを何度も聞かされました。
「1日10トンものレタスを生産できる」という話には、
まるで世界の食糧危機を救えるような夢があります。
聞く人によっては革新的な農業技術を持っている会社なのかな?と興味を引かれるかも知れません。
果たして現実はどうだったのでしょう?
この会社は、京都府の亀岡プラントや木津川市にある最新鋭設備を備えた
「テクノファームけいはんな」で一時は注目を集めていました。
私がスカウトを受けたのは、この会社がまだ「アースサイド」と呼ばれていた頃で、
営業責任者として年収800万円という条件でのお話だったと記憶しております。
製薬会社でMRとして培った実績、さらに農業ビジネスにおける経験と知識が評価されたようでした。
この会社のビジョンとして挙げられていたのが植物工場ノウハウの海外への販売です。
アメリカ東海岸や中東への技術進出が具体的なプランとして示されていました。
西海岸は既にレタスの主要産地として知られていますが、東海岸には競合が少ないらしく、
「ここならば市場を開拓できる」という狙いがあったのでしょう。
また、日本国内では生産を目的とするプラントというよりも、
大学などの研究施設に売り込む可能性があるという説明を受けました。
ただ、この話を聞けば聞くほどに
「壮大なプランがあるのは分かるけど、それを実現するための現実的な道筋が見えてこない」
そんな印象が強まってきました。
私が最終面接を辞退した理由
正直なところ、最初スカウトメールが届いたときから
「野菜工場ビジネスでの黒字化は難しい」と考えていました。
それは私が自営農家時代にレタスの契約栽培を専門にされている経営者さんから、
レタスは露地栽培でも無農薬栽培が一般的であることを聞いていたために、
わざわざ工場で作るメリットがない、と知っていたからです。
スカウトに応えたのは、自分自身の市場価値を確認するという目的、そのためだけでした。
当時、まだコロナ禍がくすぶっており、会社との接触はオンライン面接で行われ、
PCの画面に映った面接官は2名、どちらも入社してまだ1年未満とのことでした。
つまり、お二方の前任者は早々に退職されていたのです。
それを聞いた時点で、想像以上に会社の状況は良くないぞ、と感じとったのですが、
会社側からはアースサイド社の良い点ばかりを語られ、「違和感」しか感じませんでした。
「何かご質問・ご感想は?」と最後に聞かれたとき、私は少し皮肉を込めて
「本当に良い会社ですね」と笑顔で一言だけ返しました。
その瞬間、面接官のお二方が顔を見合わせて「すみません、そんなことないです」と回答されました。
このやり取りを通して、自分の直感が正しかったと確信し、スカウトを辞退する決意を固めました。
その後、最終面接の合格通知が届き、転職エージェントは一生懸命に説得してきました。
しかし、私の判断は覆るはずもありません。
「野菜工場ビジネスの未来はない」と確信したからです。
後日、別の大手転職エージェントからも、
再度「スプレッド」への応募を薦めるスカウトメールを受けましたが当然お断りしました。
好待遇にもかかわらず採用活動が長引いていたのは、私と同様に「違和感」を感じた方が多かったせいだと思います。
今思えば、アースサイドの社長に一度会って
「この会社が社員やその家族の人生を支えられると真剣にお考えですか?」
と正面から尋ねてみたかったですね。
スプレッドの工場概要
スプレッドは、いくつかの大規模な植物工場を運営してきました。
まず2007年に京都府亀岡市に「亀岡プラント」を設立。
当時、世界最大規模の日産21,000株のレタスを生産する植物工場として注目されました。
この施設では試行錯誤を繰り返し、6年間かけて独自の栽培・生産管理技術を確立しました。
そして2013年に、難しいとされていた黒字化を達成したと公表されておりますが、
当時1玉200円で販売されたレタスで
機械設備・光熱費・人件費・水道代・肥料代を本当にカバーできていたのか、甚だ疑問です。
なお、このプラントは現在は閉鎖されています。
その後、より持続可能で効率的な次世代型農業生産システム「Techno Farm」を開発。
2018年に京都府木津川市のけいはんな学研都市にて「テクノファームけいはんな」が稼働開始。
この工場では、生産性向上と環境負荷の軽減を両立した運営を実現し、現在も稼働しています。
さらに、静岡県袋井市には「テクノファーム袋井」が設立され、2024年1月から生産を開始。
この工場は中部電力株式会社と株式会社日本エスコンの協力で設立されましたが、
同年3月4日に火災が発生し、生産が停止。
その後、経営は厳しい状況に陥り、2024年8月に民事再生法の適用を申請しました。
私が最終面接を辞退してから1年後のことでした。
スプレッドの破綻までの流れ
スプレッドが破綻に至るまでには、いくつかの重要な要因が重なりました。
まず、同社は「世界最大規模のレタス工場」を掲げ、設備投資に莫大な資金を投じました。
この過剰投資が後に財務的な重荷となり、経営を圧迫する結果となりました。
さらに、資金繰りの面でも課題がありました。
融資への依存度が高く、利益率の低下が経営全体に深刻な影響を及ぼしていました。
加えて、需要見込みを誤った点も大きな要因です。
国内のレタス事業が宣伝やショールーム的な位置づけに留まり、
安定的な収益を生むことができませんでした。
同社の最先端工場で生産されたレタスには、露地野菜と差別化できる点は見当たらず、
既存産地との価格競争に巻き込まれ、赤字が続いていて当然の状況でした。
中東を含む海外展開への期待もありましたが、結局、実現には至らなかったようです。
これらの要因が積み重なった結果、
2024年3月に静岡県袋井市の工場火災が決定打となり、
同年8月26日に民事再生法の適用を申請するに至りました。
スプレッド社は多額の初期投資による綱渡りの経営の末、
一度の工場火災で破綻しました。
最終面接辞退の決断に確信を持てた理由
私が最終面接を辞退を決断したのは、面接の過程で感じた違和感を感じたからです。
最初に野菜工場の話を聞いた時から、コスト構造が全く違う露地栽培との競争力が課題だと思ってました。
しかし、その後、当時の稲田社長が
「既存のレタス産地はライバルではない」
とコメントされていることに気づきました。
私とは考えが全く違うので、仮に最終面接へ進んでいたとしても、内定は頂けなかったでしょう。
👉「儲かる植物工場」に世界が注目 | 一歩先への道しるべ ビズボヤージュ
まとめ 引き継がれるスプレッドの遺志
京都府木津川市の「テクノファームけいはんな」を承継した株式会社Green Factory TFKと、
静岡県袋井市の「テクノファーム袋井」を承継した中部電力関連の株式会社TCF。
それぞれが異なる戦略で工場運営を継続する中、
既存のレタス生産地、特に露地栽培との競合をどのように乗り越えていくのかが注目されます。
TFKは、東急不動産が持つ経営資源やノウハウ、そして再生可能エネルギーの活用を掲げ、
収益性向上と脱炭素化に挑戦しています。
一方、TCFは中部電力グループのサポートを受けながら、
生産体制の安定化を図るとともに、競争力ある価格と品質の実現を目指しています。
これらの取り組みの中で、いかに継続的な事業基盤を築き、従業員を守り、
そして地域社会や市場と調和していけるかが鍵となるでしょう。
この厳しい市場環境の中で、両社の挑戦がどのような形で実を結ぶのでしょうか?
引き続き目が離せませんね。




最後までご覧頂き有難うございました




他の会社の企業分析記事もまとめてます
そちらの記事も見て行ってくださいね
👉https://www.makoto-lifecare.com/
📱この記事をスマホでも読みたい方へ
お使いのスマートフォンで以下のQRコードを読み取って、通勤中や週末にも気軽にアクセスできます。
PCで読んで「これは保存しておきたい!」と思った方は、ぜひご活用ください。








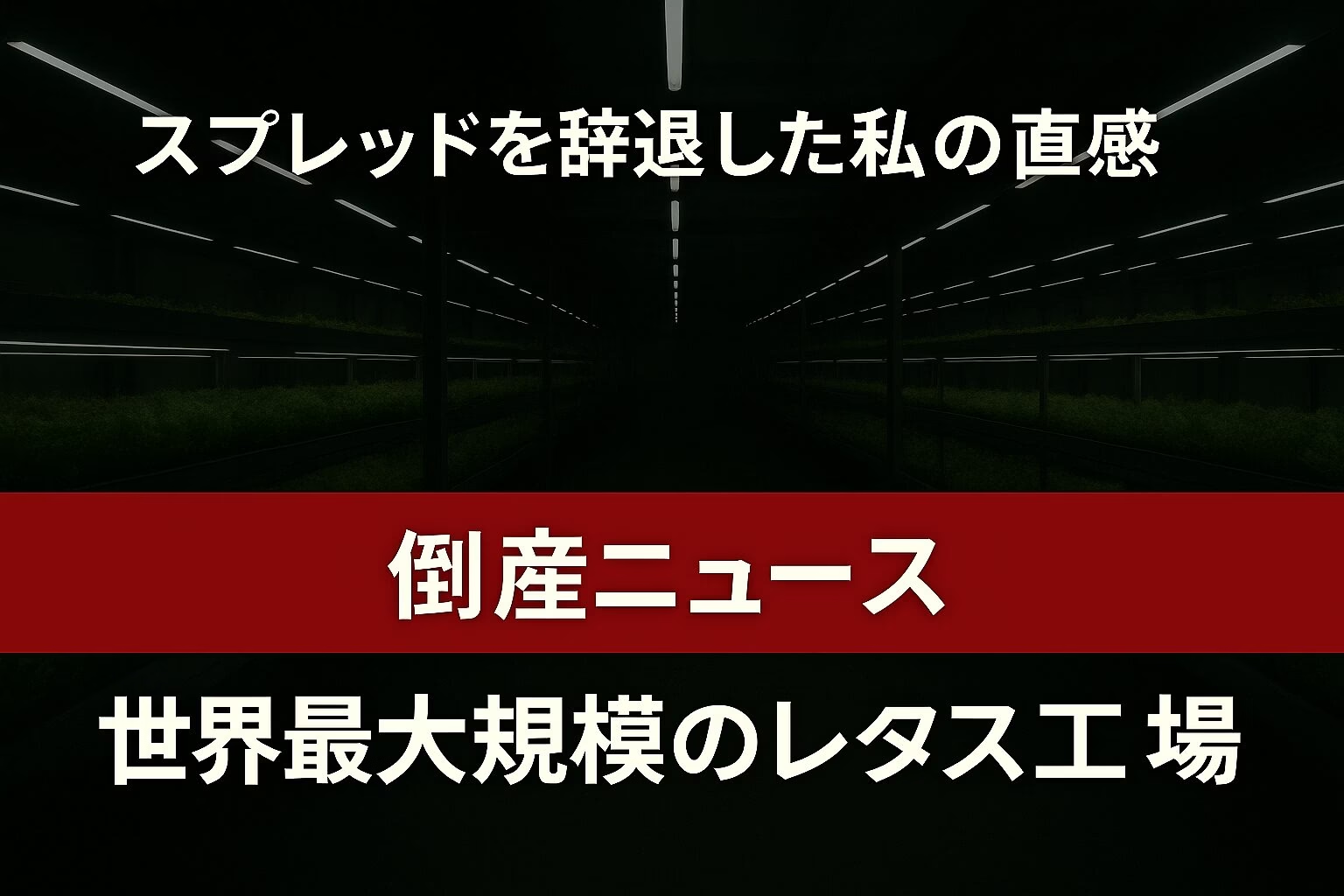

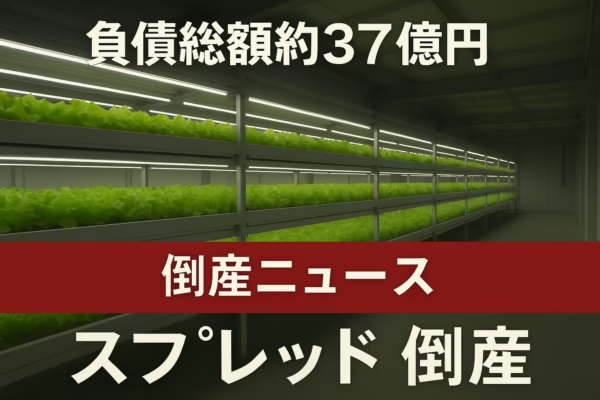


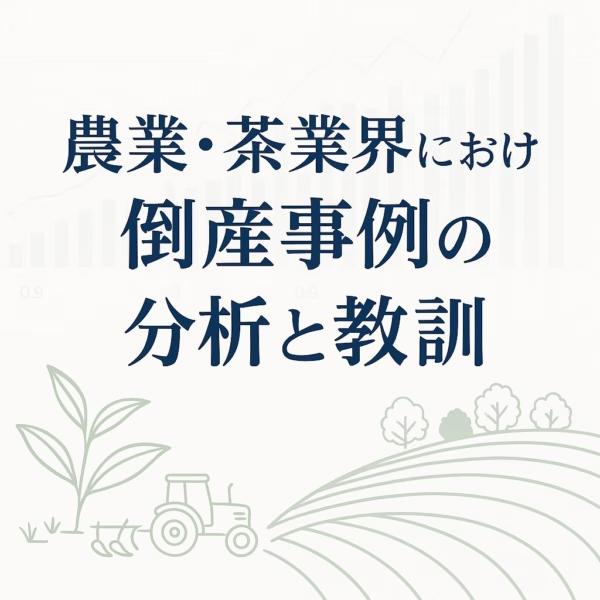
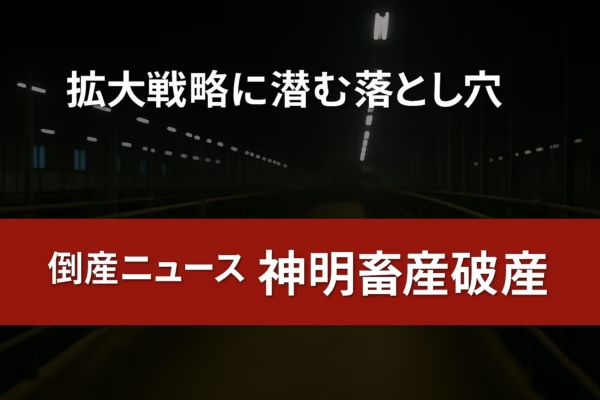
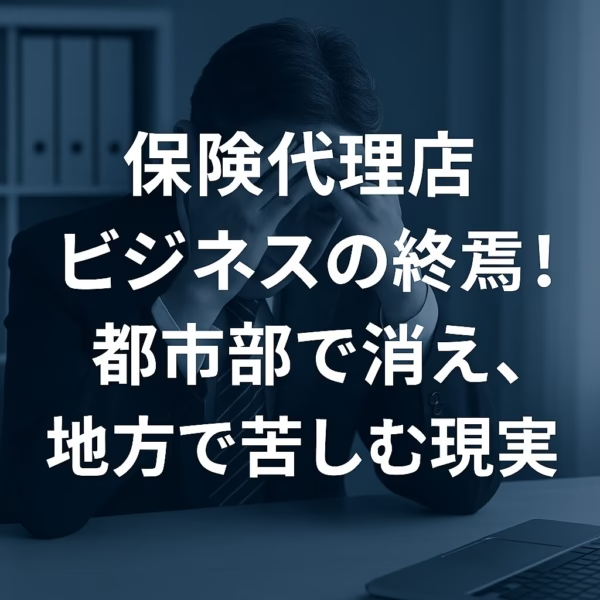
コメント