会社員の副業は、基本的に「会社ごとの就業規則」で制限されています。一方、公務員の副業は「法律」によって厳しく制限されています。
この違い、例えるならこうです。
- 会社員の副業禁止は、子どもの「ぐるぐるパンチ」程度。
- 公務員の副業禁止は、かつて“世界最強”と呼ばれたヘビー級ボクサー・マイク・タイソンのパンチ並みの威力。
ぐるぐるパンチなら痛くもかゆくもないかもしれませんが、タイソンのパンチを食らったら…間違いなくぶっ倒れます。
<会社員と公務員、同じ“副業禁止”でも重みが全然違う>

“ゆるさ” vs “厳しさ”



この例え話、秀逸でしょ?実はYouTuber リベ大両学長が動画「副業禁止 どう乗り越える」の中で使っている表現、私が大のお気に入りのフレーズでしたので、今回は、丸々お借りさせて頂いております。
サラリーマンの副業禁止対策のブログ記事も投稿・公開させて頂いておりますが、公務員の方の中にも「副業を始めたいけれど、公務員だから諦めるしかない」という方に向けても両学長が発信している内容を整理してお届けしたいと考えました。
この動画とブログ記事を読めば、皆さんも経済的自由に向けて確かな一歩を進められることだと思いますので、一緒に勉強していきましょう!
国家公務員法 第103条・第104条の内容とは? 副業禁止事項の記載について
国家公務員法 第103条第1項ではこう書かれています:
職員は、商業、工業または金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問もしくは評議員の職に就き、または自ら営利企業を営んではならない。
つまり、役員や自営業は原則禁止です。
さらに、第104条では次のように定められています:
職員が報酬を得て営利企業以外の事業・団体に関与する場合も、内閣総理大臣および所轄庁の長の許可を要する。
要は、アルバイトも含めて、許可なしに副業してはいけないということです。
地方公務員も同様に、副業は法律で制限されています
地方公務員も、地方公務員法 第38条により同様の制限があります。
なぜここまで厳しいのか?
公務員には、「全体の奉仕者」として、国民や市民のために働く使命があります。
そのため、
- 私利私欲に関わる行為(=営利活動)を避ける必要がある
- 職務専念義務
- 守秘義務
- 信用失墜行為の禁止
といった厳格なルールが課されています。これらもすべて法律で定められており、守らなければ懲戒処分の対象になります。
懲戒処分の内容(一例)
- 免職:いわゆる「クビ」
- 停職:一定期間仕事をさせない
- 減給:給料がカットされる
- 戒告:口頭注意ではなく、記録として残る
評価や昇進にも悪影響が出るため、公務員にとって副業は「気軽にやってみよう」と言えるものではないのです。
結論:会社員と公務員の副業、重さが違う
会社員の副業は「就業規則」で禁止されているだけ。違反しても“社内ペナルティ”止まりのことも多い。
でも公務員の場合は、「法律違反」です。
副業を検討する際は、自分の立場とリスクをきちんと理解しておきましょう。
ちょっと待った!公務員は副業禁止ってこと?
いいえ、完全に諦める必要はありません。
確かに公務員の副業は法律で厳しく制限されていますが、「うまくやる方法」もちゃんとあります。結論から言えば、次の3つの方法です。
✅ 公務員でも副業ができる3つの方法
- 許可を取る
- 家業を手伝う形にする
- 小さな規模であることを意識する
① 許可を取る(最も正攻法)
公務員の副業には例外があります。それが「許可制」です。
国家公務員法第104条・地方公務員法第38条では、所定の手続きで許可を得れば副業が可能とされています。
実際に許可を得ている人はどれくらい?
- 地方公務員:2018年度には全国で42,669件の許可(総務省/jiji.com)
- 国家公務員:令和4年の「自営にかかる兼業」許可は281件(公務員白書)
国家公務員は60万人以上いることを考えると許可件数は少なく、国家よりも地方の方が許可が出やすい傾向があります。
許可が出やすい副業例
- NPO法人などの公益性の高い活動
- 地域の伝統行事や防災活動
- 文化・芸術支援
- 農業・家業・不動産賃貸
最近では、IT系の副業にも許可が出たという実例もあります。
🌱 ポイント:自治体によって許可の基準は違う。
過去の事例を確認し、事前に相談してみる価値は十分にあります。
② 家業を手伝う(間接的な副業)
「本人が営利目的で行う業務は禁止」とされている一方で、
家族が経営する事業のお手伝いであれば、報酬を得なければ原則OKです。
たとえば:
- 親の農業・商店・不動産管理をサポートする
- 配偶者名義の仕事を裏方で支援する
など、間接的な形で家族の収入を支えることは可能です。
⚠️ 注意:報酬の有無や職務専念義務には注意が必要です。
③ 小さな規模であること
最後のポイントは「規模の問題」です。
実際にあった懲戒免職例
佐賀広域消防局の職員が、年間7,000万円の不動産収入を得ていたことが発覚。
副業禁止に違反し、懲戒免職処分を受けました(報道より)。
このケースで問題視されたのは、次の点です。
- 「改善命令を無視した」
- 「明らかに“事業規模”だった」
一方で、駐車場数台/年収500万円以下といった小規模での活動であれば、自治体が「事業性なし」と判断することもあるのです。
同様に、自給自足的な小規模農業も「副業」とは見なされません。
✅ 公務員も“無理せず月5万円”の副業を目指せる
「一発当てて大金持ちに!」という副業は無理でも、“月5万円”の副収入なら、許可の範囲内でも十分可能です。
たとえば:
- 地元NPOでの講師
- 地域スポーツや伝統活動の手伝い
- ITスキルを活かした業務委託(許可取得前提)
- 親名義の農業や民泊の支援
5万円を20年間、年利5%で積み立てれば2,000万円を超える資産になります。
✅ まとめ:公務員の副業は「国のため」と「自分のため」の両立が鍵
「公務員なんだから副業するな」「今の待遇で満足しろ」、そんな声もあります。
でも、公務員こそ“ゆとりある暮らし”をしてほしいと思っています。
- ゆとりがあれば、行政サービスの質も上がる
- 経済的余裕があれば、消費も増えて社会が回る
- 副業を通じて得たスキルが、本業にも活かせるかもしれない
もちろん、法律で定められたルールは守らなければなりません。
でも、その“合法的な余白”をうまく活用して、人生をより豊かにしてほしいと思います。
以下に、3つの副業方法についてポイントと難易度を比較した表をまとめました。どの方法が自分に合っているか、参考にしてみてくださいね。
| 方法 | ポイント | 難易度 |
|---|---|---|
| 許可を取る | 正攻法。公益性がカギ | ★★★★☆ |
| 家業を手伝う | 間接支援。報酬はNG | ★★☆☆☆ |
| 小さな規模に抑える | 収入・事業規模を意識 | ★★★☆☆ |
公務員になったからと言って全ての副業の道が閉ざされるわけではないことがお分かりだと思います。
公務員という立場を守りながら、副業で人生をより豊かにする。
そのためには、正しい情報を知り、正しく動くことが大切です。
一歩ずつ、ゆとりある暮らしを目指していきましょう。
こちらの記事をご覧頂きましたら、両学長のYouTube動画も是非ご視聴ください。
皆さんの人生に、きっと新たな気づきが生まれると思いますよ!




公務員の方でも許可が下りたら副業できるんですね
ご家族のお手伝い、少額の報酬もOKとか嬉しいですね




この他にもお役立ち情報を発信してますので
どうぞご覧くださいね
👉https://www.makoto-lifecare.com/
📱この記事をスマホでも読みたい方へ
お使いのスマートフォンで以下のQRコードを読み取って、通勤中や週末にも気軽にアクセスできます。
PCで読んで「これは保存しておきたい!」と思った方は、ぜひご活用ください。

-



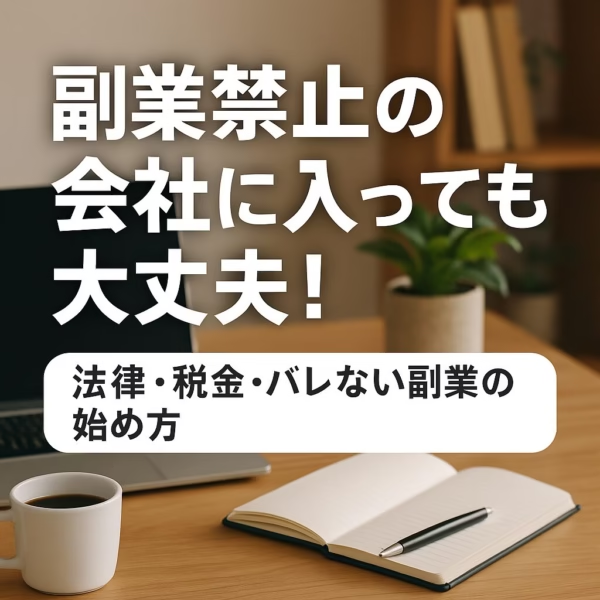
副業禁止の会社に入っても大丈夫!法律・税金・バレない副業の始め方
副業禁止の会社でも副業できる?法律・憲法・判例・税金・バレない工夫まで、実例付きでやさしく解説! -



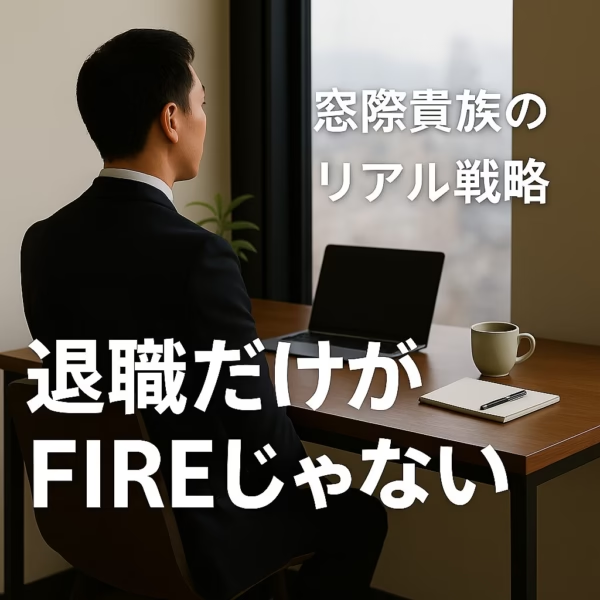
退職だけがFIREじゃない。“窓際貴族”という勝ち残り戦略【投資うさぎ式】
退職だけがFIREじゃない。信頼と資産を築き、責任あるポジションから静かに離れる「窓際貴族」という現実的な自由のかたちを解説。 -




JAの暗闇(農協の闇)と賢く付き合う方法:書籍レビュー『農協の闇(くらやみ)』
書籍『農協の闇(くらやみ)』で明かされた問題点を基に、農業者として安心してJAを活用する方法を提案します。


コメント