「うしおじさん」の愛称で親しまれていた「大山牧場」が2024年10月1日付けで事業を停止。
自己破産申請の準備に入ったことが報じられました。
コロナ禍の影響で売り上げが減少し、燃料費やえさ代の値上がりも重なり、
資金繰りが厳しくなったため、事業の継続を断念したとのことです。
順調にブランド化が浸透し、成功した酪農家の代名詞とも言える「大山牧場」、
この破産を報せるニュースは地元経済界や全国の酪農家に大きな衝撃を与えました。
日本の酪農の将来はどうなるのでしょうか?
皆さんと一緒に考えるキッカケにしたいと思います。
 パンチです
パンチですどうぞ最後までご覧くださいね
大山牧場の概要
大山牧場は、香川県さぬき市大川町にある酪農業者でした。
1949年に創業し、香川県内で唯一ジャージー牛のみを飼育。
牛乳やチーズ、ヨーグルトなどの乳製品を生産し、
直営の小売店や大都市圏のデパート、スーパーなどで販売していました。
大山牧場の製品
- ノンホモジャージー牛乳: 500mlと200mlのパッケージがあり、シンプルで清潔感のあるデザインです。
- クリームパン: 冷蔵で販売されており、パッケージには「うしおじさん」のロゴが印刷されています。
- チーズセット: モッツァレラ、カチョカバロ、酪醤(らくびしお)醤油漬けチーズなどが含まれており、ギフトセットとしても人気がありました。
- ヨーグルトセット: 和三盆ヨーグルトなどが含まれており、パッケージには高級感があります。
これらの製品は、品質の高さと風味の良さで多くの消費者に支持されていました。



引用元:一般社団法人 さぬき市観光協会
ジャージー牛を飼育するメリットとデメリット
メリット
- 高品質な牛乳: ジャージー牛の牛乳は乳脂肪分やタンパク質の含有量が高く、濃厚で美味しいと評価されています。
- 乳脂肪率の高さ: 乳脂肪率が高いため、バターやチーズなどの乳製品の製造に適しています。
- 飼育のしやすさ: ジャージー牛は体が小さく、飼育スペースが少なくて済むため、管理がしやすいです。
- 病気に強い品種: ジャージー牛は一般的に健康で、病気に強いとされています。
デメリット
- 乳量の少なさ: ジャージー牛の乳量はホルスタイン種に比べて少ないため、総生産量が低くなります。
- オスの子牛の価値が低い: オスの子牛は肉牛としての経済的価値も低く、生後すぐに処分されることが多いです。
- 市場の需要: 日本では乳量が重視されるため、ジャージー牛の乳質の良さが十分に評価されないことがあります。
- 飼育コスト: 高品質な飼料が必要なため、飼育コストが高くなることがあります。
つまり…
ジャージー牛の生乳は「美味しい」「希少性がある」「加工にも向いている」から売りやすいけれども、
「乳量が少なく」「コストが高い」ため利益を稼ぎにくいビジネス構造です。
感染症の拡大による消費冷え込み・異常気象、乳量の減少や円安による飼料高など、
何らかのアクシデントにより会社経営が一気に傾いてしまうリスクが大きいのです。
酪農経営 安定のための取り組み
日本国内でジャージー牛を生育している大きな酪農家は、経営安定のため以下のような取り組みをしています。
- 6次産業化の推進: ジャージー牛の乳製品や肉製品を自社で加工・販売することで、付加価値を高めています。例えば、牛乳、チーズ、バター、ヨーグルトなどの乳製品や、ジャージー牛の肉を使った製品を販売することで、収益を多様化しています。
- 観光農園の運営: 牧場を観光地として開放し、搾乳体験や動物とのふれあい体験を提供することで、観光客からの収益を得ています。これにより、地域の活性化にも貢献しています。
- 環境に配慮した飼育方法: 放牧を取り入れた飼育方法を採用し、自然環境に配慮した経営を行っています。これにより、飼料コストの削減や牛の健康維持が図られています。
- 地域との連携: 地域の他の農家や企業と連携し、共同でイベントを開催したり、地域ブランドとしての価値を高める取り組みを行っています。
- 高品質な製品の提供: ジャージー牛の高品質な牛乳や乳製品を提供することで、消費者からの信頼を得ています。特に、低温殺菌や無添加の製品を提供することで、健康志向の消費者にアピールしています。
しかしまさにこれは大山牧場の取り組みそのものなのです。
お手本が破産したというニュースが酪農家に与えた衝撃は大きいものだったと思われます。
何をどうすれば日本の酪農家は生き残っていけるのか…一つの答えは大資本との提携が考えられます。
ファーマーズホールディングス株式会社の生き残り戦略
岡山県倉敷市に本社があるファーマーズホールディングス株式会社は、
2023年4月28日に野村キャピタル・パートナーズ株式会社との資本提携を発表しました。
ファーマーズホールディングスは、2017年9月に設立され、酪農、物流、飼料などの分野で活動しています。
この資本提携は設立当初は勿論想定外であったとは思われますが、
ファーマーズホールディングスは野村グループのネットワークや金融サービス機能を活用し、
経営管理の高度化や事業拡大を図ることが期待されています。
ひとたび売上の大幅な減少や売掛金の回収が滞るような事態が生じた際には、
酪農業者が単独での生き残りが不可能なことは明らかです。
事業を終了させる決断をした「大山牧場」と、
株式上場を目標に事業継続している「ファーマーズホールディングス株式会社」との違いは
大資本との提携の有無であろうかと考えられます。
つまりは一緒にビジネスをするに値する企業として外部から評価されている点が重要なのです。
追記:ファーマーズホールディングスの民事再生法 適用申請について
2025年7月24日に酪農業界に衝撃のニュースが届きました。
大資本との提携は、未来が見通せなくなってきている日本の酪農業界にとって
数少ない生き残り手段だと見られてました。
しかし約91億円の負債を抱えたファーマーズホールディングスが
突然、民事再生法の適用を申請したのです。
これだけ多くの負債を背負って再建の道筋を辿るのは困難極まりないと思います。
今後もこのニュースには注目し、他の酪農家の動きについてもお知らせしたいと思います。
破産と特別清算の違い
「破産」と「特別清算」はどちらも清算型倒産手続きですが、いくつかの重要な違いがあります。
破産
- 根拠法: 破産法に基づいて行われます。
- 申立人: 債権者、債務者、取締役、清算人が申立てを行うことができます。
- 同意の必要性: 債権者や株主の同意は不要です。
- 財産管理: 破産管財人が裁判所によって選任され、会社財産の管理処分権を持ちます。
- 否認権: 破産には否認権があり、特定の債権者への優先的な弁済や不当な財産減少行為を取り戻すことができます。
特別清算
- 根拠法: 会社法に基づいて行われます。
- 申立人: 債権者、清算人、監査役、株主が申立てを行うことができます。
- 同意の必要性: 株主総会の特別決議と債権者の同意が必要です。特に、債権者の3分の2以上の同意が求められます。
- 財産管理: 清算人が選任され、会社財産の管理処分権を持ちます。
- 否認権: 特別清算には否認権がありません。
主な違い
- 法的根拠: 破産は破産法、特別清算は会社法に基づきます。
- 同意の必要性: 破産は同意不要、特別清算は株主と債権者の同意が必要です。
- 財産管理者: 破産は破産管財人、特別清算は清算人が管理します。
- 否認権の有無: 破産には否認権がありますが、特別清算にはありません。
これらの違いにより、特別清算は比較的迅速かつ柔軟に行える手続きであり、破産よりも費用が安いことが多いです。
特別清算が破産よりも費用が安くなる理由とデメリット
特別清算の費用が破産よりも安くなる主な理由
- 予納金: 特別清算の予納金は約5万円程度で済むことが多いですが、破産の場合は最低でも20万円が必要です。
- 弁護士費用: 特別清算の弁護士費用は約100万円程度ですが、破産手続きの弁護士費用はこれよりも高額になることが一般的です。
- 手続きの簡便さ: 特別清算は手続きが比較的簡便で迅速に進むため、手続きにかかる時間と費用が少なくなります。
特別清算のデメリット
- 債権者の同意が必要: 特別清算を進めるには、債権者の過半数の同意と総債権額の3分の2以上の同意が必要です。同意が得られない場合は破産手続きを選ばざるを得ません。
- 未払い債権の一部を弁済する余力が必要: 会社の資産から未払いの債権の一部を弁済できる余力が必要です。余力が全くない場合は特別清算手続きができません。
- 株式会社のみ利用可能: 特別清算は株式会社に限られ、合同会社や学校法人などは利用できません。
- 否認権がない: 破産手続きには否認権があり、不当な財産減少行為を取り戻すことができますが、特別清算にはこの権利がありません。
- 社長の債務整理が必要: 社長が連帯保証人になっている場合、特別清算手続きによって社長が会社の借金を返済することになります。そのため、社長本人の債務整理手続きが必要です。
これらの点を考慮して、特別清算と破産のどちらを選ぶかを判断することが重要です。
大山牧場が破産を選んだ理由
大山牧場が特別清算ではなく破産を選んだ理由について、いくつかの可能性を推測してみます。
- 債権者の同意が得られなかった 特別清算を進めるには、債権者の過半数の同意と総債権額の3分の2以上の同意が必要です。大山牧場の場合、債権者の同意を得ることが難しかった可能性があります。
- 資産の不足 特別清算を行うためには、会社の資産から未払いの債権の一部を弁済できる余力が必要です。大山牧場がこの余力を持っていなかったため、特別清算を選択できなかった可能性があります。
- 法的アドバイス 大山牧場が法的アドバイスを受けた結果、破産手続きが最適な選択肢であると判断された可能性があります。破産手続きには否認権があり、不当な財産減少行為を取り戻すことができるため、これが有利と判断されたかもしれません。
- 経営者の意向 経営者が特別清算よりも破産手続きを選好した可能性もあります。破産手続きは裁判所の管理下で進行するため、透明性が高く、債権者に対する説明責任を果たしやすいという利点があります。
- 時間的な制約 特別清算は株主総会の特別決議や債権者の同意を得るために時間がかかることがあります。大山牧場が迅速に手続きを進める必要があったため、破産手続きを選んだ可能性も考えられます。
今回の大山牧場の負債総額は1億円程度であり、市場認知度が高い製品ブランドを持つ優良、いや有名企業でした。
資本提携や銀行からの追加支援もなく、あえてコストがかかる「破産」を選んだ理由を邪推してしまいます。
具体的な理由は大山牧場の経営陣や法的アドバイザーのみが知るところで、表に出て来ることはないでしょうね。
数年前に大きなニュースとなった畜産関係では100億円を超える規模の倒産についても言及しております。
これを見ると改めて『うしおじさんは、たったの1億円の負債で破産?』と思うのは私だけでしょうか?
まとめ
大山牧場の破産は、全国にファンがいる「うしおじさん」の商品がもう見られなくなることを意味します。
このニュースは「大山牧場のビジネススタイル」を目標に頑張って来られている酪農家、
特にジャージー牛メインの一部の酪農家にとっては、
消費者の方たち以上に大きなインパクトがあったと思われます。
最近、長期保存が可能な牛乳「ロングライフミルク(LL)」の生産・売上は、増加傾向にあります。
食品ロス対策や災害時の備蓄用に重宝する側面は評価できると思います。
しかしながら、日本で牛乳も輸入に頼る未来が現実的になっていると感じるのは私だけでしょうか?
価格転嫁が難しく廃業や倒産に追い込まれているのは焼肉屋、ラーメン屋など多岐に及びます。
日本の食文化が、貧しくなった日本経済とともに衰退していくのを黙って見守るだけでは寂しいですね。
良いものは少し高くても買うという意識を実際に行動に移すことは、
日々の暮らしのなかで大変なことなのは分かりますが
我々が生産者に対してできる応援はこれだけではありません。
買って良かったものを見つけた時には
通販サイトのレビューにコメントしたり
SNSで発信する
これこそが今の時代にマッチした企業の応援スタイルだと思いますがいかがでしょうか?![]()
追記 2024年12月6日
ネットニュースで「国内の酪農家、初の1万戸割れ」と先日報じられました。
2024年10月時点の国内の酪農家の数は9960戸と、
調査を始めた2005年以降、初めて1万戸を下回りました。
エサ代や燃料価格の高騰する一方で売り渡し価格は据え置きで、
酪農家の半数以上は赤字経営を強いられているそうです。
規模が大きなところほど大変で、
借金でなんとか経営を継続しているところもあるようです。
そこに金利上昇が更に追い打ちを掛けるのですから、
酪農家のおよそ半数が「離農を検討している」ということです。
誰かの犠牲の上に成り立つビジネスは長続きしません。
「うしおじさん」は大怪我する前の「破産」は将来を見据えた賢明な判断だったのかも知れません。
次の世代の方たちから「日本にも乳牛がいた?嘘でしょ?」と驚かれる、
そんな未来がすぐそこまで来ているような気がします。
そうならないためにも、少し高くても乳製品を買う努力を惜しまず、
SNS発信などで酪農関係者へ支援を続けてみてはいかがでしょうか?
🔍 なぜこの記事を書くのか?
👉 筆者の想いはこちらから



最後までご覧頂き有難うございました。
“When the weight of tradition becomes a burden,
it’s time to rethink what we truly want to carry into the future.”
「伝統の重みが“重荷”に変わるとき、私たちは“未来に何を持ち運びたいのか”を、真剣に見直す時が来る。」
📱この記事をスマホでも読みたい方へ
お使いのスマートフォンで以下のQRコードを読み取って、通勤中や週末にも気軽にアクセスできます。
PCで読んで「これは保存しておきたい!」と思った方は、ぜひご活用ください。










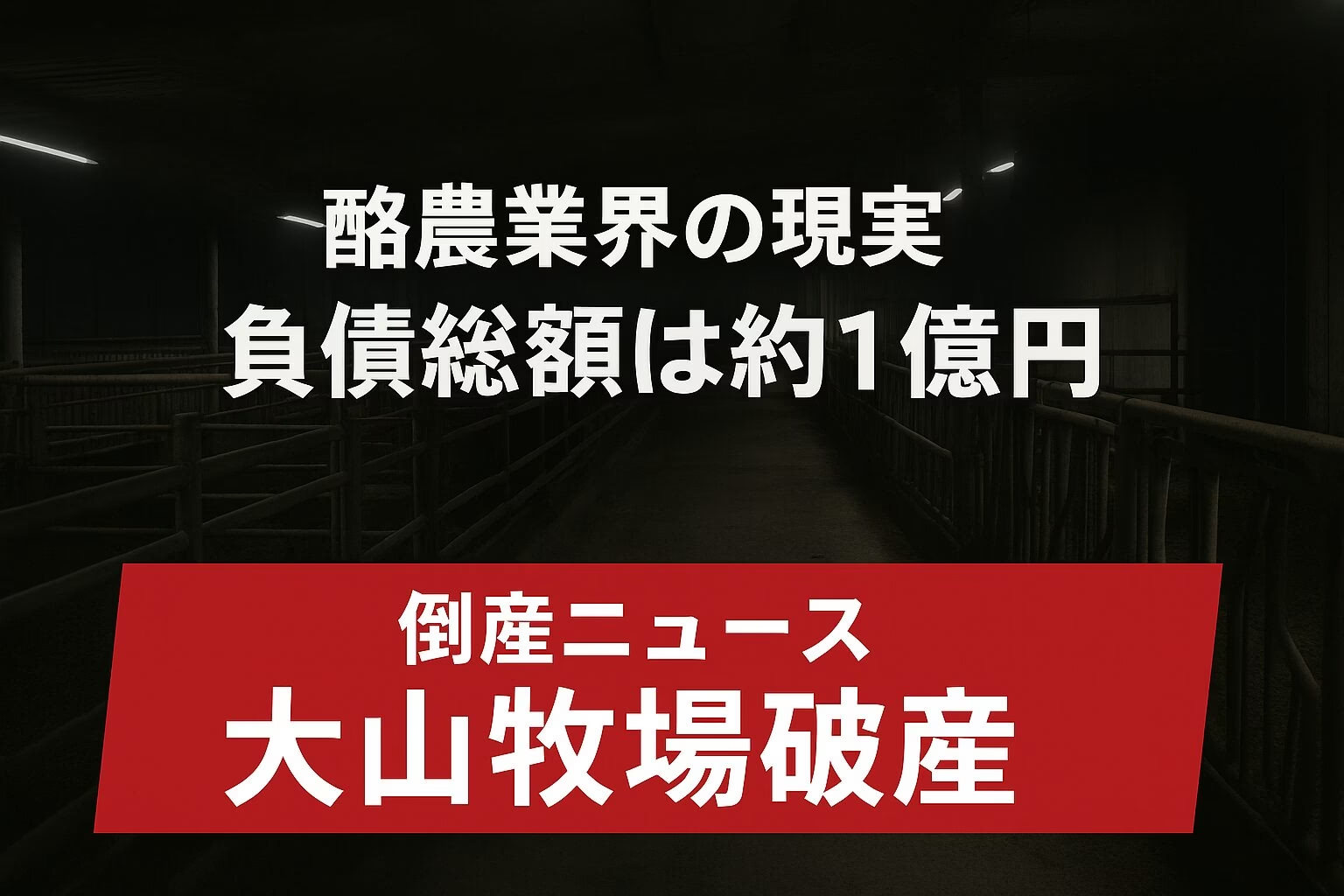
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49f44d5a.dc33229e.49f44d5b.739c87af/?me_id=1238096&item_id=10000912&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhanabatake%2Fcabinet%2Fcheese%2F150217%2Fch150217n.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49f44d5a.dc33229e.49f44d5b.739c87af/?me_id=1238096&item_id=10001423&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhanabatake%2Fcabinet%2F2017%2Foutlet%2F160118%2Fca160118n.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
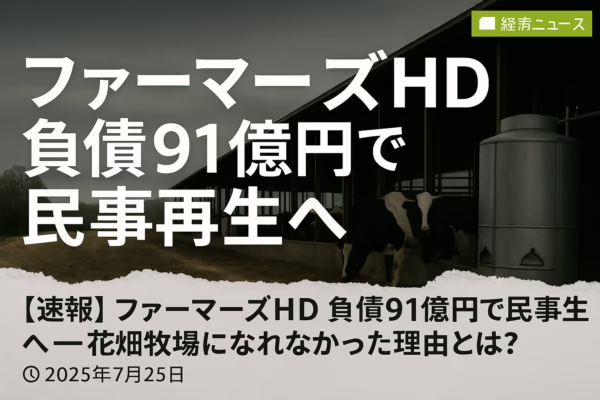
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4af54dbd.7e2408f8.4af54dbe.ba22d89e/?me_id=1363209&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff016314-otofuke%2Fcabinet%2F10125159%2Fa38_00s.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
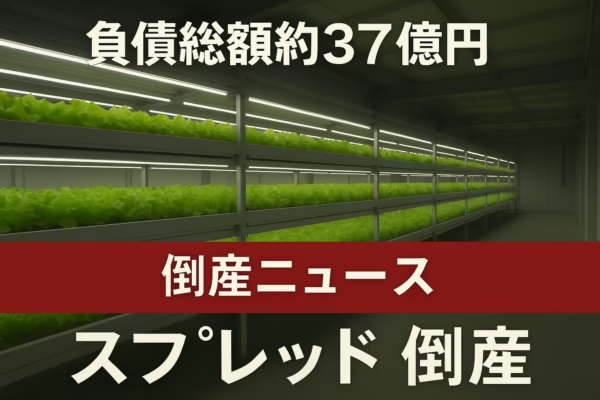
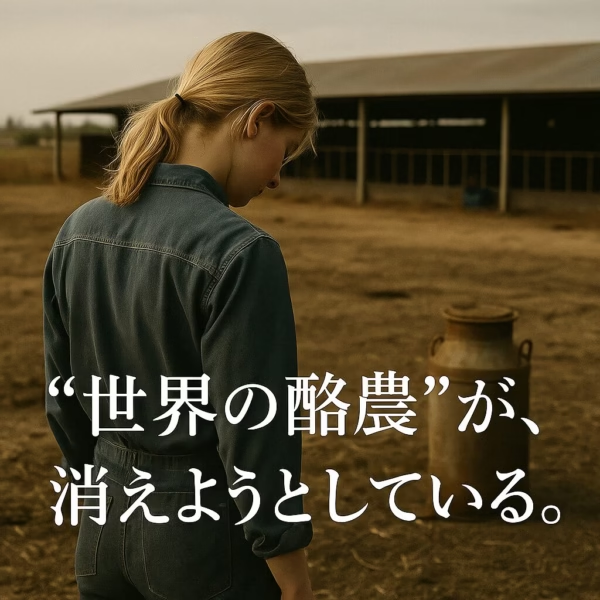


コメント