- ▶ 米国デルモンテ・フーズ破産と日本市場への影響とは?
- ▶ キッコーマンによるデルモンテ買収の戦略的成功の秘密
- ▶ ブランド価値最大化に向けた日本デルモンテ独自の取り組み
2025年7月1日付で米国の食品メーカーであるデルモンテ・フーズ(Del Monte Foods)が、連邦破産法第11条(日本の民事再生法に相当)の適用を申請しました。
「グローバル企業」と聞くと、世界中で一つの巨大な組織が同じブランドを展開しているように思われがちです。
事実、日本でも「愛用しているトマトジュースが飲めなくなるの?」といった不安の声がSNSでも拡散されました。
しかし日本市場への直接的な影響は「ほぼゼロ」。
この事実に皆さん「なぜ?」と驚かれたことだと思います。
実はグローバル企業の実態は想像以上に複雑で、国や地域によって事業形態やブランドの権利関係が大きく異なることが珍しくありません。
その好例が、2025年7月に経営危機に陥った「米国デルモンテ・フーズ」、日本で「デルモンテ」ブランドを展開する「キッコーマン」の関係なのです。
今回はキッコーマンが「デルモンテ」ブランドを傘下に入れた経緯や、その後の展開などについて紹介します。
米国デルモンテ・フーズの経営危機と日本への影響回避
デルモンテ・フーズ(Del Monte Foods)は、米国の食品加工大手として知られています。
しかし2000年代に入ると、米国内の缶詰市場の縮小、消費者の健康志向の高まり、プライベートブランドとの競争激化、そして多額の負債が重なりました。
最終的に経営が悪化し、2025年7月に米国事業の再編を余儀なくされました。
負債総額は現時点の予測値で、最悪の場合は約100億ドル(約1.4兆円)と見込まれています。
これだけの規模の会社が経営危機に瀕すれば、その傘下の海外事業も連鎖的に影響を受けるものと思われがちです。
私を含む多くの日本人が「デルモンテのケチャップが買えなくなるの?」と不安になったことだと思いますが、日本の日本デルモンテ株式会社は、この米国デルモンテ・フーズの経営危機からほとんど影響を受けませんでした。
この背景には、キッコーマンによる戦略的なブランド買収と独自の発展ビジョンがあったのです。
複雑なブランドの歴史:ナビスコがデルモンテの商標を持っていた?
キッコーマンは1961年に吉幸食品工業(後の日本デルモンテ株式会社)を設立し、1963年にはデルモンテ社との提携を開始。日本国内でのデルモンテ製品(トマトケチャップ、トマトジュースなど)の製造・販売を手掛けることになります。
さらに重要なのは、デルモンテブランドの商標権の扱いです。デルモンテは世界的に展開されていますが、その商標権は地域や時期によって異なる企業が保有する、複雑な歴史を辿っていました。
1980年代後半、巨大コングロマリット(複合企業)であったRJRナビスコが、一時期、米国以外の国際的なデルモンテブランドの商標権を保有していました。この時代は、大型の企業買収や合併が盛んな時期で、当時、RJRナビスコも同様にレバレッジド・バイアウト(LBO)による買収を進めていました。しかし投機的な買収に失敗し、莫大な負債を抱えてしまった結果、RJRナビスコは、その処理のために傘下の事業やブランドの売却を進めていました。
キッコーマンは、この状況を戦略的なチャンスと捉えたのです。
1990年1月10日、同社は日本におけるデルモンテ事業の長期的な安定を目指し、RJRナビスコから「デルモンテ」商標の日本国内での使用権を約210億円で取得しました。
当時はバブル景気の真っ只中にありましたが、この買収は「極めて戦略的で大胆な投資」と評価されました。
この決断のおかげで、日本におけるデルモンテブランドは米国デルモンテ・フーズの経営状況から独立し、現在のような安定的な運営体制が築かれる礎となったのです。
キッコーマンによるデルモンテ買収の戦略的成功
キッコーマンによるデルモンテの商標権取得は、極めて成功した戦略的投資であったと評価されています。
その理由は以下の通り多岐にわたります。
- 収益源の確保とリスク回避 商標使用権の保有により、契約更新や米国デルモンテ・フーズの経営影響を排除。日本市場で高いブランド認知度を持つ製品を安定的な収益源としました。
- 事業ポートフォリオの多角化 トマト加工品や飲料事業への拡大により、特定製品への依存を低減。流通網やマーケティングノウハウを活用し、シナジー効果を創出しました。
- ローカライゼーションによる価値向上 日本市場に特化した製品最適化(例:ケチャップやジュースの味調整)により、ブランドの競争力を強化しました。
- 地域展開の足がかり アジア・オセアニア市場での販売権拡大を通じ、新たな成長機会を確保。デルモンテはグローバル戦略において重要な役割を担っています。
例えば、こちらの「リコピンリッチ」という商品、その名称や「リコピンが1.5倍」という訴求は、日本の消費者の健康志向や機能性食品への関心の高さを意識したものであり、これも日本市場に特化した製品戦略の一環と言えます。
このような独自の商品は、キッコーマンがデルモンテブランドの商標権を保有し、日本の消費者のニーズに合わせて製品開発を自由に行えるがゆえに生まれるものです。
これは、まさに「徹底したローカライゼーションによるブランド価値向上」の具体的な事例と言えるでしょう。
ブランド価値最大化に向けた継続的な取り組み:工場再編
キッコーマンは、デルモンテブランドの価値を最大化するために、日本の市場環境の変化にも常に対応しており、その一環として、日本デルモンテの生産体制の見直しを実施しました。
2023年10月、キッコーマンは日本デルモンテの生産拠点を再編する計画を発表し、長野工場(長野県千曲市)を2025年6月までに閉鎖し、生産機能を群馬工場(群馬県沼田市)に集約しました。
群馬工場には新たな設備投資が行われ、トマト調味料を中心とした製品の生産効率がさらに向上することが期待されています。
この再編の背景には、日本の少子高齢化や単身世帯の増加、労働人口の減少といった社会構造の変化があります。これらの変化に対応し、生産性を向上させ、より効率的な運営体制を構築することが、デルモンテブランドの持続的な成長には不可欠と判断されました。
このように、キッコーマンはデルモンテブランドを単に保有するだけでなく、日本の市場環境に合わせて生産体制を最適化し、ブランド価値の最大化に継続的に注力しているのです。
まとめ
キッコーマンによるデルモンテ商標権・販売権の取得は、単なるブランド買収に留まらず、事業基盤の強化と将来の成長を見据えた戦略的投資でした。
米国デルモンテ・フーズの破綻にも影響を受けず、アジア圏への進出を後押しする重要な武器となったこの買収は、成功例といえます。
今後、この事例は、グローバル企業が複雑な市場戦略を駆使し、成功を収めるプロセスを示す良いお手本として語り継がれることでしょう。




最後までご覧いただき有難うございます
-




アメリカのデルモンテ・フーズ破産、負債総額1兆円超えの可能性も―日本市場への影響は?
こちらはGoogleでは見つけることが出来ない Microsoft Bing限定公開のブログです… -




キユーピー ベビーフード事業からの撤退を発表、そして「こども家庭庁」は沈黙
キューピーが不採算となったベビーフード事業からの撤退を発表しました。なぜ子ども家庭庁は動かないのでしょうか? -



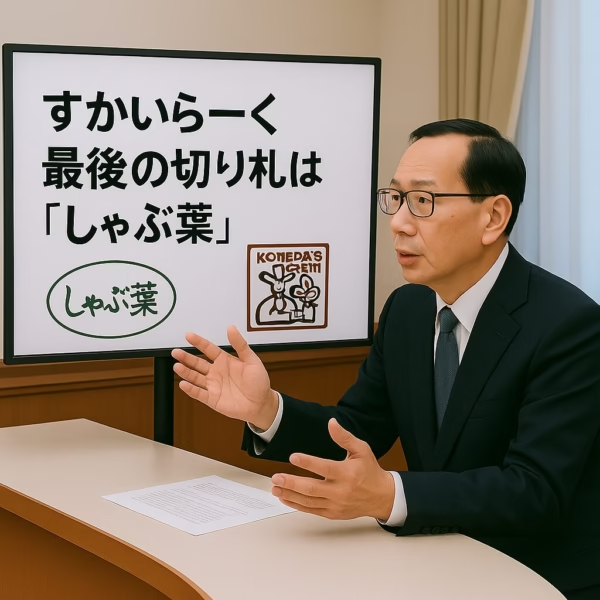
すかいらーく最後の切り札は「しゃぶ葉」-FC転換がもたらす経営再建の道すじ
全都道府県制覇、ドリンクバーの先駆け、1,000店舗達成──かつて“外食の王者”と呼ば… -




丸亀製麺が築く働きがいと未来─直営主義が生む熱血社員たちのリアル
「従業員の幸せなくして、KANDO(感動)は生まれない。」 多くの外食チェーンが掲… -




電力会社と野菜工場:スプレッドとプランツラボラトリーの「明」と「暗」
植物工場の成功例と課題について考察し、未来の農業の可能性を探る内容です。 -



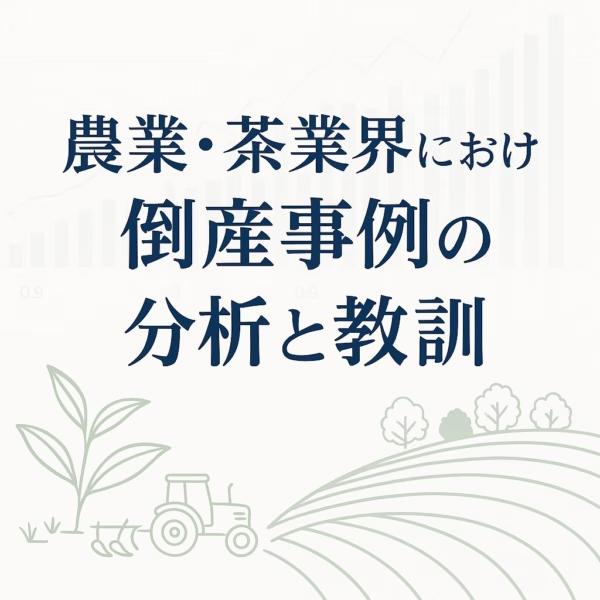
まとめ記事 農業・茶業界における倒産事例の分析と教訓
最近話題となった農業・茶業関係の倒産に関するまとめ記事です。


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a11f316.f2348186.4a11f317.5d85bf19/?me_id=1365211&item_id=10000605&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff102067-numata%2Fcabinet%2Fimg%2Fp%2F11_ibs-052001.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)


コメント