こちらはGoogleでは見つけることが出来ない
Microsoft Bing限定公開のブログです!
(一部記事を除きます)
- ▶ キユーピーがベビーフード事業から撤退することを発表し、育児家庭が不安を感じている現状
- ▶ 「こども家庭庁」の機能不全と政策課題
- ▶ 求められる「実効性ある政策」と「社会インフラとしての子育て支援」の視点
2025年6月12日、キューピーが2026年8月末をもってベビーフード事業からの撤退を発表しました。

これに対し、乳幼児を抱える多くのお母さんたちからは悲鳴にも似た声が上がり、事業継続を求める署名活動まで起きていると報じられています。
「キユーピーのベビーフードがなかったら、子どもと外出することなんてできなかった」
「これがなくなるなら、2人目は諦める」
こういった切実な声がSNS上に溢れているのを目にすると、単なる企業の事業撤退という枠を超え、
多くの家庭の「日常」が脅かされている深刻な問題であることがわかります。




どうぞ最後までご覧くださいね
「お金の教養講座」のご紹介です
\まずは無料セミナー受講から、始めてみませんか?/




受講生満足度98.7%の講義を
体験してみてくださいネ
キユーピーの事業撤退、なぜ、こんなにも騒がれるのか?
ベビーフードと一口に言っても、離乳食の進捗に合わせて7ヶ月、9ヶ月と細かく対象年齢が分かれます。
肉じゃが、シチュー、魚のクリーム煮、さらにはバナナプリン、そのラインナップは72品目にも及びます。
これだけの多品種を揃え、安定的に供給するには、並々ならぬ企業努力が必要なはずです。
更に少子化が加速していくなかでビジネス継続のために人材育成や設備更新などが必要なことを考えると
65年間の事業運営に幕を下ろすという判断も理解できます。
しかし、このキユーピーの撤退を「今まで、ありがとう」と素直に言えないのが、
もう一つのベビーフードの大手サプライヤーである
「和光堂への不信感」が
一部の消費者の間でくすぶっているからだと思われます。
和光堂が供給するベビーフードや粉ミルクにおける異物混入の報告が増加していることに起因して、
同社に対する不安の声がSNS上で拡散されているようです。
実際、近所のスーパーマーケットのベビーフード売り場を見てみても、
割高なキユーピー製品の方が売れている様子を伺い知ることができました。
例えばキユーピーの「ほっくり肉じゃが弁当 90gX2」は売れた形跡があり棚に隙間が確認できましたが、
和光堂の「じゃがいもとお肉のカレーライスランチ 170g 」は、ギッシリと棚に収められていました。
キユーピーの製品は多くの親にとって「頼れる選択肢」であったため、今回の撤退がもたらす影響が大きいのです。



ただ和光堂もラインナップに、今までになかった「月齢5か月」からを対象とした新製品を発売するなど、
消費者の信頼を取り戻すための取り組みに力を注いでいるのが見て取れます。
和光堂の今後の評価がどうなるか、注目ですね。
2025年7月11日付追記 キッコーマンがベビーフード事業に参入
大手食品メーカー「キッコーマン」が
「卵や落花生など食物アレルギーが起こりやすい食材の離乳食」の
本格販売を始めたことを日本経済新聞が報じました。



小児アレルギーの専門医が監修し開発し、1袋に個包装されたキューブが6個入り。
子供のペースに合わせて食べる量を少しずつ増やしながら食材に慣らすことができるのが特長です。
価格は固ゆでした卵黄と卵白が1袋ずつ入った
「6ヶ月からのたまごセット」が1080円
落花生が4袋入った「1歳からの落花生」が2160円
今後、さらにラインアップが充実される予定です。
キューピーが事業撤退を決めたなかで、新たな選択肢が増えたことは私たちにとっても嬉しいニュースですね。
\楽天市場のショップでお買い求めできますよ!/
🆕 赤ちゃんが理由もなく機嫌が悪くなる原因、もしかすると「鉄分不足」かも?
1〜2歳の乳児が鉄分不足になると、脳や神経の発達に悪影響を及ぼしたり、鉄欠乏性貧血を引き起こすリスクがあるそうですから心配ですね。
鉄分不足が引き起こす問題
- 脳・神経の発達への影響: 鉄は神経伝達物質の合成や神経細胞の発達に不可欠な栄養素です。この時期の鉄不足は、認知機能、記憶力、注意力といった脳の発達に長期的な影響を与える可能性が指摘されています。
- 鉄欠乏性貧血: 鉄分が不足すると、酸素を全身に運ぶヘモグロビンが十分に作られず、貧血になります。主な症状として、顔色が青白い、疲れやすい、食欲不振、元気がないなどが見られます。
- その他の症状: ひきつけなどの神経症状との関連性も示唆されていて、「理由のない機嫌の悪さ」の原因となることもあります。
なぜ1〜2歳が特にリスクが高いのか?
生後6ヶ月頃までは、母親から受け継いだ鉄分を体内に蓄えているため、鉄不足になることは少ないとされています。
しかし、生後6ヶ月以降は、急速な成長に伴って鉄の需要が高まります。
この時期に離乳食などで鉄分を十分に補給しないと、供給が需要に追いつかず、鉄欠乏に陥りやすくなります。
母体からの鉄分貯蔵が徐々に枯渇し始める時期なので、特に、母乳栄養児や、偏食がちな子どもは注意が必要です。
乳児の鉄分補給に「はぐくみ太郎」、いかがですか?
1~2歳が1日に摂る鉄分の推奨量は4.5mgです。
「はぐくみ太郎」は、それに加えて亜鉛やカルシウム、ビタミンB1なども配合されてます。
食べものの味を損ねないので、大好きな離乳食に混ぜてあげると、気づかずに食べてくれたと、楽天市場には喜びのレビューがたくさん届いています。
好き嫌いが多くて毎日の食事に悩んでいるご家庭には、まさに救世主になるかもしれませんね。



\もし興味があったらこちらをご覧になってみてくださいね/
出典・参考情報
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
子ども家庭庁への期待と現実
本日、2025年6月17日正午の段階では本件に対して「こども家庭庁」からのコメントは確認できませんでした。
こうした子育て世帯の切実な声に対し、現時点で、政府の反応は鈍いと言わざるを得ません。
2023年4月に発足した「こども家庭庁」は、子どもに関する政策を一元的に所管し、「司令塔」としての役割を果たすことが期待されていました。
しかし、その評判はすこぶる芳しくないのが現状です。
令和7年度予算案は一般会計と特別会計を含めた総額で7兆3,270億円にのぼるとされています。
「こどもまんなか社会の実現」を目指し、主な歳出予定として「児童手当の拡充」、「幼児教育と保育の質向上」のほかに「妊娠・出産サポート」があげられています。
「こども家庭庁」は「こども若者★いけんぷらす」という意見表明の場を提供しているようです。
キユーピーは将来にわたる少子化状態での事業採算性が見合わないものとして事業撤退を決定しているのです。
営利活動を目的としている私企業に対して署名を出したところで、翻意されることはないでしょう。
だったら「こども家庭庁」へ意見をぶつけて、彼らのリアクションをSNSを通じて促す方が、
より良い未来に繋がると思うのは私だけでしょうか?
小学1年生から20代の方であれば、だれでも、いつでも登録できます!
子育て支援は、超高齢社会となった日本において、与党の支持層である高齢者に直接的な恩恵が少なく、
政策推進が難しいという構造的な問題があるのは理解できます。
しかし、少子化という国家的な危機に直面している今、目先の票勘定ではなく、
長期的な視点に立った政策推進が不可欠です。
今回のキユーピーの件は、まさにその日本の政策解決能力の限界を示しているように感じます。
企業の経営判断であるとはいえ、ベビーフードが子育て世代にとっての「社会インフラ」としての側面を持つことを考えれば、責任官庁である「こども家庭庁」が、ただ静観しているだけでは済まされないはずです。
2025/9/7 追記 キユーピーは成長市場として介護職を選択
少子化の進展で離乳食市場は大変小さく、成長する見込みはありません。
しかも苦労して確保した顧客である「赤ちゃん」は、数年すれば成長し、ベビーフードは無用となります。
その代わりにキユーピーが注力を決定したのが「介護食」です。



平均余命は男性81.09歳、女性は87.13歳であり、女性は世界1位を維持しているそうです。
「人生100年時代」というのは、女性に限っては、大袈裟ではないですね。
「大好きだったあのメニューのおいしさが楽しめる」がシリーズのコンセプト。
介護食は一旦ファンを獲得できれば、ベビーフードよりも遥かに長い期間、購入頂ける期待ができます。
しかも日本の政治は老人には手厚く、子育て世代よりも遥かにリッチな高齢者の方が多いですから、
良いものを作れば儲かる下地がある、食品業界にとっては宝の山なのです。
これは営利追求の宿命を背負った民間企業としては、当然の選択と言わざるを得ません。
残念ながらキユーピーがベビーフード事業から退場するのは動かしがたい事実として受け止めましょう。
求められるのは「実効性ある政策」と「当事者意識」
「こども家庭庁」には、国民の不信感を払拭し、真に子どもと家庭のための政策を推進していくことが求められます。
- 具体的な成果と迅速な情報発信: 「絵に描いた餅」ではない、実効性のある政策を立案し、その成果を国民にわかりやすく、迅速に伝える努力が必要です。
- 現場の声への傾聴と当事者意識: 実際に子育てをしている親や子どもの声に耳を傾け、それを政策に反映させる姿勢が不可欠です。
- 省庁間の連携強化と司令塔機能の発揮: 子どもに関する政策を多角的に捉え、関係省庁との連携を強化し、真の「司令塔」として機能することが求められます。
今回のキユーピーのベビーフード撤退問題は、「こども家庭庁」にとって、その存在意義が問われる試金石となるでしょう。
この問題にどう向き合い、どのような解決策を提示できるのか。多くの親たちが、政府の動きに注視していることを関係者の方は意識して欲しいと思います。
このブログ記事で、皆様の共感を呼ぶことができれば幸いです。
皆さんのご意見をどうぞコメント欄よりお聞かせください。




繰り返しになりますが、
これは一企業では手に負えない深刻な事態で、
政治の出番だと私は思います。
\資産運用、そろそろ始めてみませんか?/








![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4aed0273.2b4c8c5b.4aed0274.6f547284/?me_id=1420298&item_id=10009555&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkusuriaoki-r-2%2Fcabinet%2Fgazo125%2F4901577088414_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4aed0659.c4515da0.4aed065a.87ba5136/?me_id=1307506&item_id=10120466&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbeisia%2Fcabinet%2F05912159%2F13222.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a323ae0.ca93ff37.4a323ae1.ca5306bd/?me_id=1428756&item_id=10001031&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchummys%2Fcabinet%2F10780283%2Fcompass1746929783.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

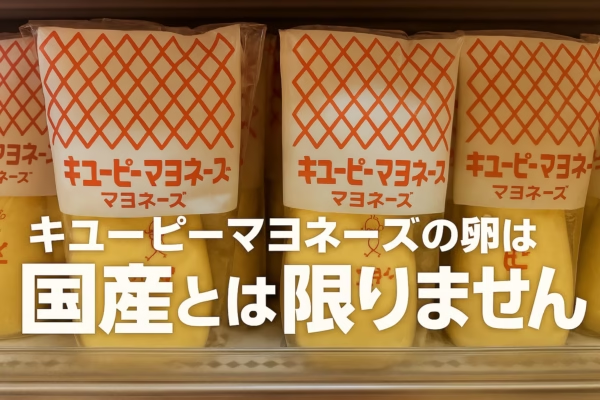



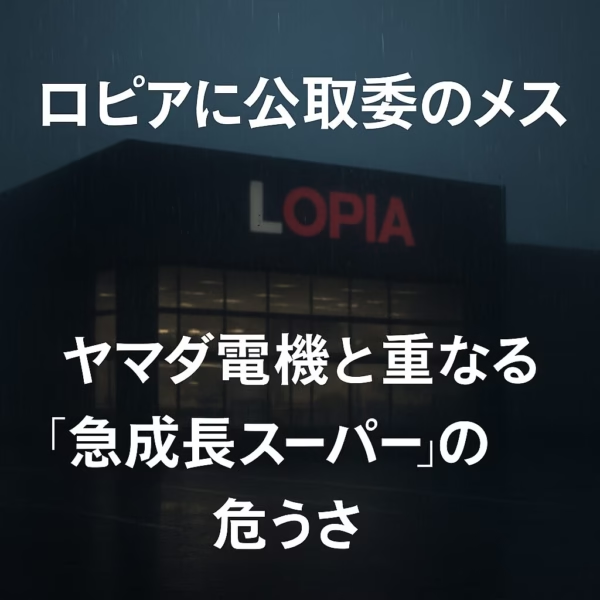
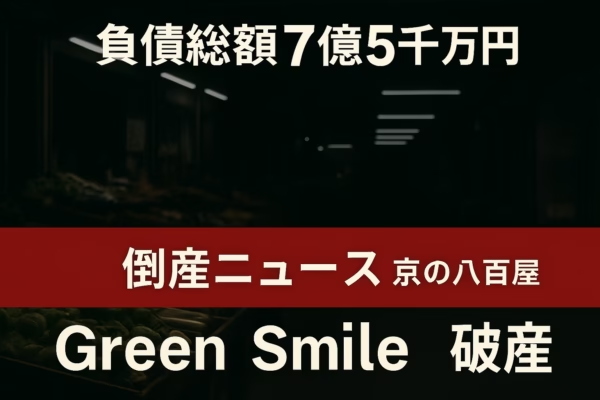
コメント