作家の山本周五郎が記者時代に牧野博士へインタビューした際、「雑草」という言葉を口にしたところ、「世の中に雑草という草はない。どんな草にも、ちゃんと名前がついている」と諭されたそうです。
朝ドラ「らんまん」の主人公にもなり、日本の植物分類学の礎を築いた彼の名は、今や教科書にも記されるほど広く知られています。しかし、その人生が決して順風満帆ではなかったことは、意外と知られていません。本書『雑草という草はない』は、そんな牧野博士の歩みを、写真や図版を交えて紹介する一冊です。
図書館でこの本を手に取った瞬間、私は思わず「おおっ」と声を漏らしました。A4判の大型カラー図鑑のような装丁で、手描きの植物図や直筆資料の写真がふんだんに収められています。ページをめくるたびに浮かび上がるのは、草木への深い愛情と、学問に対する妥協なき覚悟を併せ持った一人の人物の姿でした。
本記事では、植物と真摯に向き合い続けた男・牧野富太郎の人生をひもとき、その学問への姿勢から、現代を生きる私たちが学べることを探っていきます。
家族を失って、植物と出会う
牧野富太郎は、1862年、高知の裕福な商家に生まれました。家業は酒造と雑貨業を営んでおり、幼少期は物心ともに恵まれていたように思えます。しかし、彼の人生は早くも厳しい現実に直面することになります。
わずか3歳で父を、5歳で母を、6歳で祖父を次々に亡くし、兄弟姉妹もいなかった牧野少年は、祖母の手によって大切に育てられました。彼自身、「父母の顔を覚えていない」と語っており、その言葉からは孤独な幼少期の面影がうかがえます。
しかし、彼にはもう一つの“家族”がありました。それが、身の回りに咲き誇る草木たちです。
美しい花々や、季節ごとに色づく木々──それらは、彼にとって遊び相手であり、学びの師であり、何より心の支えでした。牧野は自然の中で学んだのではなく、「植物と遊んだ」と語っています。
それはまさに、「好きに理由はいらない」という純粋な感情の発露。その感覚こそが、後年の研究姿勢にも通じる、彼の学びの原点だったのです。
学問への覚悟──『赭鞭一撻』の15ヵ条
自然を相手に遊ぶように植物と向き合ってきた牧野富太郎は、二十歳の頃に植物学を志すにあたり、「赭鞭一撻(しゃべんいったつ)」と題した十五ヵ条の勉強心得を自らに課しました。
「赭鞭」とは、古代中国の伝説上の帝王・神農が手にしていたという赤い鞭のこと。薬草を見極めるための象徴として語られるこの名をあえて冠し、「一撻」──つまり、自らを律し、鞭打ってでも達成すべき心得として掲げたのです。
この心得は、他人に向けた教訓ではなく、あくまで己の心を律するための戒めでした。そこに並んでいたのは、真摯な学びの姿勢であり、言い換えれば「年齢に関係なく、すべての人が先生である」ということを示しています。
実は、私が以前勤務していた会社の「社訓」は「万象皆師」というものでした。周りのすべての人や物事が先生であるという理念は、まさに牧野の考えと通じるものです。信頼できる人、時には反面教師──さまざまな出会いがありましたが、それらは間違いなく私の成長に欠かせない要素でした。そのため、彼の生きざまには大いに共感を覚えます。
“植物と遊ぶ”と語っていた青年が、自らを律する「覚悟の書」を記した──そこには、好きなことを生涯の仕事にするためには、遊び心と同じくらいの自制心が必要だという、若き日の牧野の決意がにじんでいます。
薬草から世界へ──書物と知識への尽きぬ欲
牧野富太郎の植物への興味は、身近な草花だけにとどまりませんでした。特に、薬草としての利用を目的に記された古書への関心は、彼の知的好奇心を大きく刺激したようです。
そのきっかけの一つとなったのが、知人の医師の家にあった『本草綱目啓蒙』という江戸時代の薬草書です。小野蘭山が著したこの書物は、植物を分類しつつ、薬効などを詳しく記したもの。牧野はこの書を写本の形で借り受け、繰り返し読み込むうちに、やがて自分の手元に置きたいと願うようになり、書物の購入へと動き始めます。
しかし、彼の探究は薬草に限られませんでした。オランダの植物学書には、シーボルトによって西洋にもたらされた日本由来の植物が掲載されており、それらを見た牧野は「大変懐かしい」と深い関心を寄せます。日本の植物が異なる文化の視点でどのように記述されているのか──それを見つめ直すという知的な試みも込められていました。
牧野は、「学び」とは単なる知識の蓄積ではなく、自らの世界を広げるための“扉”であると考えていたのかもしれません。漢方から洋書まで、あらゆる書にあたり、分け隔てなく植物を「知りたい」と願う。その真摯さこそが、後の大著『日本植物志図篇』や『牧野日本植物図鑑』へと結実していく礎となったのでしょう。
描いて、解剖して、図鑑にする──完璧を求めた植物画家
植物学において、観察と記録は車の両輪のようなものです。牧野富太郎は、スケッチを単なる画での記録ではなく、学問の根幹として位置づけていました。まずは対象とする植物が“標準的な個体”かどうかを見極め、鮮度を保ったまま自宅に持ち帰り、徹底的に観察。そのうえで、多角的にスケッチを施す──彼の描く植物画には、そうした入念な準備と観察が凝縮されていました。
当時は保冷剤もビニール袋もない時代。牧野はガラス張りの「生かし箱」を自作し、植物の鮮度を保つために工夫を凝らしていました。帰宅後は、解剖用ナイフと低倍率の顕微鏡を駆使し、花の構造や葉の付き方を詳細に記録、このようにスケッチは単なる写生ではなく、科学的観察の集積として完成させていったのです。
しかし、彼の執念はスケッチのみにとどまりませんでした。それをどう図鑑に掲載するか──レイアウト、構成、文章表現に至るまで、細部にわたって介入し、納得するまで修正を重ねました。朝ドラ『らんまん』でも描かれたその姿勢は、まさに「妥協なき完璧主義」ですね。
植物を描き、解剖し、記述し、出版する。この一連の営みは、科学者・観察者・編集者・画家としての牧野富太郎の全人格が注がれた営為であったからこそ、今日まで読み継がれる図鑑群の背後にある、執念の結晶といえるでしょう。
学術を超えて生き続ける名前たち──分類と命名の旅
牧野富太郎の研究の核心は、植物を「名づける」ことにありました。彼は一生のうちに約1500種の植物を命名しました(※1)。名づけるという行為は、単なるラベリングではなく、その植物の「居場所」を世界の植物体系の中に与える行為です。
植物学者にとって命名とは、発見した喜びの証であると同時に、責任ある分類者としての覚悟が問われる営みです。新種であれ既知種であれ、既存の分類体系の中でその位置を見極め、属や科の定義に照らし合わせて学名を与える。しかもその名が、後世まで使われ続けることになるのです。
これは、言葉を持たない植物たちに“言葉”を与える営みでもあります。例えば「ヤマトグサ」──この植物は、1889年に牧野が大久保三郎とともに日本人として初めて命名・発表した新種であり、学名「Theligonum japonicum Okubo et Makino」として記録されています(※2)。のちに和名として「ヤマトグサ」と呼ばれるようになったこの植物は、彼の植物学者としての出発点を象徴する存在です。
分類・命名のためには、膨大な既存文献を渉猟し、同定を慎重に行う必要がありました。スケッチ、標本の採取、観察──すべてが「正しい名を与える」ための手段だったのです。そして一つひとつの植物に「あなたは何者か?」と問い続ける日々の積み重ねが、やがて『牧野日本植物図鑑』という金字塔につながっていきます。
名前とは、記録であり、記憶であり、敬意でもあります。牧野の名づけた植物たちは、今も研究者や自然愛好家たちの手に触れられ、口にされ、語られています。その名とともに生き続けるのは、まぎれもなく牧野富太郎の思索と情熱そのものなのです。
※1 出典:BOTANIST Journal「世界が驚いた天才植物学者・牧野富太郎ってどんな人?」https://journal.botanistofficial.com/lifestyle/4931/
※2 出典:高知県立図書館オーテピア常設展示「植物分類学の父 牧野富太郎」https://otepia.kochi.jp/science/zone/84.html
【まとめ】“雑草という草はない”という眼差し
本書のタイトルにもなっている「雑草という草はない」という言葉は、牧野富太郎の植物に対する根源的な姿勢を象徴しています。この言葉の背景には、分類学者としての厳密なまなざしと、自然を慈しむ温かなまなざしが同居しています。
学問とは、細分化し、整理し、ラベルを貼っていく作業である一方で、それによって見落とされがちな「個の命」をすくい取る営みでもあります。牧野はその両方を兼ね備えた稀有な存在だったと言えるでしょう。
事実、彼が収集した標本16万点は百年の年月を超えて「牧野標本館」にて大切に保管されており、その研究価値が年々高まっています。この百年で絶滅してしまった植物が残されており、その遺伝子解析にも活用されています。この技術の進歩にはさすがの牧野博士も驚いていることでしょうね。
“好き”を突き詰め、“学び”に変え、そして“名づける”ことで植物の命を記録にとどめた人。その姿は、私たちが日常の中で見過ごしがちな草花や足元の自然に、あらためて目を向けるきっかけを与えてくれます。
牧野富太郎の歩みから学べるのは、ただの植物知識ではなく、「ものの見方」そのものなのかもしれません。
 パンチです
パンチですきれいな植物図鑑を観ながら
牧野富太郎の人生を振り返る
すごく素敵な本でしたよ!




お薦めの本がまた増えました!
皆さんの感想も聞かせて下さいね
👉https://www.makoto-lifecare.com/
📱この記事をスマホでも読みたい方へ
お使いのスマートフォンで以下のQRコードを読み取って、通勤中や週末にも気軽にアクセスできます。
PCで読んで「これは保存しておきたい!」と思った方は、ぜひご活用ください。


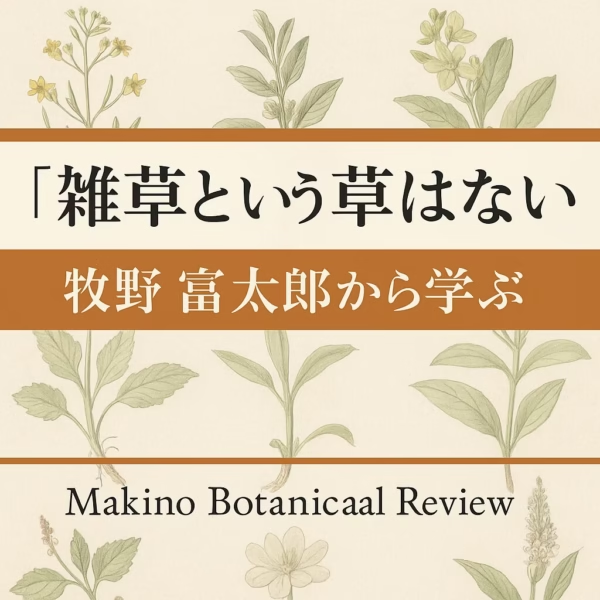
コメント