農業協同組合新聞(JAcom)が報じたところによると、
「生乳価格の上昇に伴う牛乳の値上げ」が消費の減少を引き起こしているとのことです。

店頭から1リットルで200円以下の安価な牛乳が姿を消し、一部の商品は300円に迫る勢いです。
一方で、消費者からは「ホクレン経由の牛乳は高すぎる」といった声が上がり、
比較的安価な加工乳へと消費がシフトする傾向が見られます。
関係者は「牛乳は生活必需品」と訴えますが、消費者側は、どのように考えているのでしょうか?
今回の値上げを機に消費者の「牛乳離れ」が加速してしまうと、
我が国の未来において、国産の酪農業の存続は難しいものとなるでしょう。




どうぞ最後までご覧くださいね
牛乳価格の値上げに対する「不信感」を払拭には何が必要?
今回の値上げに伴う消費減退、その一つの理由として
「ホクレン系統の牛乳が値上げに際して十分な説明を行われなかったこと」
があるのではないでしょうか?
この結果、消費者の間に「一方的な値上げ」という不信感を生み、それが牛乳離れの一因となったのであれば、
この状況を打開することが必要です。
具体的には、以下の取り組みを通じて消費者の信頼を積み重ねることが不可欠です。
- 価格の透明化: ウェブサイトやSNSで、生産者への支払い価格、流通コスト、加工費などの内訳を公開し、値上げの理由をデータに基づき明確に説明する。
- 対話の場の創出: SNSでの質疑応答や、リアルイベントでの試飲会などを通じて、消費者の疑問や意見に直接耳を傾け、双方向のコミュニケーションを築く。
既に取り組んでいるものもあるかも知れませんが、結果的に消費者に広く深く伝わっていたのでしょうか?
それを問い直すラストチャンスが、今なのかもしれません。
ホクレン組織のあり方を問う「段階的プロセス」
しかし、それでも消費者の支持が得られない場合、
それは「単なるコミュニケーションの問題ではない」と真摯に受け止めるべきです。
ホクレンが取るべき道は、組織のあり方を根本から問い直すという、段階的かつ覚悟を伴うプロセスでしょう。
系統外のMMJなどの牛乳とホクレンの牛乳では1リットル当たり100円の違いがある点について
この理由を「品質や安定供給体制の確保・維持のため」というような
上っ面の説明で納得してくれる消費者は少ないと思います。
長年培ってきた流通システムやコスト構造、そして組織文化そのものを見直すことは、多くの抵抗を伴うでしょう。
業界内のモラル低下に伴い、目先の利益確保のために不祥事に走るリスクも否定できません。
しかし、組織改革なくしては
「消費者ひとり一人が日本の酪農を支えよう」
という機運が消費者から出て来ることは考えにくいと思いませんか?
日本の酪農の未来に向けた「ラストチャンス」
日本の酪農が生き残るためには、これまでのやり方を見直し、覚悟を持って新たな道へ踏み出す必要があるのではないでしょうか?
第一に、既存の事業を支えるための「付加価値」を追求することです。
若年層にはSNSを活用した情報発信でブランド価値を伝え、高齢者層には試飲会などの対面イベントで安心感を醸成する。
例えば牧場での搾乳体験やバター作りといった「体験型商品」は、消費者に酪農の価値を体感的に理解してもらう上で、強力な武器となります。
これが単なる酪農家個人が企画・運営するイベントではなく、収益を生み出すビジネスモデルとして一般的になったらどうでしょうか?
この結果、消費者が「あの牛乳ならば高くても買いたい」と思える理由を創出できる可能性が少しずつ高まると思います。
第二に、新たな市場を開拓することです。
例えば航空業界のファーストクラスが選ばれるのと同様に、
コップ一杯で1,000円でも飲みたい・買いたいといった超高付加価値な牛乳を積極的に生産・販売し、
富裕層・インバウンド向けのホテルやレストラン、高級老人ホームといった特定のルートに供給する体制づくりなどはどうでしょうか?
この方策は収益構造を安定させ、ひいては一般的な牛乳の価格設定の柔軟性を高めることにつながります。
これらの取り組みは、短期的な利益を追求するのではなく、
日本の酪農業がこれから迎える人口減少時代を生き抜くための、
まさに「ラストチャンス」と捉えるべきです。
飼料販売店、酪農機器メーカー、獣医師、そして牛乳運送業者などの周辺産業が廃業・撤退してしまったら
日本の酪農業が2度と復活する日が来なくなるのは明白です。
業界関係者の皆さんがこの危機をチャンスと捉え、勇気を持って変革に挑むことを心から期待します。




最後までご覧いただき有難うございました


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b722bb4.5a4cd0d4.4b722bb5.08de129d/?me_id=1287627&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fnakahora-bokujou%2Fdev-mall%2Fassets%2Fimg%2Fproducts%2F24_10002_W_SQ.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


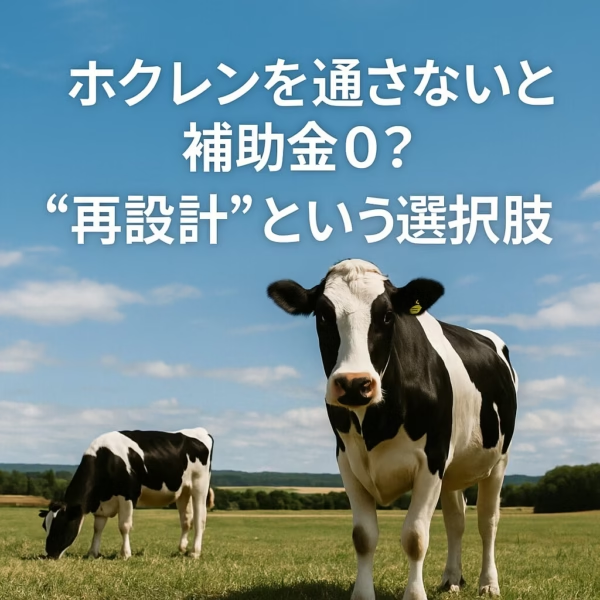
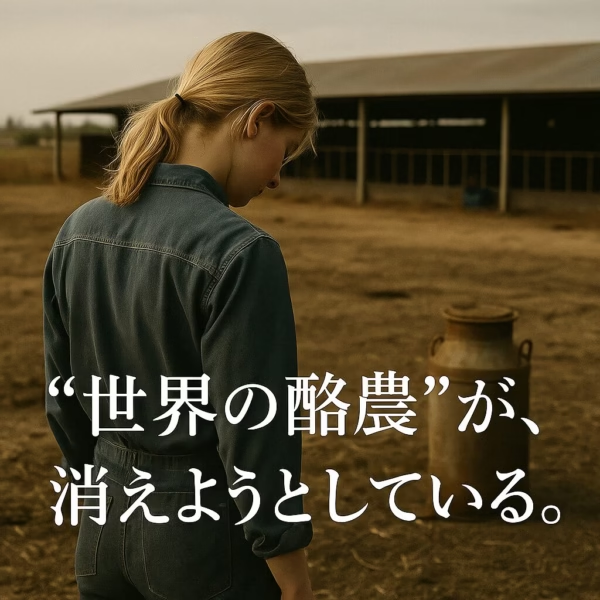
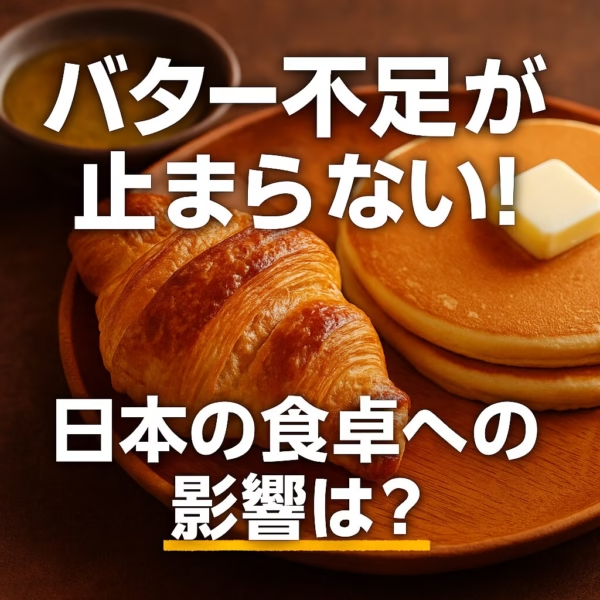
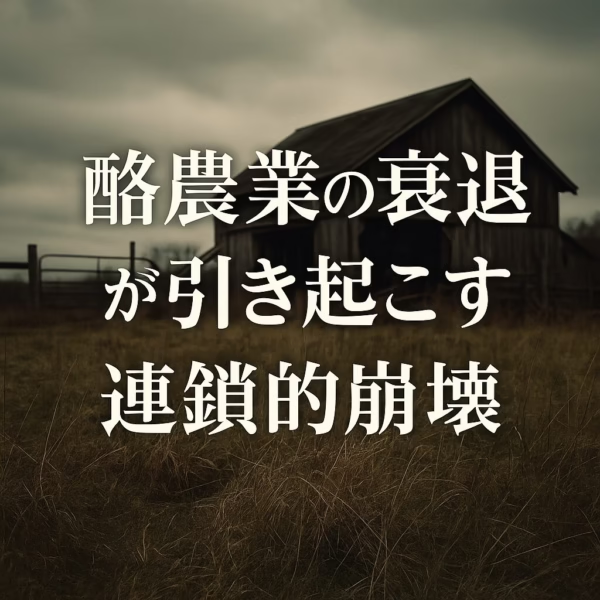

コメント