日本の飲食店は、創業から3年以内に約半数が廃業するとも言われています。
そんな中、「ただめしを食べさせる」という一風変わった食堂が、10年近く黒字で続いています。
ですが、誤解しないでください。
“ただめし”はこの店の目的ではなく、あくまで理想を続けるための手段にすぎません。
本当にやりたかったのは、「あなたのためだけに用意する一皿」――
そんな“誂え(あつらえ)”のおもてなしを、現実の経営として成立させることでした。
理想を掲げるのは簡単です。
それを10年続けるには、どれほどの工夫と覚悟が必要なのか。
飲食店を始めたい方、経営に悩む方、
そして飲食業で働くすべての人に読んでほしい、ある一冊をご紹介します。
 パンチです
パンチです最後まで楽しんで下さいね
筆者のご紹介
まずは、未来食堂の創業者であり本書の著者でもある小林せかいさんの経歴をご紹介します。
学歴・職歴
- 東京工業大学 理学部 数学科 卒業
- 日本IBMにエンジニアとして入社
- クックパッドに転職し、エンジニアとして6年半勤務
飲食業界への転身
IT企業を退職後、1年4ヶ月にわたり大戸屋やサイゼリヤなどで修行を重ね、
2015年9月、東京都千代田区一ツ橋に「未来食堂」をオープン。
受賞歴
- 「日経WOMAN」ウーマン・オブ・ザ・イヤー2017
小林せかいさんは、エンジニアとしてのキャリアを持ちながら飲食業界に転身し、成功を収めた異色の経営者です。
中学生の頃から「いつか自分のお店を持ちたい」という夢を持ち続け、現実のものにされた方でもあります。
開業までのプロセスを自身のブログでも詳細に公開しており、その中には印象的な記事も多くあります。
中でも個人的に強く印象に残っているのが、こちらの記事:
『“サイゼリヤ”という名のスポーツ』
サイゼリヤでのアルバイト経験を通じて、一人のスタッフが複数工程をこなす“属人性の排除されたオペレーション”をまるでスポーツのように分析された内容で、
エンジニア出身ならではの視点と、現場での体験が融合した非常に興味深い記事ですのでご覧くださいね。
👉”サイゼリヤ”という名のスポーツ – 未来食堂日記(飲食店開業日記)
未来食堂は、独自のコンセプトと仕掛けによって多くのメディアでも取り上げられ、日経WOMANの受賞をはじめ、高い注目を集めています。
将来、自分も経営者にという夢をお持ちの学生さん全員がこの視点でアルバイトに臨めたら、日本はもっと面白くなるのでは?と思わされました。
著者をご存知の方も多いかと思いますが、その根底にある“理想を貫く力”を、これからご紹介する本書を通じて改めて感じていただければと思います。
本書のご紹介
未来食堂の経営者であり本書の著者でもある小林せかいさんは、独自のアイデンティティと発信力を持つ経営者です。
彼女は、事業を始める前からこう語っていました。
「自分たちが未来食堂を成功させることで、このシステムの浸透を図る」
つまり、ただお店を経営するのではなく、“社会に仕組みを残すこと”までを視野に入れた挑戦だったのです。
「真似されることを恐れない」という姿勢も象徴的です。
実際、彼女はブログで月次の売上・売上原価・売上総利益といった詳細な経営データを惜しみなく公開しています。
「この熱い思いをみんなに伝えたい!」というエネルギーが、ページの行間からにじみ出ているように感じます。私自身、かつて農家を個人経営していた経験があります。現在は廃業していますが、その経験の一部は当ブログでも紹介しています。
小林さんは今も現役で、「追いつかれるプレッシャーこそが、新しい価値を生む」と語っています。
このマインドセットには、多くの経営者が学ぶべきものがあると強く感じます。
ちなみに、本書のタイトルにもなっている「ただめし」は、未来食堂の本質ではありません。
本当にやりたかったのは、お客さま一人ひとりのために、その場で料理を“誂える”――そんなオーダーメイドのおもてなしを実現し続けること。
しかし、それを現実の経営として成立させるには、人件費を抑えつつ、来客数を安定的に確保する必要があります。
その課題を解決する手段として生まれたのが、「ただめし」でした。
宣伝費や人件費の代替となる戦略として機能し、理想を貫くために練られた、実に戦略的な一手だったのです。
本書を手に取られる前に、ぜひ未来食堂の公式ホームページもご覧になってみてください。
小林せかいさんの魅力は、徹底的に準備された設計力と、状況に応じて戦術を柔軟に切り替える判断力の両立にあります。
そこに人が集まる理由があるのだと、きっと感じていただけるはずです。
飲食店ビジネスで成功したい方には、本書はまさに“理想の貫き方”の教科書とも言える一冊です。
冒頭でお伝えした「創業3年以内で50%が廃業」という現実を、
理念を曲げずに越えてきた軌跡が、ここには詰まっています。
まとめ
小林せかいさんは、「“ただめし”のようなセーフティーネットは、使われないのが一番嬉しい」と語っています。
それでもあえてこの仕組みを導入したのは、“繋ぐべき理想を実現する”ためでした。
この“救い”のシステムによって、小林さんの思いはより多くの人に届き、共感され、静かに広がっていきました。
「最も大切なのは、未来食堂のDNAが受け継がれていくこと」
これは、小林さん自身の言葉です。
驚くべきは、これだけの仕組みを完成させながらも、2号店も、チェーン展開も、あえて選ばなかったという点。
その背景にあるのは、“広げる”ことよりも、“貫く”こと、“残す”ことを大切にする姿勢です。
その覚悟と選択に触れるには、やはり本書を実際に読んでみていただくのが一番です。
これから起業を考えている方にとっては、「目から鱗がボロボロこぼれ落ちる」ような気づきがあるかもしれません。
ネタバレなしで本書の魅力を語るのは、正直このあたりが限界です。
このレビューが、あなた自身の“理想を貫く”挑戦のきっかけになれば、こんなに嬉しいことはありません。




最後までご覧いただき、ありがとうございました。




起業を考えている学生の方や
経営者の方にも
お薦めの一冊ですよ!
📱この記事をスマホでも読みたい方へ
お使いのスマートフォンで以下のQRコードを読み取って、通勤中や週末にも気軽にアクセスできます。
PCで読んで「これは保存しておきたい!」と思った方は、ぜひご活用ください。

-



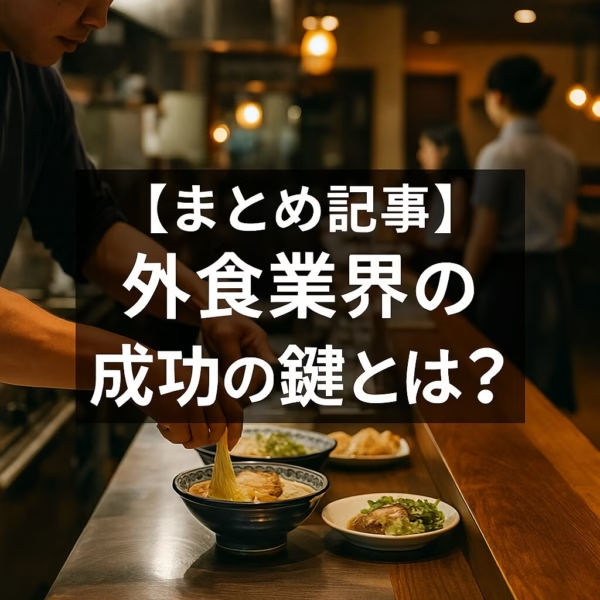
【まとめ記事】丸亀製麺・牧のうどん・すかいらーく・未来食堂・吉野家──外食業界の成功の鍵とは?
「従業員の幸せなくしてKANDOは生まれない」という理想を掲げながら、その実現に苦戦する企業も少なくない現代の外食関連産業。 一方で、厳しい環境下でも独自の戦略で… -



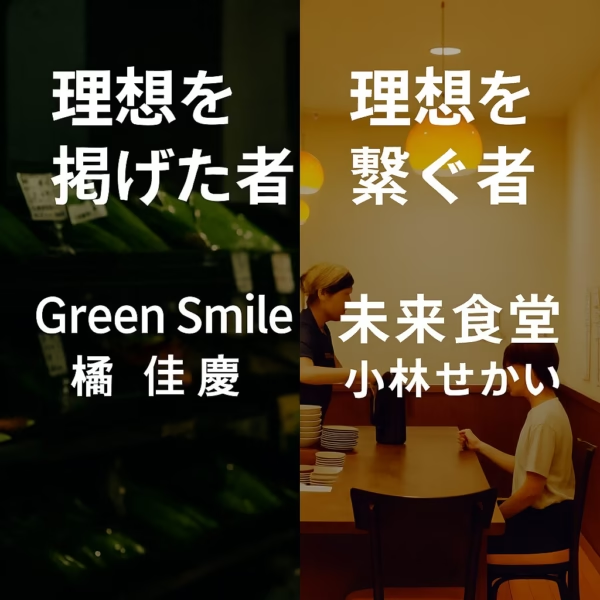
“理想を掲げた者”と“理想を繋ぐ者”──Green Smile 橘佳慶と未来食堂 小林せかい
「ただめしを食べさせる食堂」として注目を集め、10年近く黒字経営を続けている未来食堂。一方、デザイン性とコンセプトで話題を呼んだ「日本一カッコいい、未来の八百… -




JAの暗闇(農協の闇)と賢く付き合う方法:書籍レビュー『農協の闇(くらやみ)』
書籍『農協の闇(くらやみ)』で明かされた問題点を基に、農業者として安心してJAを活用する方法を提案します。

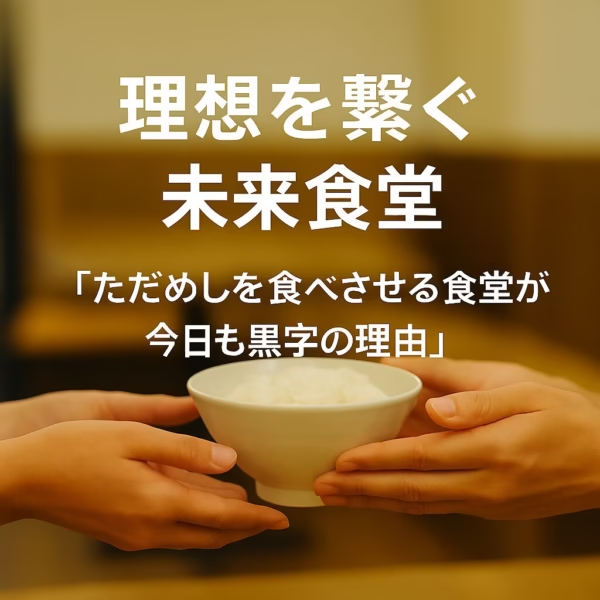
コメント