1915年創業の老舗で、製菓材料の卸売を手掛けていた(株)サクライが2025年7月30日付で、
東京地裁に破産を申請したと東京商工リサーチが伝えました。
負債総額は約34億5千万円とも73億円とも伝えられている異例な状況となってます。
実は日本の老舗企業の数、創業が明治維新前という企業だけでも3,654社にのぼります。
長年の歴史で培われた信用力は、企業の強みとして知られ、
「老舗だから大丈夫だろう」という信頼感は、
金融機関からの融資においても有利に働いてきました。
しかし、その「老舗神話」が崩壊しつつあるという現実が、
最新のデータやニュースから浮き彫りになってきているのです。




どうぞ最後までご覧ください
「お金の教養講座」のご紹介です
\まずは無料セミナー受講から、始めてみませんか?/




受講生満足度98.7%の講義を
体験してみてくださいネ
過去最多水準に迫る老舗企業の倒産
帝国データバンクの調査によると、2024年の老舗企業の倒産件数、
過去10年間で最も多かった2019年と並ぶ高水準で推移しています。
\帝国データバンクの分析レポートはこちらです!/
この背景には、コロナ禍からの経済回復期に中小企業を苦しめる様々な要因が挙げられます。
物価高によるコスト上昇、深刻な後継者不足に加え、
金融機関から返済猶予(リスケジュール)を受けても経営改善が進まなかった
「返済猶予後倒産」が増加しています。
金融機関は老舗企業に対しても財務状況や事業実態をより厳しくチェックする姿勢を確実に強めているのです。
老舗企業 サクライ破産の背景とは?
この厳しい環境下で、衝撃的なニュースが報じられました。
製菓材料の卸売を手掛けていた創業100年以上の老舗企業、(株)サクライが破産を申請したのです。
長年にわたり一定の事業規模を維持していた同社でしたが、
東京商工リサーチによると、「決算書に粉飾決算の疑い」が生じ、信用が失墜。
結果として一部金融機関が融資姿勢を厳しくしたことが、事業継続を困難にさせ、倒産につながりました。
この事例は、たとえ長年の付き合いがある老舗であっても、
「粉飾」という不正行為を金融機関として許さない
という明確なメッセージとなりました。
ゼロゼロ融資終了が追い打ち
この一連の動きに追い打ちをかけているのが、
コロナ禍で実施された実質無利子・無担保の「ゼロゼロ融資」の返済本格化です。
これまで多額の借入金で経営を維持していた企業は、
今、自社の利益だけで返済を続けていく必要があります。
このタイミングで、金融機関が「老舗だから」という理由で安易な融資を続けることは、
不良債権を抱えるリスクに直結します。
もはや、過去の付き合いや見せかけの安定は通用しない時代になったのです。
まとめ:老舗企業がサクライ破産から学ぶべきこととは?
この厳しい時代を乗り越えるために、老舗企業は以下の3つの変革を真剣に考える必要があります。
財務の透明化: どんぶり勘定をやめ、会計士や税理士と連携して正確な経営状況を把握すること。
事業の再構築: 時代に合った新しいビジネスモデルや販路を模索し、収益性を高めること。
円滑な事業承継: 後継者問題を先送りせず、計画的に事業を引き継ぐ準備を進めること。
このような「企業の転生事例」、私の趣味であるお茶の業界から
「丸三三原商店(長野県安曇野市)」の華麗な転身を紹介させていただきます。
同社は明治7年(1874年)に創業した、元々は製茶卸業でしたが、
その老舗が今では「胡蝶庵」というブランドを立ち上げ、抹茶スイーツや和カフェを展開しました。
菓子店はコロナ禍の影響だけではなく、日本人のライフスタイルの変化により苦戦する企業が多いなか、
「胡蝶庵」は地方企業ながら伝統ある京都や東京の和菓子の名店を抑え、
楽天市場でNo.1の快挙を成し遂げたのです。
以上のことから、令和の現代においては表面的な「老舗」という看板ではなく、
本質的な経営体質の強さが、企業の存続を左右する時代となったと言えるようです。
顧客ニーズや販売チャネルの変化などに柔軟に対応することが求められますが、それに先立って、
これまでの悪しき慣習を断ち切り、
新たな時代に適応する勇気を持つ。
それこそが未来への生き残りの最低条件となるのでは、と私は考えます。




最後までご覧いただき有難うございました
\資産運用、そろそろ始めてみませんか?/







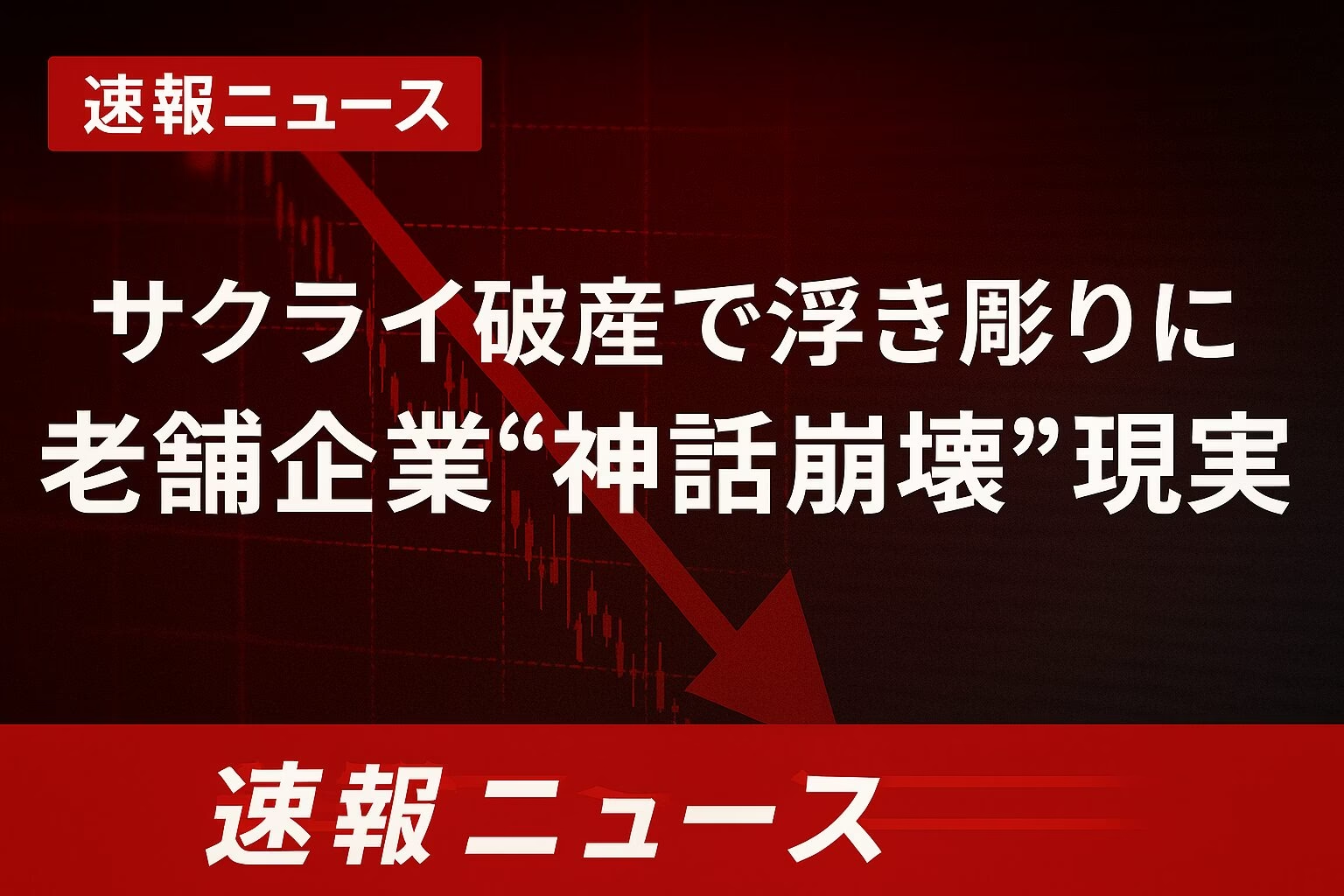

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/40f9c3c4.2935f677.40f9c3c6.1534fbe3/?me_id=1199392&item_id=10000354&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkochouan%2Fcabinet%2Ftorodaiset%2Fshiawase_rakuten5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

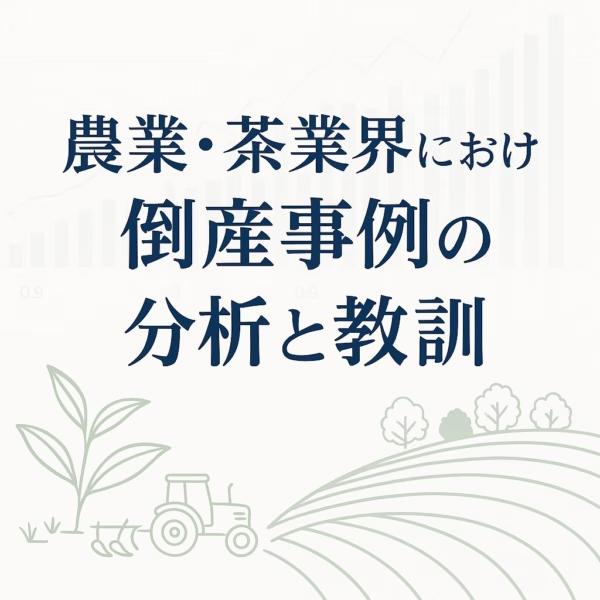


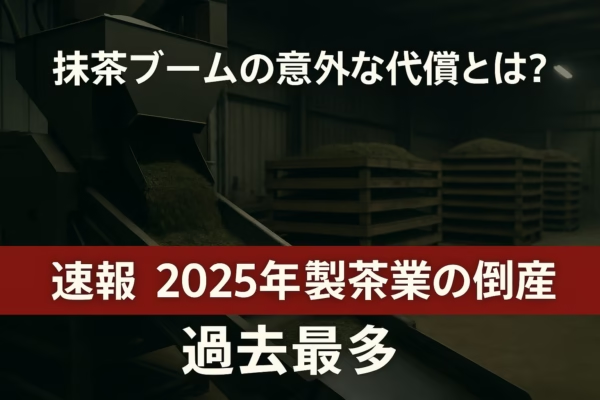
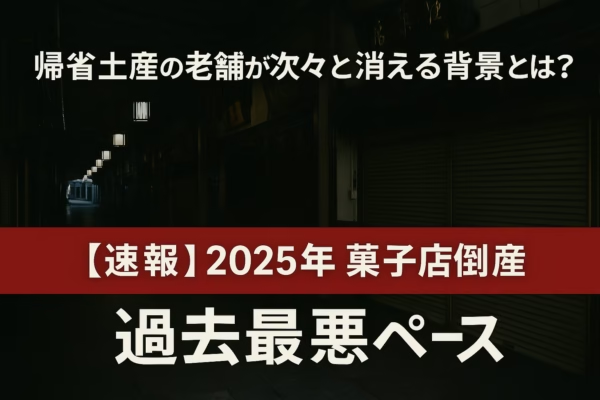

コメント