「うちの会社、副業禁止なんだよ!」
こう言って転職や収入の多様化のチャンスを、自ら手放してしまう人が少なくありません。でも、それって本当に“絶対に守るべき規則”ではないのをご存知でしょうか?
現代の日本では、すでに終身雇用も年功序列も崩壊しています。
それなのに、給料は上がらず、物価は上がるばかり。
そんな中で、生活や将来の安心を支える選択肢の一つが、副業による収入の確保です。
実際、趣味で始めた副業ブログがきっかけで、いつの間にかプロのライターとして独立を目指す人も出てきています。
それなのに、「うちの会社は禁止だから…」と何の疑問もなく従い、皆さんの可能性を自ら閉ざしてしまうのは、あまりにももったいないと思いませんか?
このページでは、YouTuber リベ大両学長の動画を参考に、「副業禁止」の壁にどう向き合えばいいのかを、法律・税金・職場のリアルな対処法を交えながら、わかりやすく解説していきます。
「バカ正直に縛られてチャンスを逃す」のではなく、「迷惑をかけずに、うまくやる」ための知識を、ぜひ一緒に学んでいきましょう。
📘 会社の就業規則 vs. 個人の職業選択の自由
多くの企業では、就業規則にこんな文言があります。
第○条:従業員は、会社の許可なく他の会社等の業務に従事してはならない。
一見すると「副業は禁止されている」と読み取れます。しかし、これに法的拘束力があるのかどうかは、もう少し掘り下げて考える必要があります。
労働基準法の立場
労働基準法第2条第2項にはこうあります。
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
つまり、「就業規則は守ってね」と明記されており、これだけを見ると副業禁止規定にも従う義務があるように見えます。
でも、憲法はもっと強い
ここで登場するのが、日本国憲法第22条。
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
つまり、「他人に迷惑をかけない限り、職業を選ぶのは個人の自由ですよ」と国家が認めているわけです。そして、憲法はすべての法律よりも上位にある“国の最高法規”です。
じゃあ、副業は自由なのか?
結論から言えば、副業そのものが「公共の福祉に反する」ものでなければ、本質的には禁止されるべきものではありません。
例えば、
- 勤務時間中に副業をして本業に支障が出る
- 競業行為で会社に損害を与える
こうしたケースは別ですが、「土日にブログを書く」「平日の夜に翻訳業をする」や「SNSでのインフルエンサー活動」など、本業に支障をきたさない副業であれば、憲法の観点からはむしろ保護されるべき行動なのです。
まずは「どうやればできるか」を考える視点を
副業禁止だから無理、と最初から諦めるのではなく、
「どうすれば本業に支障なく、副業を成立させられるか」
を考える視点を持つことが、これからの時代では重要です。特に終身雇用や年功序列が崩れつつある今、「複数の収入源を持つ」ことは、個人のリスク管理でもあり、生存戦略でもあります。
⚖️ 副業禁止の「ウソ」と「ホント」──国はもう副業を認めている!
「うちの会社、副業禁止だから…」
そう言ってチャレンジを諦めてしまうのは、もったいない話です。
実は国(厚生労働省)ですら、副業を認める方向に明確に舵を切っているのをご存知でしょうか?
厚生労働省の動きは「副業容認」です
平成30年1月、厚生労働省はモデル就業規則から「副業禁止規定」を削除しました。
これは国として、「副業を一律に禁止するのはもう時代遅れ」と判断したという、明確なメッセージです。
さらに厚労省が公開している『副業・兼業の促進に関するガイドライン』には、こう記載されています:
労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由。
各企業においてこれを制限できるのは以下のような場合に限られる。
副業が制限されるのは、こんなときだけ
副業が問題になるのは、以下のような明確なリスクがある場合に限られます。
✅ 労務提供に支障がある場合
・副業で夜更かしして本業に遅刻、ミスを連発
・就業時間中に副業(スマホで操作など)を行う
✅ 守秘義務や情報漏えい
・会社の内部情報や機密を副業に利用
・顧客情報、社内資料などを副業に流用
✅ 競業・利益相反
・自社の競合企業で副業する
・副業が自社ビジネスの市場や信用を侵害する
✅ 会社の信用・ブランドを傷つける行為
・法的・倫理的に問題のある副業(アダルト業、違法販売など)
・SNSで「○○社の社員がこんな副業やってる」と炎上リスクがある行為
つまり、「普通にまじめにやってる副業」は大丈夫!
- 本業に支障が出ない
- 社内情報を使っていない
- 会社のライバルではない
- 世間的に問題のある仕事じゃない
これらを守っていれば、「副業している」という理由だけで法的に処罰されたり、懲戒されることは原則としてありません。
📜 実際の裁判の判例について
副業が就業規則で禁止されている場合でも、実際の裁判では「本業への支障がないか」「企業秩序を乱していないか」といった実質的な影響が重視されます。以下に、就業規則に反して副業を行っていたものの、会社に迷惑をかけていないと判断された主な判例をご紹介します。
👉引用元:ベリーベスト法律事務所
1. 私立大学教授の語学学校兼職事件(東京地裁 平成20年12月5日判決)
- 概要:私立大学の教授が、大学の許可を得ずに語学学校の講師や通訳の副業を行っていた。大学はこれを理由に懲戒解雇とした。
- 裁判所の判断:副業は主に夜間や休日に行われており、本業の講義に支障を来していないことから、懲戒解雇は無効とされた。
引用元:ベリーベスト法律事務所
2. タクシー運転手のアルバイト事件(広島地裁 昭和59年12月18日決定)
- 概要:隔日勤務のタクシー運転手が、非番日に月7〜8回、輸出車の船積み作業のアルバイトをしていた。会社はこれを理由に解雇した。
- 裁判所の判断:労務提供に支障が生じておらず、他の従業員も同様の副業を行っていたことから、解雇は過酷すぎるとして無効とされた。
引用元:厚生労働省
3. マーケティング会社部長代理の副業事件(東京地裁 平成30年9月27日判決)
- 概要:年俸1,200万円の部長代理が、副業禁止規定に違反して副業を行っていたとして解雇された。
- 裁判所の判断:副業が本業に支障を与えていないことから、解雇は不当とされ、会社に約2,200万円の支払いが命じられた。
引用元:企業法務に強い弁護士への相談は大阪「咲くやこの花法律事務所」へ
4. 別会社の代表取締役就任事件(東京高裁 平成31年3月28日判決)
- 概要:従業員が在職中に別会社の代表取締役に就任し、多額の役員報酬を得ていたことを理由に解雇された。
- 裁判所の判断:本業への支障が認められなかったため、解雇は不当とされ、会社に約2,700万円の支払いが命じられた。
引用元:企業法務に強い弁護士への相談は大阪「咲くやこの花法律事務所」へ
判例からのポイント
- 就業時間外の副業は原則自由:労働者が就業時間外に行う活動は基本的に自由であり、会社が全面的に禁止することは合理性を欠くとされています。
- 副業禁止規定の合理性:副業禁止規定は、労務提供に支障がある場合や企業秩序を乱す場合など、特別な事情がある場合に限り合理性が認められます。
- 懲戒解雇の有効性:副業が本業に具体的な支障を与えていない場合、懲戒解雇は無効と判断される傾向があります。
引用元:厚生労働省
副業を検討する際の注意点
- 就業規則の確認:副業に関する規定を事前に確認し、必要に応じて会社の許可を得るようにしましょう。
- 本業への影響を避ける:副業が本業に支障を与えないよう、労働時間や業務内容に注意を払いましょう。
- 企業秘密の保護:副業で得た情報が本業の企業秘密と関係しないよう、情報管理に留意しましょう。
「教科書的」には、副業を行う際は、これらのポイントを踏まえて慎重に判断することが重要です。
🧠「副業OK」は法的に正しくても、絶対に口外しないこと!
副業が法律的に認められていても、実際の職場では別問題です。
- 「あいつは副業やってるから残業しない」
- 「副業のせいで仕事のミスが多いんじゃないか」
そんな難癖・やっかみ・足の引っ張り合いに巻き込まれるリスクは、想像以上にあります。
だから、結論はシンプルです。
「うまくやりましょう」= 要するに バレないようにやる
法的に問題がないことと、会社に副業を公言すべきかどうかはまったく別の話です。
特に副業に理解のない会社や、昭和的な空気の職場なら…
「言わぬが華」&「口は災いの元」です。
引用元:リベ大両学長動画「副業禁止 どう乗り越えるより」
副業は“後ろめたさ”ではなく“粋”の精神で静かにやりましょう。
本業にもプラスをもたらすものだとしても、それを声高にアピールする必要はありません。
【要注意】副業がバレる2大ルート
1. 税金(住民税)経由
副業収入が増えれば、当然住民税も増えます。
会社の給与額に見合わない住民税額になってしまうと、経理担当に「あれっ?」と思われてバレます。
➤ 対処法:住民税は「普通徴収」に!
確定申告書のこの欄を見てください。
給与・公的年金等以外の所得にかかる住民税の徴収方法
→【自分で納付(普通徴収)】にチェック!
これで、副業収入にかかる住民税は会社経由ではなく自分で払うことになり、会社には通知されません。
2. 自分の“うっかり口”
実はバレる原因の大半は自爆です。
- 「俺、副業で稼いでるから会社なんてどーでもいい」系のマウンティング
- 「今月、副業収入が本業を超えたんだよね」系のうっかり自慢
- 「こんなスキル、どこで学んだの?」と聞かれて、つい「副業で…」と答えてしまう
口は災いの元。成功すればするほど口が軽くなるのが人間の性。
ぐっとこらえて、黙って静かに稼ぎましょう。
副業は“知恵”と“沈黙”で守れ
- 法律的なリスクはすでにクリアされている
- それでも現場には「空気」という最大の敵がある
- 税と口に注意して、粛々と副収入を構築しよう
「バレなければいい」という乱暴な話ではなく、「余計な対立や誤解を生まないために沈黙を選ぶ」という処世術として、副業は慎重に運営する。
これが、令和の会社員に求められる“美しい副業マナー”です。
最後に──副業を「できない理由」ではなく「できる方法」を考えよう
大事なのは、
「禁止されてるからダメだ」ではなく、
「どうやったら本業に迷惑をかけずにできるか」を考えることです。
引用元:パンチさん(このブログの筆者、私です)
社会全体が「副業(複業)」や「副収入(複収入)」を当たり前とする時代に入った今こそ、個人が自分のスキルや時間をどう活かすかが問われています。
その結果、皆さんが経済的な自由を手に入れて後悔のない人生を過ごすことができるだけではなく、皆さんの副業での創作活動で他の誰かの笑顔を生み出す切っ掛けとなるかも知れません。
会社と戦う必要はありません。
仕事は仕事で一生懸命、そして副業では好きなことを思いっきりやる。
仮に上司や同僚から「副業やってる人のこと、どう思う?」なんて投げかけられたとしても
「私は会社の仕事だけでヘロヘロで、週末は家でひたすら寝てますよ」なんて答えてたら良いんですよ!
皆さんの周りに就活や転職活動で悩んでいらっしゃる方がいたら、是非この動画を紹介してあげてくださいね。
ところでこの動画の中で両学長が言ってた「最大の副業バレ対策」についてお知らせします。
「一生懸命、本業に取り組んで、職場の仲間を思いやりながら働くこと」だそうです。
一人でも多くの皆さんにこの素敵な両学長のメッセージが届き、自由な働き方と副業の可能性に気づく人が増えれば――それは、きっとこの社会全体にとっても大きな前進になるはずです。
 パンチです
パンチです就業規則が絶対ではないんですよ!
上手に楽しく副業やってみましょう。
口外しないようにだけ気をつけてね




「今月は副業でガッツリ稼いだからご馳走するよ!」
なんて職場の女の子誘うのもNGですからね💛
📱この記事をスマホでも読みたい方へ
お使いのスマートフォンで以下のQRコードを読み取って、通勤中や週末にも気軽にアクセスできます。
PCで読んで「これは保存しておきたい!」と思った方は、ぜひご活用ください。


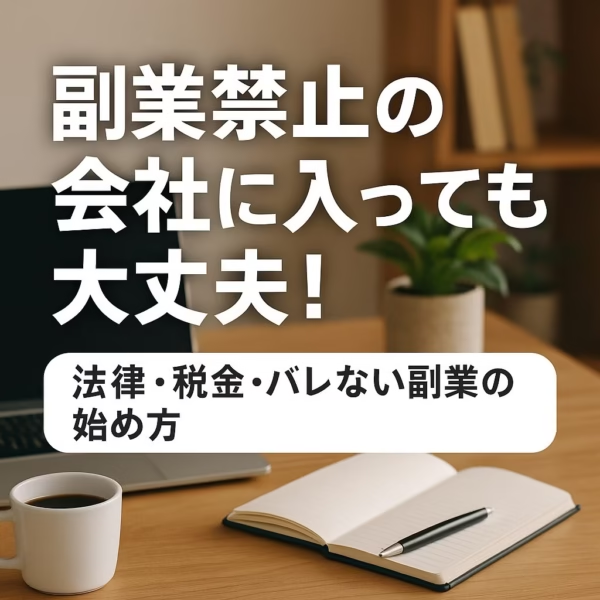
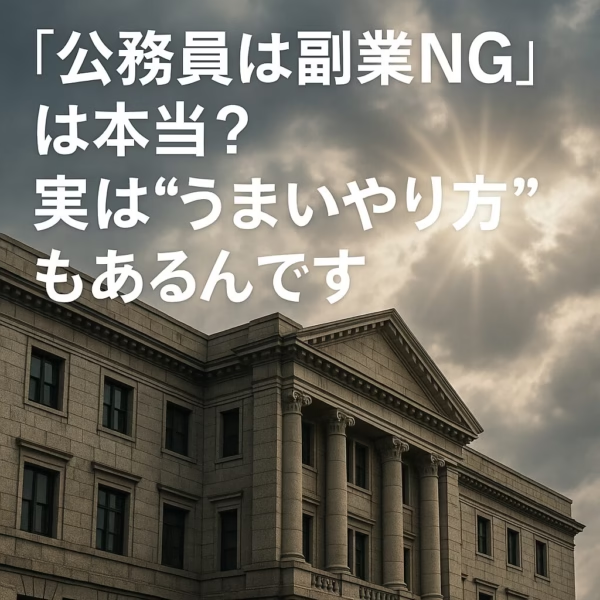
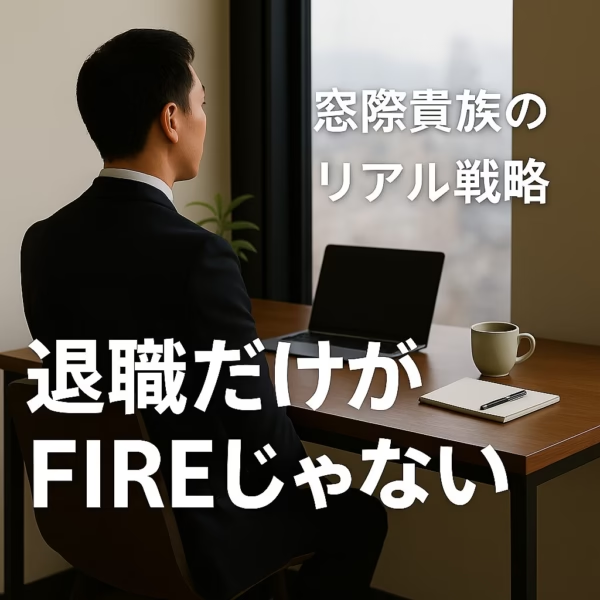
コメント