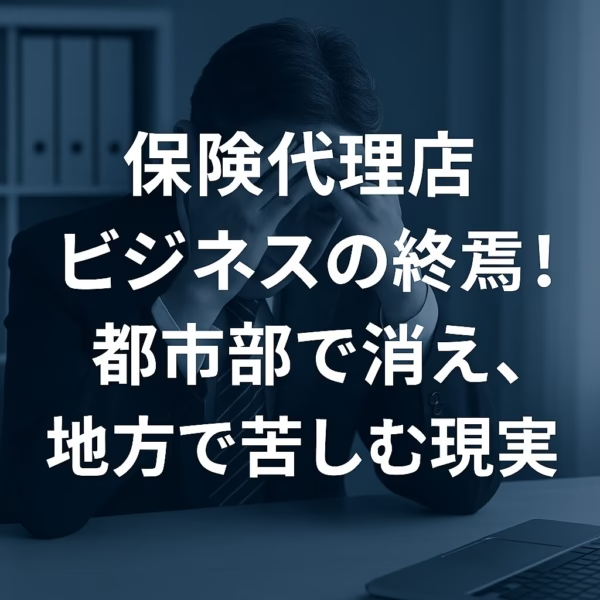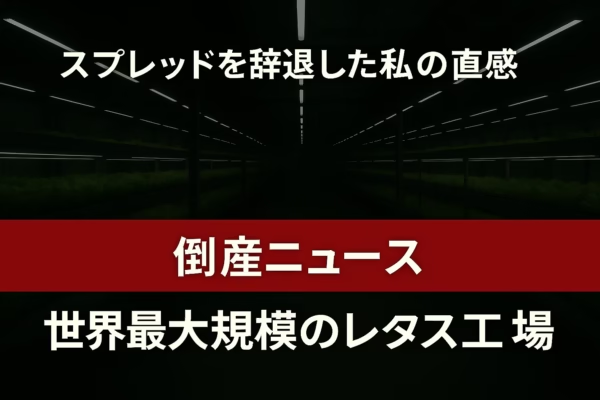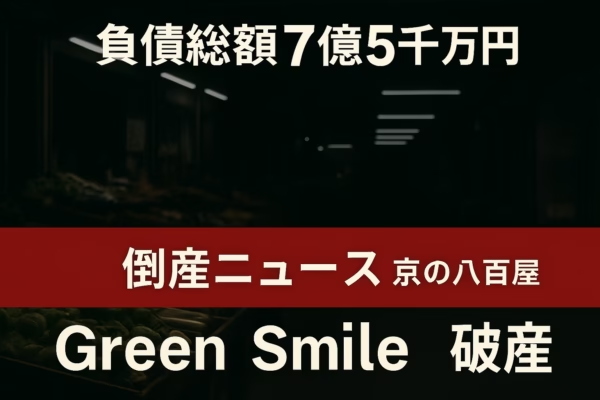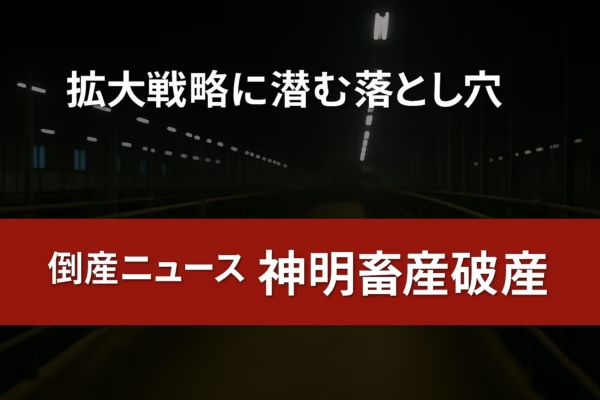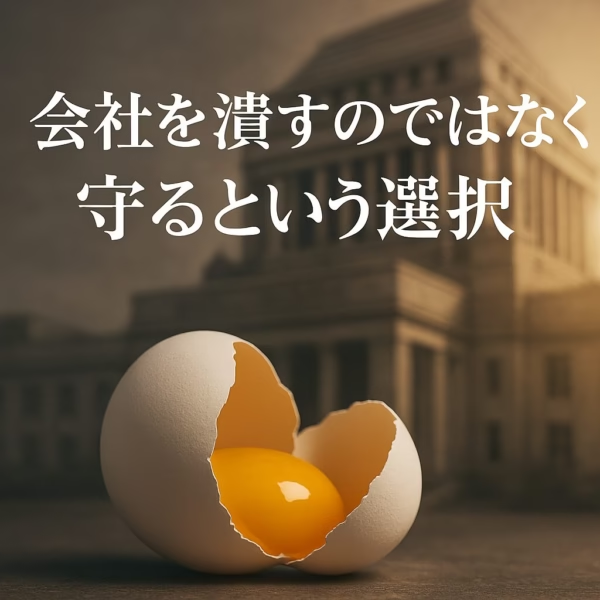倒産– tag –
-

保険代理店ビジネスの終焉!都市部で消え、地方で苦しむ現実
生命保険会社本体では、例えば第一生命が新卒社員に月給33万5,560円を提示し、社員1人あたり約15万円相当の自社株を配布するなど、業界の大盤振る舞いが話題となっています。 それとは対照的に、厳しい現実に直面しているのが 「生命保険代理店」です。 現在、代理店ビジネスは都市部でも地方でも深刻な苦境に立たされ、存続の危機に瀕しています。 その背景には、都市部と地方で異なる構造的な問題が潜んでいます。本記事では、その詳細と現場の実態について徹底解説していきます。 都市部で消えゆく代理店、地方で苦しむ代理店 生命保険代理店を取り巻く環境は、大きな変化を迎えています。 都市部では、保険のネットビジネスが急速に拡大し、従来の対面営業スタイルの代理店は次々に... -

世界最大規模のレタス工場倒産|スプレッドを辞退した私の直感
「世界最大規模、1日10トンのレタスを生産できる工場」 世界中の空腹に苦しむ人々を食糧危機から救うかも知れない そんな期待を背負っていた野菜工場のトップランナー『スプレッド』は 2024年8月26日に民事再生法の適用を申請、 1年近くを経て2025年4月にその手続きが完了しました。 実は私、この会社から「営業責任者」としてのポジションを提案されたのですが、 最終面接を前に辞退する決断を下しました。 その理由は、企業側から理念や事業計画を聞く中で 「野菜工場のビジネスモデルに未来はない」という確信を得たからです。 ✔ この記事でわかること ▶ 「スプレッド」の破綻に至るまでのビジネスモデルの限界と経営課題 ▶ 野菜工場ビジネスにおける、農業経験者から見た“現実的な... -

パン業界の現状と今後 明暗を分ける「選ばれる理由」とは?
✔ この記事でわかること ▶ 米価格高騰によるパン業界への影響と、パン屋倒産件数が減少した背景 ▶ 「選ばれ続けるパン屋」と「消えゆくパン屋」の違いと、具体的な成功事例・失敗事例 ▶ ベーグルなど新たな健康志向トレンドと、消費者が今後パンを選ぶポイント 2024年から2025年にかけて「コメ不足による価格高騰」が問題となったことで、 消費者の間でパンの相対的な「割安感」が広がりました。 この影響でパン屋の倒産件数は2025年1-4月に半分に減少したと東京商工リサーチが報告しています。 しかし、この倒産件数の減少は、経営危機に陥っていたパン屋にとって 一時的な「延命措置」があったためであり、 今後は楽観できないと私は見ています。 事実、2025年8月には新潟県長岡市で... -

電力会社と野菜工場:スプレッドとプランツラボラトリーの「明」と「暗」
植物工場の成功例と課題について考察し、未来の農業の可能性を探る内容です。 -

京の八百屋「菜珠(さいじゅ)」を運営、日本一カッコいい Green Smileが破産
-

なぜ神明畜産は破綻したのか?拡大戦略に潜む落とし穴
✔ この記事でわかること ▶ 神明畜産が経営破綻に至った背景と拡大戦略のリスク ▶ 畜産業界に共通する“拡大路線”の危うさと持続可能性の課題 ▶ 今後の畜産業界に必要な「守りの視点」とリスク分散戦略 畜産業界において『大規模化』と『効率化』を追求する企業が増える中、 リスクを過小評価した結果、経営破綻に追い込まれるケースが増加しています。 神明畜産の事例はその典型であり、拡大戦略が招いた深刻な結果を浮き彫りにしました。 神明畜産は、豚熱の発生により約5万6,000頭の豚を殺処分し、 資金繰りの悪化を招きました。 最終的に2022年9月には民事再生法を申請しましたが、 その過程には多くのリスクが潜んでいました。 この記事では、神明畜産の倒産の背景やリスク管理の重... -

453億円の巨額負債 イセ食品の再建はなぜ成功したのか?
✔ この記事でわかること ▶ イセ食品はなぜ破綻し、どう再建したのか──“たまご&カンパニー”誕生までの経緯と背景 ▶ なぜ金融機関は本気で支援に動いたのか──卵業界・流通への影響と社会的意義 ▶ “誇れる仕事”をした金融マンたち──理想と現実に揺れる金融業界へのメッセージ 「イセ食品は倒産後、どう再建したのか?」 「スポンサー企業はどこだったのか?」 「なぜSMBCをはじめとする金融機関がこれほど本気で動いたのか?」 ——この記事では、2022年に会社更生法の適用を申請し破綻したイセ食品が、 わずか2年で再建に至った背景を、 多くの元銀行員と交流してきた筆者の視点から掘り下げます。 金融の現場で理想と現実とのギャップに揺れる若い方々へのメッセージとしても、 ぜひ読ん... -

負債総額4億円超 仙台 壽三色最中本舗の自己破産 和菓子文化に未来は?
「白松がモナカ」や「萩の月」―仙台の街を歩けば目にするこれらの看板には、 仙台が長い歴史の中で築いてきた和菓子文化の豊かさが詰まっていますね。 その一方で、近年は時代の変化や消費者の嗜好の多様化によって、 老舗和菓子店が厳しい経営環境に直面するケースも増えています。 先日、地元で愛され続けた「壽三色最中本舗」、 2025年4月23日に自己破産を申請したというニュースがありました。 東京商工リサーチによると、2022年3月期時点の負債総額は約4億7500万円ということです。 この出来事は、仙台が誇る和菓子文化を未来へ継承するために何が必要なのか、 改めて考えるきっかけとなります。 この記事では、 壽三色最中本舗の歴史と経緯、 仙台に根付く和菓子文化の背景、 そ... -

街の洋菓子店の厳しい現状-不二家の販売戦略から学ぶ生き残りのヒント
近年、日本全国で洋菓子店が次々とその歴史を閉じるというニュースが後を絶ちません。帝国データバンクによると、2024年度には洋菓子店の倒産が過去最多を記録し、その数は「51件」に達しました。その背景には、原材料価格の高騰や消費者の買い控え、さらにはコンビニスイーツとの競争が存在します。 一方で、老舗の洋菓子ブランド「不二家」は積極的な戦略を展開し、この厳しい状況を乗り越えるために努力を重ねています。 今回は、街の洋菓子店が直面している問題点と、不二家の事例から学べる生存のヒントについて考えてみたいと思います。 街の洋菓子店が直面する苦境 原材料価格の高騰 小麦粉や砂糖、バター、鶏卵などの価格が軒並み上昇。特にチョコレートケーキの原価はここ5年... -

愛媛 華月グループの破産と生花関連業界の現状と将来
2025年3月18日、生花販売を手掛ける愛媛県宇和島市の華月グループが、負債総額約4億6000万円で破産手続き開始を決定しました。 「華月」は2007年の設立以来、冠婚葬祭施設やホテル、学校などに販路を築き、ピーク時には年商約7000万円を誇っていました。 また、系列企業として「葉月」が菊栽培を担当し、「千華」が生花の配送業務を担うなど、生産から販売までの一貫した体制を構築していました。 しかし、新型コロナウイルスの影響で冠婚葬祭の規模が縮小し、イベントや行事の自粛による受注の激減が業績に大打撃を与えました。 コロナ収束後も回復は思うように進まず、さらに先行投資の負担が重くのしかかり、最終的に事業継続が困難となりました。 このケースは、生花産業が深いかか...