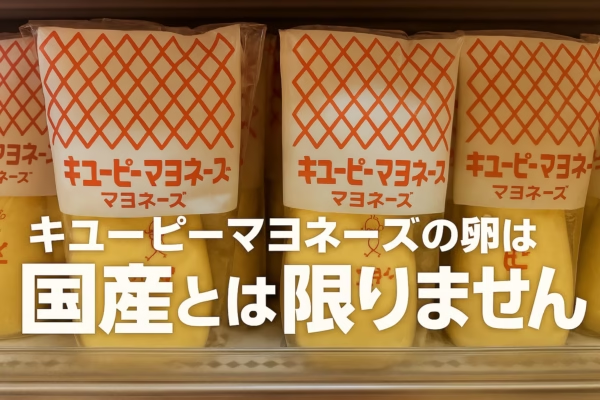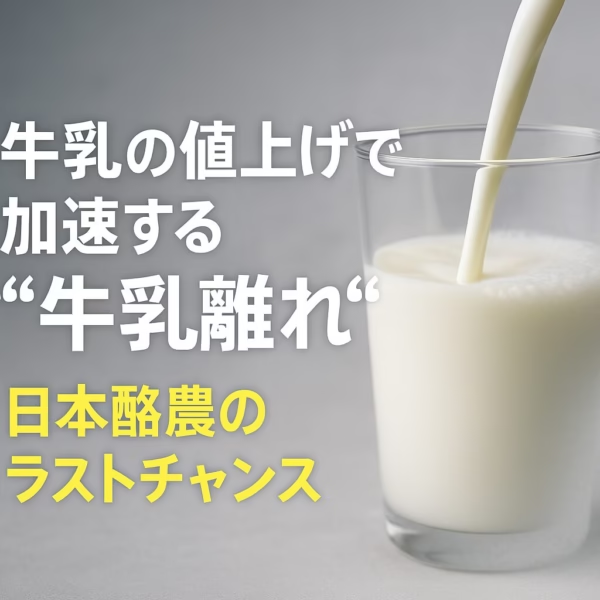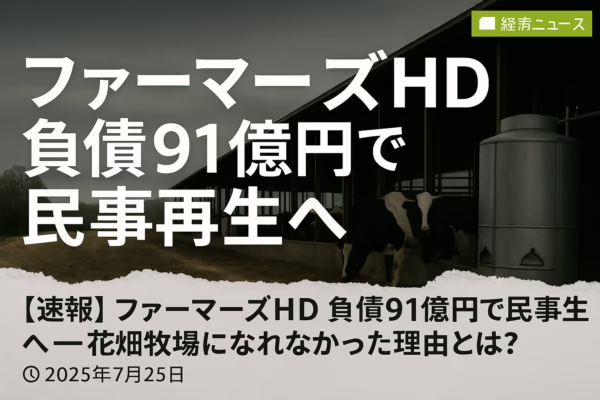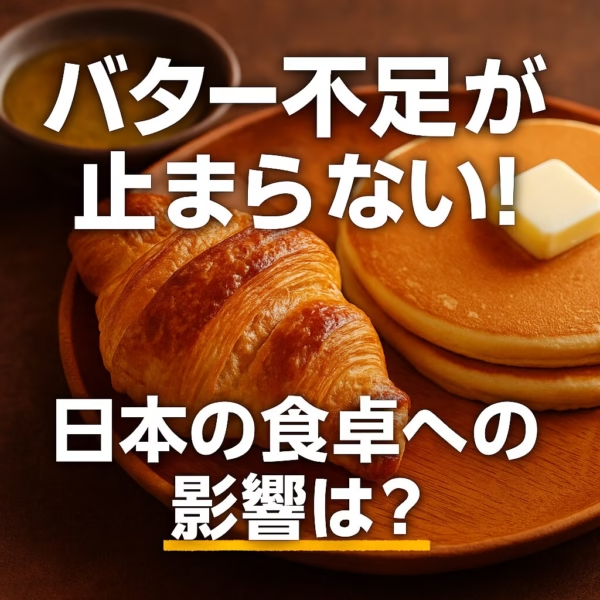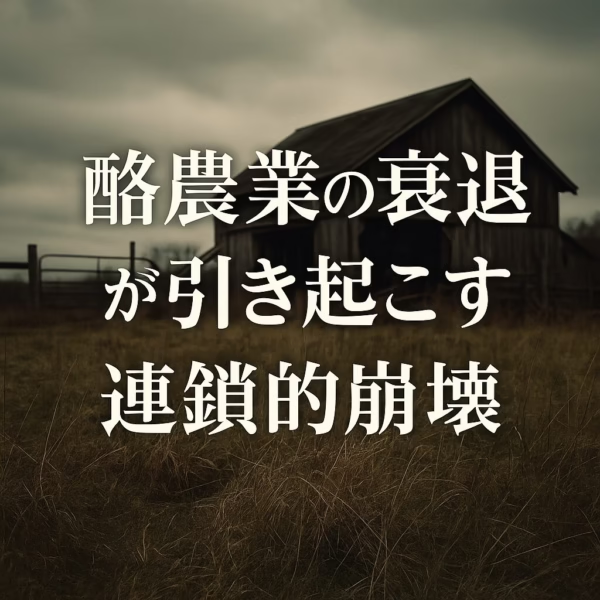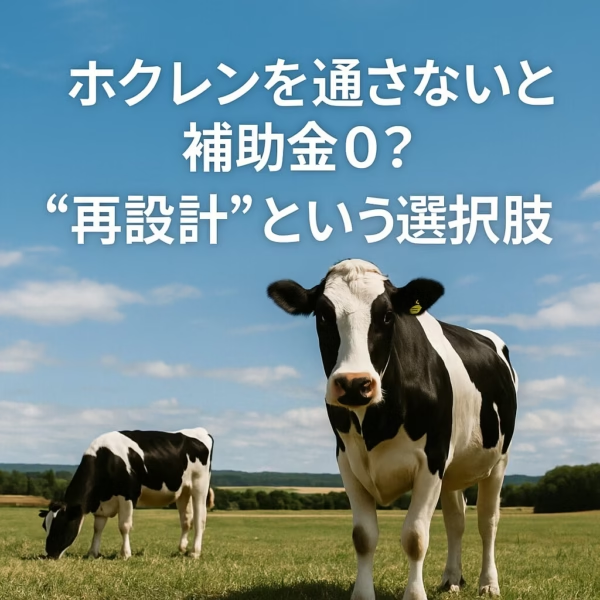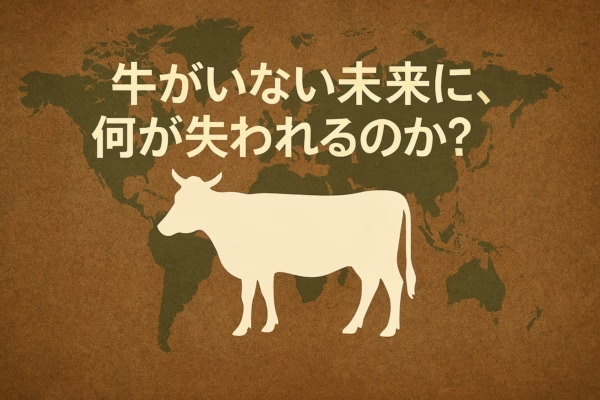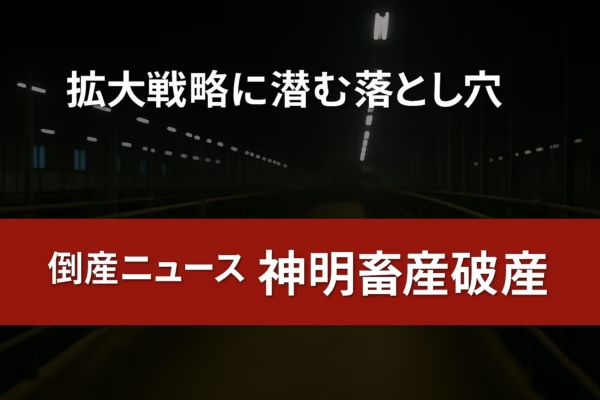酪農・畜産– tag –
-

実は…キユーピーマヨネーズの卵は国産とは限りません──鳥インフルが揺るがす日本の食卓
テレビCMで流れる映像を見てると、私たちが日ごろ愛用しているマヨネーズは 「とれたての新鮮な国産卵だけで作られている」 という、そんなイメージを抱いていませんか? しかし現実には、必ずしもそうとは限りません。 たとえば定番のキユーピーマヨネーズ。 原材料は「卵黄」とだけ表示されており、ライバルメーカーの表示とは少し異なっているのです。 引用元:キユーピーマヨネーズ公式ホームページ 引用元:味の素公式ホームページ 実際、品質確保のために国産卵が多く使われている一方で、 将来的に輸入卵を使う可能性も否定されておらず、一部業務用には既に使用されています。 なぜ、世界有数の鶏卵生産国である日本が、わざわざ輸入に頼らなければならないのでしょうか? その... -

牛乳価格の値上げで加速する”牛乳離れ”──日本酪農のラストチャンス
農業協同組合新聞(JAcom)が報じたところによると、 「生乳価格の上昇に伴う牛乳の値上げ」が消費の減少を引き起こしているとのことです。 店頭から1リットルで200円以下の安価な牛乳が姿を消し、一部の商品は300円に迫る勢いです。 一方で、消費者からは「ホクレン経由の牛乳は高すぎる」といった声が上がり、 比較的安価な加工乳へと消費がシフトする傾向が見られます。 関係者は「牛乳は生活必需品」と訴えますが、消費者側は、どのように考えているのでしょうか? 今回の値上げを機に消費者の「牛乳離れ」が加速してしまうと、 我が国の未来において、国産の酪農業の存続は難しいものとなるでしょう。 どうぞ最後までご覧くださいね 牛乳価格の値上げに対する「不信感」を払拭には... -

【速報】ファーマーズHD 負債91億円で民事再生へ──花畑牧場になれなかった理由とは?
こちらはGoogleでは見つけることが出来ない Microsoft Bing限定公開のブログです! (一部記事を除きます) ✔ この記事でわかること ▶ ファーマーズHDが民事再生法を申請した理由 ▶ 「IoT化酪農」と現場のギャップ ▶ 日本の酪農業が抱える構造的な問題 岡山県倉敷市を拠点とする大手酪農グループであった ファーマーズホールディングス株式会社(以下 ファーマーズHD)が、 2025年7月24日、関連会社11社とともに民事再生法の適用を申請しました。 負債総額は約91億円にも上ると報じられており、同グループ会社の2024年6月期の連結売上58億円の1.5倍に上ります。 日本の酪農業のモデルケースだった同社の失敗は、業界全体が直面する厳しい現実を浮き彫りにしています。 実は私、この会... -

バター不足が止まらない!気候変動・人手不足・需要爆増──日本の食卓への影響は?
こちらはGoogleでは見つけることが出来ない Microsoft Bing限定公開のブログです! (一部記事を除きます) 今回の主役は芳醇な香りで私たちを魅了する「バター」です。 2025年7月初旬、欧州を襲った記録的な猛暑は、実は私たちの食卓にも暗い影を落とし始めています。 ロイター通信によると、熱波に伴いフランスやイタリア、スペインで少なくと8人が死亡し、ギリシャやトルコなどでは山火事が発生。スイスでは冷却に利用される河川水温の上昇により、原子炉が停止と社会生活に大きな影響が出ています。 一見、遠い国の話に思えるかもしれませんが、世界的にバターの供給が逼迫し、今後その状況がさらに厳しくなる見込みであることが、複数の報道や専門家の分析から浮き彫りになって... -

群馬の酪農家、10年で半減──酪農業の衰退が引き起こす連鎖的崩壊
群馬県の酪農業がここ10年で半減したという残念なニュースが届きました。急速な減少により地域経済への影響が心配されます。 -

ホクレンを通さないと補助金ゼロ?酪農制度の“再設計”という選択肢
「ホクレンに出さないと補助金がもらえない」──そんな話を聞いたことはありませんか?北海道の酪農家が抱える“自由なはずの出荷”と“縛られた制度”の矛盾。年間売上5,000万円でも赤字に苦しみ、廃業へ追い込まれる現実。本記事では、補助金の仕組み、ホクレンとの関係、そして制度再設計という選択肢について、現場の視点から丁寧に読み解きます。 はじめに 最近、SNSやネット番組を中心に「ホクレンは農家を搾取している」「全量出荷を強制してくる」などの声が聞かれるようになりました。中には有名インフルエンサーが「ホクレンが牛乳の価格を操作している」と断言する場面もありました。しかし、現場の実態はどうなのでしょうか? 本記事では、酪農とホクレンの関係について、制度の... -

北海道産肉用牛が日本一へ──鹿児島県を抜いた日
2023年、日本の畜産界において大きな節目となる変化がありました。 これまで63年もの間、肉用牛の出荷額で全国1位の座を守ってきた鹿児島県を、北海道が初めて抜いたという出来事です。 一昔前までは乳牛は多いけれど肉牛のイメージは強くなかった北海道のこの快挙の背景には、独自の生産体制や畜産戦略、そして農業従事者たちの不断の努力がありました。 サクランボもトマトも肉牛も美味しい北海道!最後までどうぞご覧くださいね。 歴史的な首位交代 農林水産省が公表した2023年の生産農業所得統計によると、北海道の肉用牛の産出額は1,224億円(前年比21億円増)となり、鹿児島県の1,208億円(前年比20億円減)をわずかに上回りました。 1960年以降、肉用牛生産額で常にトップを走り... -

「牛なき世界」とは?——私たちの暮らしに起きる3つの異変
「牛なき世界」を想像してみて下さい。代替品のない牛、様々な要因により私たちの今の生活は保てないかも知れません。 -

まとめ記事 畜産業と酪農業の「疲弊しきった現実」と「厳しい未来」
日本の畜産業の苦悩は続きます。明るい未来は訪れるのでしょうか? -

なぜ神明畜産は破綻したのか?拡大戦略に潜む落とし穴
✔ この記事でわかること ▶ 神明畜産が経営破綻に至った背景と拡大戦略のリスク ▶ 畜産業界に共通する“拡大路線”の危うさと持続可能性の課題 ▶ 今後の畜産業界に必要な「守りの視点」とリスク分散戦略 畜産業界において『大規模化』と『効率化』を追求する企業が増える中、 リスクを過小評価した結果、経営破綻に追い込まれるケースが増加しています。 神明畜産の事例はその典型であり、拡大戦略が招いた深刻な結果を浮き彫りにしました。 神明畜産は、豚熱の発生により約5万6,000頭の豚を殺処分し、 資金繰りの悪化を招きました。 最終的に2022年9月には民事再生法を申請しましたが、 その過程には多くのリスクが潜んでいました。 この記事では、神明畜産の倒産の背景やリスク管理の重...
12