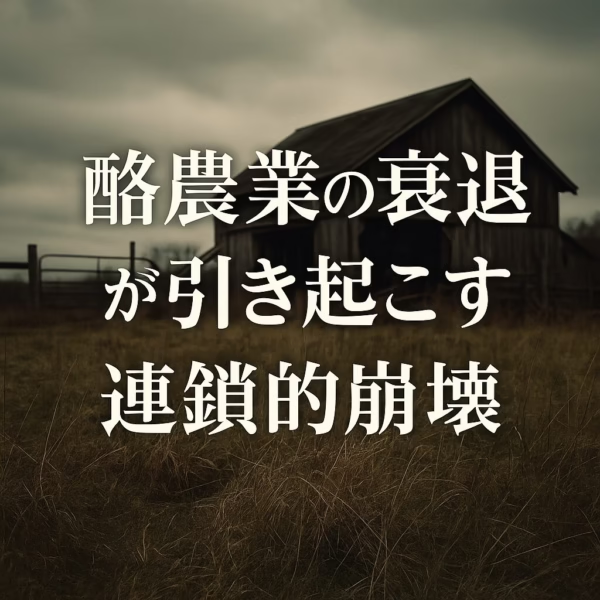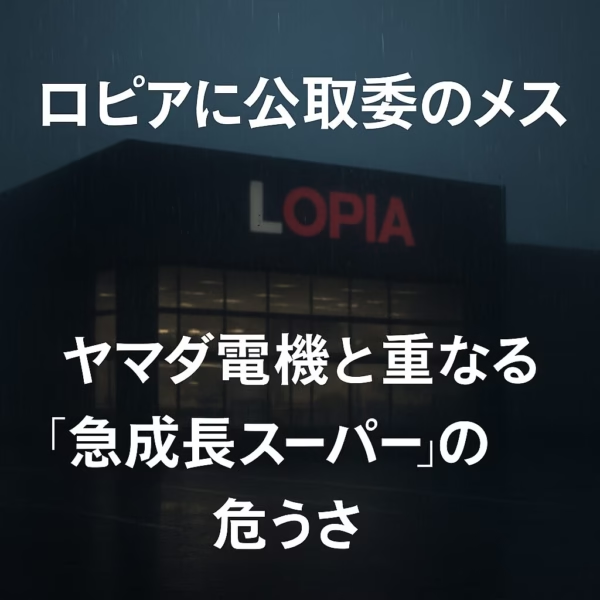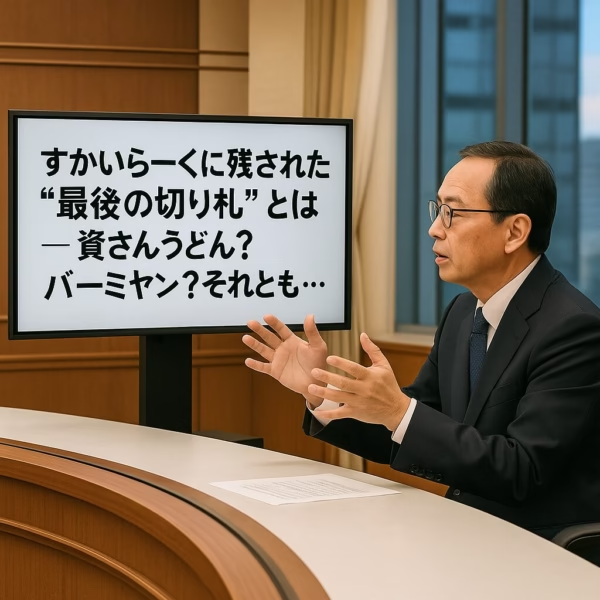経済ニュース– category –
-

群馬の酪農家、10年で半減──酪農業の衰退が引き起こす連鎖的崩壊
群馬県の酪農業がここ10年で半減したという残念なニュースが届きました。急速な減少により地域経済への影響が心配されます。 -

キユーピー ベビーフード事業からの撤退を発表、そして「こども家庭庁」は沈黙
キューピーが不採算となったベビーフード事業からの撤退を発表しました。なぜ子ども家庭庁は動かないのでしょうか? -

【速報】すかいらーくグループ、無料Wi-Fiサービスを終了へ!その裏にある経営戦略とは?
すかいらーくグループの無料Wi-Fiサービス終了、他の飲食チェーン店は追随するのでしょうか? -

ロピアに公取委のメス──ヤマダ電機と重なる“急成長スーパー”の危うさ
エンタメスーパー「ロピア」に公取の立ち入り検査が入りました。今後、小売業が果たすべき役割が問われます! -

福岡のソウルフード 牧のうどん──“店長たちが毎朝、本店に通う”直営チェーンの完成形
福岡県の方にとっては当たり前の存在でも、県外の方から見ると少し不思議に映る──そんな唯一無二のローカルうどんチェーンが地域密着の「牧のうどん」です。 極太でやわらかい麺、スープをどんどん吸って増えていく独特の食感、さらに、「ごぼ天」や「かしわごはん」といった福岡ならではの定番サイドメニュー。これだけでも十分に個性的ですが、実はこのお店、運営の面でも非常に特徴的です。 私はかつて、福岡で自営農家をしていた時期がありました。毎朝、畑へ向かう道中で、糸島市にある「牧のうどん本店」の前を通るのが日課でした。 そのとき、私はいつもの光景を何度も目にしました。まだ日も昇りきらない早朝、複数のバンが本店に集まり、それぞれの店長と思われる方が、巨大な... -

オレンジジュース危機の裏で、グレープフルーツも絶滅寸前──でもシークヮーサーがあるから大丈夫!
最近、日経新聞オンラインでアメリカのフロリダ州のオレンジ危機についての記事を見かけました。 「オレンジジュース用のオレンジが史上最少の収穫量に。アメリカは「輸入拡大」に動いており、日本にも値上げの波が──」 そして「オレンジジュース危機」という耳慣れない言葉がネット上でも散見されていて、商品の大幅な値上げなどを取り上げた特集の記事も出ています。 正直、私には関係ないなと思ったんです。 今ジュース飲んでないんですよ。ダイエット中ですし、そもそも甘い飲み物は卒業済みですし。 私には無関係な話──だと思っていました。でもその裏で、もっと静かに、もっと深刻に消えかけている果物があるのです。 グレープフルーツが「消えかけている」ってご存知でしたか? ... -

もっと早く契約しとけばよかった…楽天カード×楽天モバイルで“実質月546円”の驚き生活!
日々の支払いで「どうせ払うならポイントを貯めたい」と思うのは当然のこと。私自身、楽天カードは以前から使っており、日常のスーパーでの買い物や病院での支払いなどで貯めたポイントを楽天市場で使えるのは「お得だな」と感じていました。 ところが、昨年から楽天モバイルにも加入してみたところ、そのお得度が一気に跳ね上がったのです。月額基本料金の安さはもちろん、何より驚いたのが「ポイントの貯まり方」で、もっと早く契約しておけばと後悔しています。 実際に、2025年1月〜5月のたった5ヶ月間で、楽天モバイル契約者特典として4,844ポイントもSPU(スーパーポイントアップ)で付与されていました。つまり、月額1,078円(税込)の基本料に対し、実質負担はたった546円だった... -

ガスト店長、年収1000万円超の裏側──私が経営者なら「店ごと」譲渡します!
すかいらーくホールディングス(以下 すかいらーくHD)が導入した店長年収1000万円超制度は、人手不足解消と利益率向上という二つの難題に挑む革新的な試みです。 同社は「店長年収1000万円超」の新制度を導入を発表しました。従来の上限840万円から大幅アップとなるこの施策は、各メディアで「飲食業界の人手不足を救う、夢のある制度」とされる中、Yahoo!ニュースでは「相当きつそう」というその実現に疑問を投げかける報道も一部ありました。 Yahoo!ニュースの記事にも取り上げられているように、この取り組みの短期的成果として店長のレベル底上げだけではなく、成功ノウハウも社内に蓄積されて機運も高まることでしょうが、確かに実現するにあたっては様々な問題が生じそうですね... -

丸亀製麺が築く働きがいと未来─直営主義が生む熱血社員たちのリアル
「従業員の幸せなくして、KANDO(感動)は生まれない。」 多くの外食チェーンが掲げるこの理念を、真に行動で示せる企業はどれほどあるでしょうか? トリドールホールディングスが展開する丸亀製麺の山口寛社長は、全店舗を自ら訪問するほど現場主義を貫きます。社員やアルバイトからの評価は高く、経営目標も次々と達成。企業のエンゲージメントは業界屈指です。一見「厳しいブラック企業」と映る環境の中で、働く人々が語るのは「他社とは違う」という誇りと忠誠心。この「時代遅れ」とも思われがちな価値観が、いま、なぜ復活し、機能しているのか? 本記事では、丸亀製麺の「構造」と「熱」、その秘密に迫ります。 なぜ丸亀製麺は“ブラック寸前”でも人が辞めないのか? 丸亀製麺が“... -

すかいらーくに残された“最後の切り札”とは──資さんうどん?バーミヤン?それとも…
かつて「ファミレス王国・日本」を築いたのは、まぎれもなくすかいらーくグループでした。ドリンクバーの先駆けとして外食文化を変革し、全国すべての都道府県への出店を達成。「ガスト」の1,000店舗体制は、“国民的ファミレス”の象徴とも言える存在でした。 しかし今、ファミリーレストランという業態そのものが、大きな転換点に差し掛かっています。家族での外食は「ファミレス」から「回転寿司」や「焼肉食べ放題」へ、単身層の“ちょい食べ”は「コンビニ」や「フードコート」へ──利用シーンそのものが分散し、ファミレスの役割は徐々に薄れつつあるのです。 その変化に最も苦しんでいるのが、皮肉にもこの業態の先駆者であるすかいらーく。特に「ガスト」には、今や“何を食べに行け...