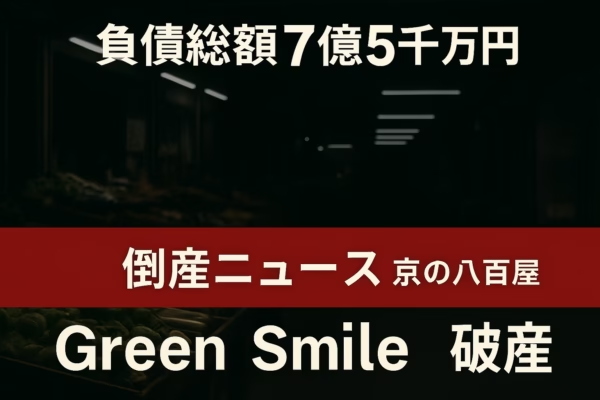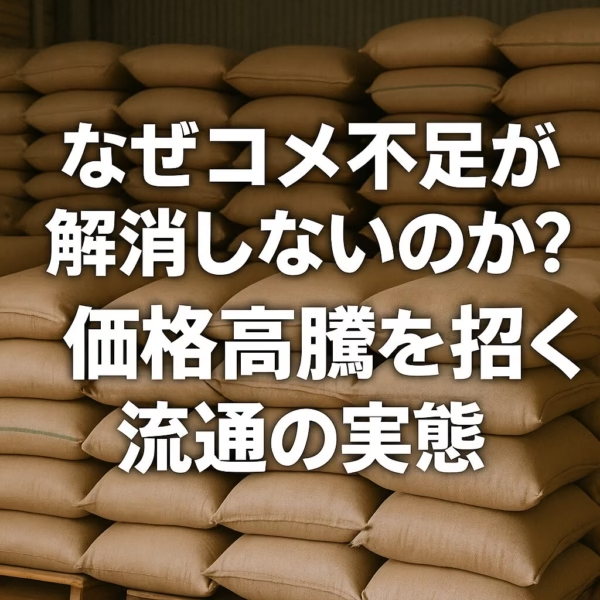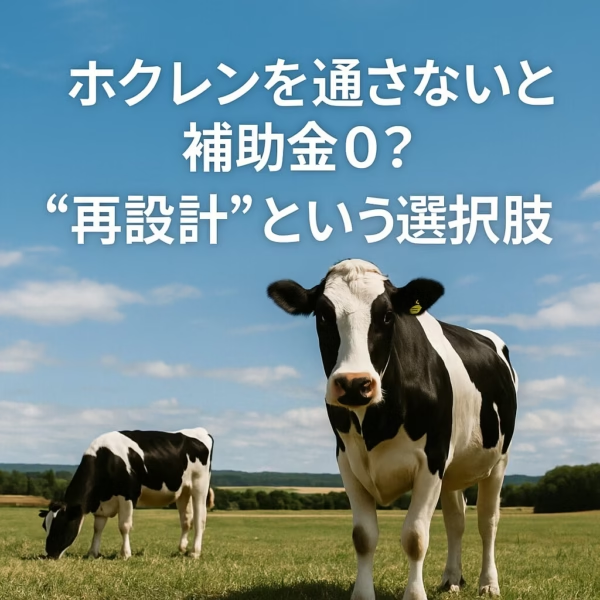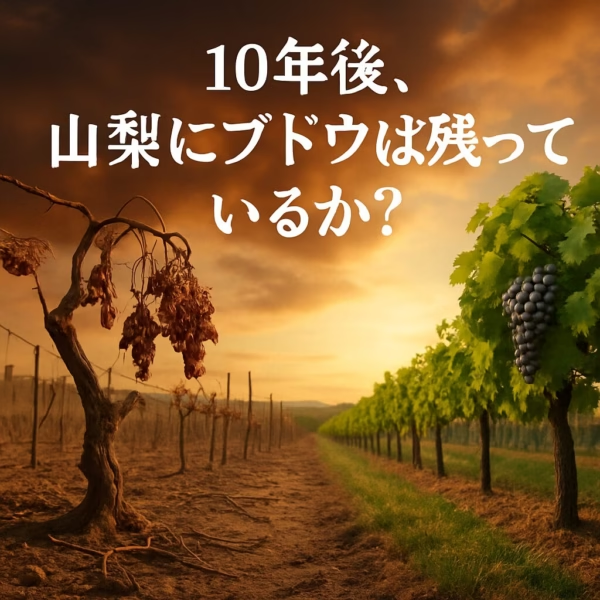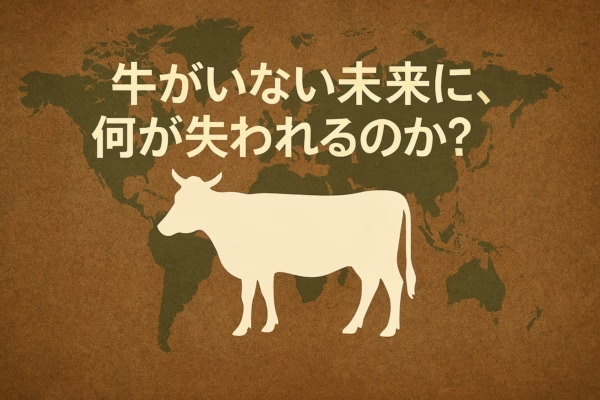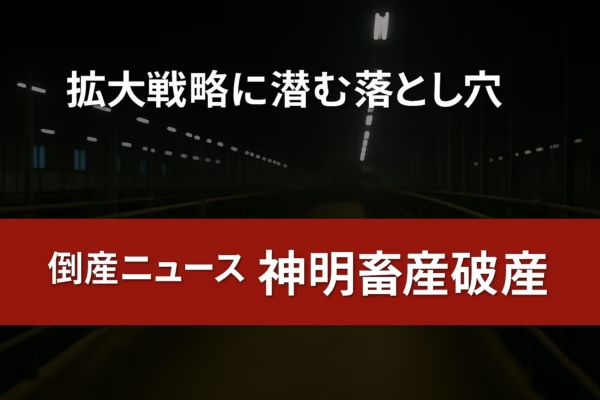食品ほか– category –
-

電力会社と野菜工場:スプレッドとプランツラボラトリーの「明」と「暗」
植物工場の成功例と課題について考察し、未来の農業の可能性を探る内容です。 -

ダイエット中でも会食OK!15kg減量成功者が教える秘訣
ダイエット中でも会食を楽しむ方法をご紹介!私もこの方法で15kg減量に成功しました。 -

京の八百屋「菜珠(さいじゅ)」を運営、日本一カッコいい Green Smileが破産
-

なぜコメ不足が解消しないのか?価格高騰を招く流通の実態
コメが足りない――なのに「在庫はある」と言われる。スーパーでもふるさと納税でも、米は品薄で価格は高騰。この矛盾の裏でいま、日本のコメ流通に何が起きているのか? 本記事では、価格を動かす「買い占め」や「出し惜しみ」の実態、そしてそれを見えなくしている制度の限界と構造的な問題に切り込みます。消費者も生産者も納得できる流通改革の第一歩を、一緒に考えてみませんか? はじめに 「スーパーでコメが高すぎて買えない」「ふるさと納税でもコメの予約が殺到」——。 いま、日本中で"コメ不足"の声が広がっています。農林水産省は「在庫はある」と発表し、2025年春には備蓄米15万トンを市場に放出しました。しかし、それでも米価は下がらず、消費者の不安も沈静化していません... -

ホクレンを通さないと補助金ゼロ?酪農制度の“再設計”という選択肢
「ホクレンに出さないと補助金がもらえない」──そんな話を聞いたことはありませんか?北海道の酪農家が抱える“自由なはずの出荷”と“縛られた制度”の矛盾。年間売上5,000万円でも赤字に苦しみ、廃業へ追い込まれる現実。本記事では、補助金の仕組み、ホクレンとの関係、そして制度再設計という選択肢について、現場の視点から丁寧に読み解きます。 はじめに 最近、SNSやネット番組を中心に「ホクレンは農家を搾取している」「全量出荷を強制してくる」などの声が聞かれるようになりました。中には有名インフルエンサーが「ホクレンが牛乳の価格を操作している」と断言する場面もありました。しかし、現場の実態はどうなのでしょうか? 本記事では、酪農とホクレンの関係について、制度の... -

気候変動で変わる日本のワイン産地:山梨と北海道の現在地
ワインができるのは10年後、皆さんは、どこにブドウの苗を植えますか? -

北海道産肉用牛が日本一へ──鹿児島県を抜いた日
2023年、日本の畜産界において大きな節目となる変化がありました。 これまで63年もの間、肉用牛の出荷額で全国1位の座を守ってきた鹿児島県を、北海道が初めて抜いたという出来事です。 一昔前までは乳牛は多いけれど肉牛のイメージは強くなかった北海道のこの快挙の背景には、独自の生産体制や畜産戦略、そして農業従事者たちの不断の努力がありました。 サクランボもトマトも肉牛も美味しい北海道!最後までどうぞご覧くださいね。 歴史的な首位交代 農林水産省が公表した2023年の生産農業所得統計によると、北海道の肉用牛の産出額は1,224億円(前年比21億円増)となり、鹿児島県の1,208億円(前年比20億円減)をわずかに上回りました。 1960年以降、肉用牛生産額で常にトップを走り... -

「牛なき世界」とは?——私たちの暮らしに起きる3つの異変
「牛なき世界」を想像してみて下さい。代替品のない牛、様々な要因により私たちの今の生活は保てないかも知れません。 -

まとめ記事 畜産業と酪農業の「疲弊しきった現実」と「厳しい未来」
日本の畜産業の苦悩は続きます。明るい未来は訪れるのでしょうか? -

なぜ神明畜産は破綻したのか?拡大戦略に潜む落とし穴
✔ この記事でわかること ▶ 神明畜産が経営破綻に至った背景と拡大戦略のリスク ▶ 畜産業界に共通する“拡大路線”の危うさと持続可能性の課題 ▶ 今後の畜産業界に必要な「守りの視点」とリスク分散戦略 畜産業界において『大規模化』と『効率化』を追求する企業が増える中、 リスクを過小評価した結果、経営破綻に追い込まれるケースが増加しています。 神明畜産の事例はその典型であり、拡大戦略が招いた深刻な結果を浮き彫りにしました。 神明畜産は、豚熱の発生により約5万6,000頭の豚を殺処分し、 資金繰りの悪化を招きました。 最終的に2022年9月には民事再生法を申請しましたが、 その過程には多くのリスクが潜んでいました。 この記事では、神明畜産の倒産の背景やリスク管理の重...