2025年5月19日、吉野家ホールディングスは2029年度までの中期計画にラーメン事業を据えて発表しました。
報道各社は一斉にそのニュースを「好意的」に伝えておりますが、詳細な分析を重ねた結果、この達成は「ほぼ無理」だと思われます。
この「ほぼ無理」な中期経営計画発表の背景には直近の決算で売上は前年比でアップしたものの「営業利益は前年比で8.4%のマイナス」となった反省を踏まえ、極めてチャレンジングなものを出さざるを得なかった事情によるものと思われます。
<2025年2月期決算:吉野家ホールディングス>
- 売上高:2,049.8億円(前年同期比 +9.3%)
- 営業利益:73.0億円(同 -8.4%)
- 純利益:38.0億円(同 -32.1%)
- 営業利益率:3.6%(前年同期 4.3%)
営業利益率の低下、純利益の大幅減少は、コスト増や競争激化による影響です。こうした厳しい状況の中、吉野家ホールディングスは新たな成長戦略としてラーメン事業を中核に据えた新中期経営計画(2025年度~2029年度)を打ち出しましたが…
この記事では、この計画の概要、達成の可能性、リスク、そして注目すべきポイントを徹底分析します。
ほぼ無理な中期経営計画の概要
- 期間:2025年度~2029年度
- テーマ:『変身』と『成長』
- 目標:
- 売上高:3,000億円
- 営業利益:150億円
- ROIC:7.0%
- D/Eレシオ:0.9倍以内
- 投資計画:総額1,300億円(成長投資450億円、M&A投資400億円)
売上高3,000億円、営業利益150億円 ラーメン事業で牽引は、ほぼ無理です
✅ ポジティブ要因
- ラーメン事業の急成長:売上400億円(2024年:80億円→2029年:400億円)。ただし、営業利益成長率(CAGR 58.5%)が売上高成長率(CAGR 38.0%)を上回っており、収益性向上が期待されているが、達成可能性には疑問が残る。
- はなまる事業の成長:売上309億円(2024年)→480億円(2029年)。営業利益率の上昇が期待されている。しかしながら、以下の点より過信禁物と分析します。
- 元々かけうどん1杯105円から始まったフランチャイズ中心の店舗で、2025年1月の値上げで現在は360円となり客離れが深刻化してます。
- 更なる値上げで営業利益を改善するのは現実問題、ハードルが高い。
- 海外事業の強化:中国・東南アジアへの出店拡大
- IT・デジタル投資:150億円の効率化投資
❌ リスク要因
✅ 中国市場での地政学リスク
吉野家ホールディングスにとって、ラーメン事業の海外展開は中国市場が鍵を握っています。しかし、この中国市場は台湾有事を除いても、以下の通り極めて高い地政学リスクを抱えています。
1. 政治的・規制リスク
- 中国政府の規制強化:営業許可の取り消し、衛生基準の厳格化、データ規制など、突然の政策変更リスクがあります。
- 法的環境の不透明さ:突然の税制変更、外資企業に対する特別課税の導入。
- 中国政府の規制強化:営業許可の取り消し、衛生基準の厳格化、データ規制など、突然の政策変更リスクがあります。
- 反日感情の高まり:日中関係が悪化すると、反日感情が高まり、店舗への不買運動や営業妨害のリスクがあります。
- 政治的圧力:中国政府は国内企業を優遇し、外資系企業(特に日本企業)には厳しい規制を課す可能性があります。
- 法的環境の不透明さ:突然の税制変更、外資企業に対する特別課税の導入など、不透明な法的環境に依存しています。
- ゼロコロナ政策再導入リスク:突然のロックダウンや営業制限が再発する可能性も否定できません。
2. 中国ローカル競合の台頭
- 味千ラーメン、ラーメン無敵家、現地ローカルブランドが強力で、価格・サービスで差別化が難しい。
3. 日本系ラーメンチェーンとの競争
- 一風堂:中国主要都市に展開し、ブランド認知度が高い。
- 幸楽苑:現地パートナーと提携し、現地化戦略を進めています。
- その他:日本系ラーメンブランドが既にプレゼンスを確立し、吉野家ラーメンが後発組となります。 吉野家ホールディングスにとって、ラーメン事業の海外展開は中国市場が鍵を握っています。しかし、この中国市場は極めて高い地政学リスクを抱えています。
確かに吉野家のラーメン事業は昨日今日に始まったものではありませんが、既に数百億円の売上規模のブランドに立ち向かうには心もとない戦力といわざるを得ません。
- 幸楽苑:店舗縮小とコスト削減で赤字を回避しようとしています。
- 一風堂:国内では店舗再編と高価格戦略で利益率を維持していますが、競争は厳しい。
- 天下一品:こってりラーメンで固定ファンを持つものの、新規客獲得に苦戦し、FC店舗の閉鎖も続いています。
- 家系ラーメン:濃厚な豚骨醤油スープと太麺という独自のカラーから、「強力な固定ファン」を有します。
- ご当地ラーメン:博多、札幌、喜多方など地元に根付いたラーメン屋との競争は厳しい戦いです
吉野家は昨日今日、ラーメン事業を始めた訳ではありません。2024年5月1日付で、ラーメン店向けの麺やスープ、タレなどを製造・販売する宝産業株式会社(京都市)の全株式を取得し、子会社化しました。
宝産業は1970年に京都で創業され、国内には京都工場と関東工場、海外にはアメリカ、フランス、タイ、インドネシア、フィリピンに拠点を展開しています。同社では、ストレート麺や縮れ麺、細麺など60種類以上の麺と、豚骨、鶏ガラ、魚介など20種類以上のスープを供給しており、餃子や焼き豚、メンマなどの製造も手掛けています。
吉野家HDはこれまでに、ラーメン店「せたが屋」(2016年)や、「ばり嗎」「とりの助」を展開するウィズリンク(2019年)を買収しており、今回の宝産業買収はラーメン分野で3社目の買収となります。
この買収により、吉野家HDはラーメン事業のバリューチェーンを強化し、製造から販売までの一連の流通網を活用することで、調達リスクの分散やコスト削減を目指しています。
吉野家HDはラーメン事業を次なる成長の柱と位置づけ、国内外での事業拡大を目指しています。しかし、2024年2月に発表された決算では、ラーメン事業の売上実績は80億円、営業利益はわずか4億円にとどまっています。
競争の激しい日本、そして中国市場を制して「2029年度に売上400億円、営業利益40億円」を達成、そして世界1位を目指すには、更なる戦力強化が求められるのではないでしょうか。
当然、吉野家は、今後のM&A戦略(合併・買収)を推進する方針を明確にしています。具体的には、京都のラーメン企業「キラメキノ未来」などを既に買収しており、今後も同様の戦略を継続する意向を示しています。
しかし「キラメキノ未来」は、関西を中心に鶏白湯ラーメンや台湾まぜそばで人気ですが、このブランドが吉野家の既存ラーメンブランドとシナジーを生む可能性は低く、むしろ「カニバリゼーション(市場の食い合い)」が発生するリスクが高いと考えられます。
それ以外にも原材料コストの上昇(牛肉、小麦、油価格の高騰)、国内人件費の上昇(最低賃金アップ、定期昇給)、中国以外の地政学リスク(ウクライナ情勢、為替リスク)、国内ラーメン市場の競争激化(国内ラーメン市場はすでに飽和状態で、競合は激化しています)などは言わずもがなです。
✅ 吉野家傘下の既存ラーメンブランドとの競合
- キラメキノ未来:鶏白湯ラーメンや台湾まぜそばで人気。
- せたが屋:醤油ラーメンを中心としたブランド。
- ばり嗎:九州豚骨ラーメンが主力。
- とりの助:鶏白湯ラーメンに特化。
❌ なぜカニバリゼーションが発生するのか?
- ブランド間競争:吉野家HDは複数のラーメンブランドを展開し、それぞれが同一エリアで顧客を奪い合う可能性。
- 既存店舗の閉鎖リスク:新ブランドを優先して既存店舗が閉鎖される可能性も。
- 地域特性に応じたブランド最適化が未成熟:同一エリアでブランド間競争が激化。
❓ 収益性に対する違和感
吉野家ホールディングスの中期計画における各セグメントの営業利益成長率(CAGR)が、売上高成長率を上回っている点は大きな違和感があります。
- 牛丼事業は低価格・薄利多売であり、利益率の向上は困難:価格競争が激しく、売上高が伸びてもコストも比例して増加するはず。
- はなまる・ラーメン事業でも同様の違和感:特にラーメン事業は成長期にもかかわらず、利益率が急速に向上する前提は非現実的。
❗ 赤字転落リスク:甘すぎる営業利益率5%の罠
吉野家ホールディングスは2029年度に売上高3,000億円、営業利益150億円(営業利益率5%)を目指しています。しかし、この目標は現実味に欠け、むしろ赤字転落のリスクさえ考えられます。
- ラーメン事業の先行投資は借入金依存:成長投資1,300億円のうち、ラーメン事業へのM&A(400億円)や新規出店・設備投資(200億円)は借入金で賄われる可能性が高い。
- ラーメン事業が赤字に転落すれば、借入金返済が困難:2029年度のセグメント計画は売上400億円・営業利益40億円ですが先行するチェーン店での実績で、吉野家ホールディングスの掲げる営業利益率10%に達しているチェーン店はなく未達に終わる可能性が大で、実際には競争激化と中国リスク次第で赤字になるリスクがある。
| 企業名 | 営業利益率(概算) | 備考 |
|---|---|---|
| 一風堂(力の源HD) | 約5〜6% | 国内外で展開。高価格帯でブランド力が強いが、原材料費や人件費の高騰が影響。 |
| 幸楽苑 | 約2〜3% | 低価格帯で大量出店。価格競争が激しく、利益率は低め。 |
| 日高屋(ハイデイ日高) | 約7〜8% | 首都圏中心に展開。低価格帯ながらも効率的な店舗運営で比較的高い利益率を維持。 |
| 味千ラーメン(中国) | 約3〜4% | 中国本土で大規模展開。現地化戦略を進めるも、競争激化やコスト増が課題。 |
- D/Eレシオ(0.9倍以内)は借入金増加を前提:自己資本に対する借入金の比率が高まり、返済リスクが急増。年間返済額はXX億円に達する可能性。
- 返済原資は他セグメントに依存:ラーメン事業が利益を生まなければ、牛丼やはなまるの利益で返済を補う必要がありますが、どちらも利益率は低い。
✅ 競争激化:ラーメン事業の失敗リスク
- ラーメン事業の先行投資は借入金依存:成長投資1,300億円のうち、ラーメン事業へのM&A(400億円)や新規出店・設備投資(200億円)は借入金で賄われる可能性が高い。
- ラーメン事業が赤字に転落すれば、借入金返済が困難:計画は売上400億円・利益率10%ですが、実際には競争激化と中国リスクで赤字になるリスクが高い。
- D/Eレシオ(0.9倍以内)は借入金増加を前提:自己資本に対する借入金の比率が高まり、金利上昇局面でもあり、返済リスクが急増する恐れが高い。
- 返済原資は他セグメントに依存:ラーメン事業が利益を生まなければ、牛丼やはなまるの利益で返済を補う必要があるが、どちらも利益率は低い。
ラーメン事業の失敗は単に利益減ではなく、借入金返済という致命的な問題を引き起こす可能性があるのです。
吉野家ホールディングスは2029年度に売上高3,000億円、営業利益150億円(営業利益率5%)を目指しています。しかし、この目標は現実味に欠け、むしろ赤字転落のリスクが高いと考えられます。
- 牛丼事業は利益率3-4%が限界:薄利多売でコスト増に苦しむ。
- ラーメン事業は利益率10%は非現実的:競争激化で原価率も高い。
- 中国市場のリスク:反日感情、規制強化で突然の業績悪化リスク。
- はなまる事業も利益率は低い:安価なうどんは価格上昇が難しい。
投資家はこの計画を信じるのは危険です。吉野家株は早期に売却を検討した方が良いかもしれません。
吉野家ホールディングスの中期計画における各セグメントの営業利益成長率(CAGR)が、売上高成長率を上回っている点は大きな違和感があります。
この矛盾は、以下の2つの仮説で説明できます:
1.コスト削減効果を過度に楽観視:IT投資やM&Aでの効率化が過度に期待されている。
2.価格引き上げ効果を過大評価:特にラーメン事業での高価格メニューが想定されているが、競争激化で実現困難の可能性。
→ 現状、この中期計画の実現の見込みは限りなく低いものとして捉えるべきです。
セグメント別成長戦略: ラーメン事業と海外事業で2重計上?
✅ 吉野家(牛丼事業)
- 売上目標:1,880億円(2029年)
- 成長戦略:
- メニューの多様化(定食、サイドメニュー、季節限定メニュー)
- デジタル化でオーダー効率を向上(モバイルオーダー、セルフレジ)
- コスト削減(食材調達の効率化、店舗人件費の最適化)
✅ はなまる(うどん事業)
- 売上目標:480億円(2029年)
- 成長戦略:
- 都市部・郊外の新規出店(駅近・商業施設への進出)
- 高価格メニュー(天ぷら、肉うどん)の強化
- デリバリー・テイクアウト事業の拡大
✅ ラーメン事業
- 売上目標:400億円(2029年)
- 成長戦略:
- 国内:競合との差別化(味、価格帯、店舗デザイン)
- 海外:特に中国市場での拡大(フランチャイズ展開、M&Aでブランド拡充)
- 高価格ラーメンブランドの導入
✅ 海外事業
- 売上目標:310億円(2029年)
❓ 海外事業とラーメン事業の不明瞭な関係
吉野家ホールディングスの中期経営計画では「海外事業」と「ラーメン事業」が明確に分離されているように見えますが、実際にはその境界は極めて曖昧です。
- ラーメン事業の海外展開はほぼ中国市場に依存:売上400億円のうち、相当部分が中国市場からの収益が見込まれています。
- 海外事業310億円は重複の可能性:ラーメン事業の売上が中国市場で拡大することを前提としながら、海外事業としても中国市場をカウントしている疑いがあります。
- 数字のつじつま合わせ:売上3,000億円を達成するために、海外事業という曖昧な項目で調整されている可能性があります。
このように、「海外事業」と「ラーメン事業」は実質的に重複しております。
この点においても売上目標3,000億円の信頼性には疑問しかなく、ほぼ無理から、「無理」に変わりました
総括:ラーメン事業では迫力不足で、楽観的なシナリオでも「ほぼ無理」
吉野家ホールディングスの中期経営計画は、私たちが以下の通り描く楽観的なシナリオであっても達成は「ほぼ無理」であり、計画未達に終わる可能性が高いと言えます。
- 現実的なシナリオ:2025年決算数字を元に、今後4%を成長したと仮定し、営業利益率が現状よりやや悪化するものと試算したところ、「売上高2,398億円、営業利益83.9億円(営業利益率3.5%)」に留まり、目標「売上高3,000送園、営業利益150億円」には大きく届かないと思われます。
- 悲観的なシナリオ:ラーメン事業が中国市場で地政学リスクに直面し、赤字転落。借入金返済に苦しみ、財務悪化が進むリスクも否定できません。
この計画は、「ラーメン事業の成功」と「コスト効率化」に大きく依存していますが、以下の理由で実現は厳しいと考えられます。
投資家としては、この計画のリスクを冷静に見極める必要があります。吉野家ホールディングスの株式は、楽観的な目標が実現されると信じるのではなく、現実的な収益性と借入金リスクに注意して評価すべきです。
🍅 追記:あのユニクロもかつて“野菜事業”で世界を目指していた
覚えていらっしゃる方も多いと思いますが、2000年代初頭、ファーストリテイリング(ユニクロ)は農業に進出し、「野菜で世界一」を目指していました。山口県に農場を開設し、40代の若手を代表に抜擢し、「服と同じように野菜も管理できる」という思想のもと、野菜の事業化に挑みました。
しかし、自然を相手にする農業は、工場で服を作るように思い通りにはいかず、2〜3年で撤退。担当者は更迭され、事業はなかったことになりました。
もしかして事業がうまく行ってたら、夏は「エアリズム」と「トマト」を、冬は「ヒートテック」と「大根&白菜」をユニクロの店舗に買いに行く世界線がもしかして…いやいや、あり得ないですね。
畑違いの分野に“トップの意思”だけで突っ込み、既存ノウハウを転用してスケールさせようとする…。 ラーメンも農業も、「現場」がモノを言う産業です。
今回の吉野家の中期計画を見て、あのユニクロの野菜事業を思い出さずにはいられません。
注意事項
本資料には、吉野家ホールディングス株式会社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら将来の計画予測数値などは、現在入手可能な情報を元に、弊社が計画・予測したものであります。
実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの計画とは異なる場合があり、この資料はその実現を確約したり、保証するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社は一切責任を負いませんので、ご承知おきください。
お問い合わせ先 誠ライフケア 👉https://www.makoto-lifecare.com/
 パンチです
パンチです業績予測の元プロの私が本気で分析してみました!
情報を集めれば集めるほどこの計画の達成は「ほぼ無理」です。




今後は業績予測にも取り組みますね。
リクエストがあれば是非お知らせ下さいね!
-



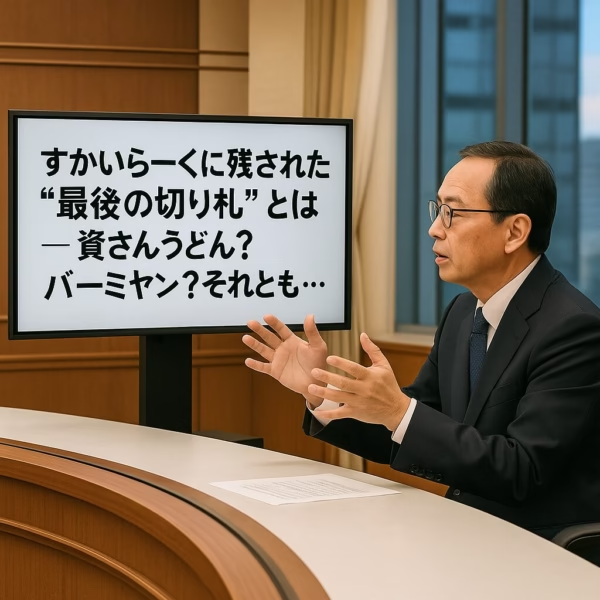
すかいらーくに残された“最後の切り札”とは──資さんうどん?バーミヤン?それとも…
かつて「ファミレス王国・日本」を築いたのは、まぎれもなくすかいらーくグループでした。ドリンクバーの先駆けとして外食文化を変革し、全国すべての都道府県への出店… -



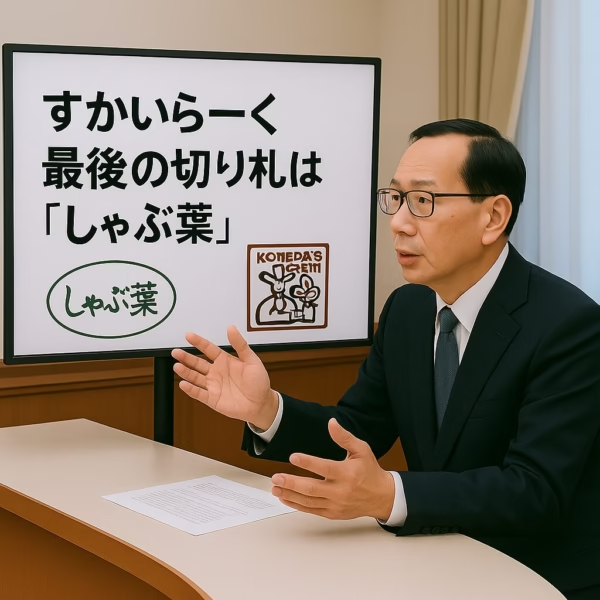
すかいらーく最後の切り札は「しゃぶ葉」-FC転換がもたらす経営再建の道すじ
全都道府県制覇、ドリンクバーの先駆け、1,000店舗達成──かつて“外食の王者”と呼ばれたすかいらーくグループは、今や時代の変化に取り残され、その主力ブランド「ガスト… -



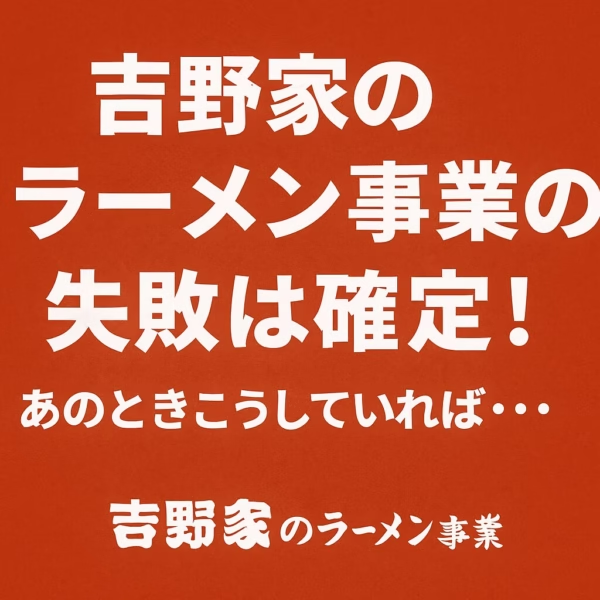
吉野家ラーメン事業の失敗は確定!あのときこうしていれば・・・
吉野家グループホールディングス(以下、吉野家HD)は、世界一のラーメン事業を目指すと発表しましたが、その成功への道は既に誤っていると言わざるを得ません。 では、…

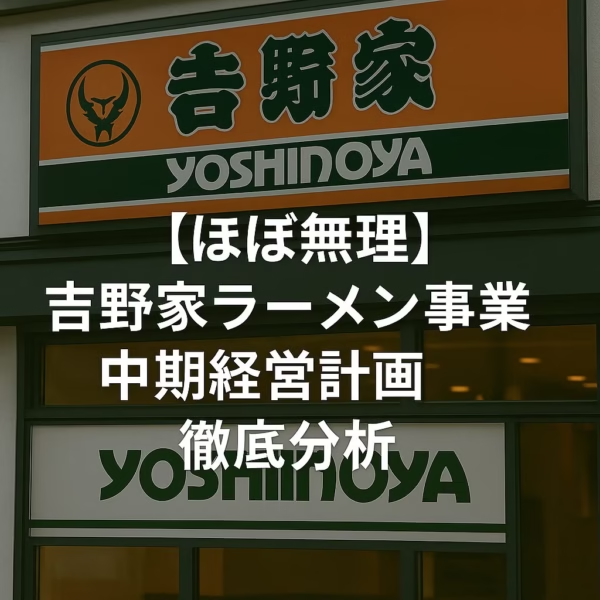
コメント